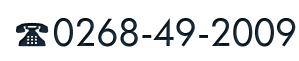校長日記
学校の出来事などを、校長の目線で言葉にしていこうと思います。
ご覧いただけたら幸いです。
| 4月の日記 | 5月の日記 | 6月の日記 | 7月の日記 | 8月の日記 | 9月の日記 |
| 10月の日記 | 11月の日記 | 12月の日記 | 1月の日記 | 2月の日記 | 3月の日記 |
2月24日(火) 参観日② ~4年生~
本日の参観日、予定では1年生から3年生まででしたが、前回の参観日で4年生が授業参観できなかったため、本日、4年生も参観日となりました。
4年生は、音楽会以降、取り組みを続けてきた表現活動を保護者の前で発表しました。予定では体育館のステージでの発表でしたが、体育館は他の学年が利用するため、体育館隣のミーティングルームで行いました。若干狭さを感じましたが、保護者の目の前で発表できたので、発表する側も、見る側も、どちらにとっても場所の変更は良かったように感じました。
プラスチック製のコップをリズムに合わせて移動させるカップスの発表、リズムに合わせて縄を跳ぶダブルダッチの発表、リズムに合わせてけん玉技を披露するリズムけん玉の発表、リズムに合わせたダンスの発表と、4つのチームそれぞれが発表しました。発表しない時には、歓声を上げるなど、発表するときも、友だちの発表を見る時も、みんながみんな活躍していました。司会進行もお見事でした。それぞれの発表の後には、全員でのダンスの発表を披露し、終盤には、10歳の節目として、10年間のお礼の気持ちを記したお手紙を保護者に届けました。目頭を熱くしたお家の方もいたかと思います。
本日の参観日をもって、今年度の参観日は終了しました。限られた回数ではありましたが、毎回、大勢の保護者の皆様には、お忙しい中学校へ来て、子どもたちの学ぶ姿、活躍する姿を見ていただきました。今週を終えると、いよいよ3月、今年度最後の月となります。最後の3月も、最後の3月だからこそ、それぞれの学級ならではの、1年間の締めくくりをしていくはずです。こうご期待です!!
2月24日(火) 参観日 ~1・2・3年~
本日5時間目、1年生から3年生の参観日が予定通り行われました。(4年生も同時刻に参観日を行いましたが、様子は後ほど・・・)
それぞれの参観授業の様子は以下の通りです。
1年1組:保護者をお客さんとしてお迎えし、お店屋さんを開きました。楽器屋、果物屋、お菓子屋、
新鮮な魚屋、子どもたちはそれぞれの店員となり、学級独自通貨でのやりとりを行いまし
た。お釣りが生じた時には、習った算数の計算を駆使し、間違えないように計算することが
できました。
1年2組:3学期頑張ってきた、縄跳びの技を披露していました。後ろ交差跳び、あや跳び、二重跳び
など、難しい技にチャレンジする姿もありました。残り10秒になると、係の子がカウント
ダウンを始めていました。大繩にもチャレンジし、保護者を前にして、見事、新記録達成で
す。おめでとう!
2年生:1年生同様、お店を開き、お家も人たちを楽しませました。ゲームコーナーや商品にとてもこ
だわっていて、本格的なゲームセンターさながらのお店となっていました。手作りのレジ、リ
アルな的あて、館内に流れるオルガンによりBGMなど、自分のやりたいことを、とことんやり
きっていました。
3年生:最後の参観日に合わせ、親子レクを体育館で行いました。大勢の保護者の方が参加してくださ
しました。ありがとうございます。私が見た時には、ちょうどドッジボールが終わる時で、ど
うやら大人チームが勝ったようです!!3年生のみんな残念!ほかにも、「大繩チャレンジ」
「イントロクイズ」などなど、楽しい活動が目白押しでした。
それぞれの学年、学級ならではの、楽しくもあり、素敵な時間となりました。この一年の子どもたちの成長を感じていただけたかと思います。来校してくださった保護者のみなまさ、ありがとうございました。
2月24日(火) 親子一緒に ~給食試食会(1年)~
今年度2回目の給食試食会が行われました。今回は、1年生でした。お昼の時間に合わせ、1年生の多くの保護者の方に来ていただきました。お忙しい中、ご都合つけていただき、ありがとうございます。
会場はランチルーム。子どもたちは、自分の親が来ているかどうか気になり、いることを確認すると一安心。逆に、時間になっても来ていることが確認できない子は、そわそわしだし、ようやく来たことを確認すると、「もう、待ったぞ!」若干おこりつつも、表情はうれしさに溢れていました。
1組、2組、それぞれ準備を終えると、クラスごとに「いただきます」、給食を食べながらの親子の会話は今日でないとできません。子どもたち、本当にうれしそうでした。ここ数年、コロナ禍の影響で試食会を行うことができないでいましたが、昨年度から試食会が復活し、今年度は今回の1年生、前回の2年生と、年に2回行いましたが、来年度からは通常開催に戻るため、1年生のみ、年1回の開催となります。
青木小(青木中、青木保育園も含め)は自校給食、自慢の給食です。保護者の方が給食を食べられる機会は試食会のみです。来年度入学する保護者のみなさま、ぜひ、この試食会の機会を楽しみにしていてくださいね。そして、毎回のことになりますが、調理員のみなさん、本当においしい給食を、いつもいつもありがとうございます。
2月20日(金) 今回は低学年 ~体育集会 大繩チャレンジ~
前回は高学年の大繩チャレンジが体育集会で行われました。今回は1年生から3年生が体育館に集まり、5分間の大繩にチャレンジしました。回すの先生と子どもですが、2年生では大繩を回す器具を活用し、担任のK先生はひとりで回していました。
練習タイムが終わり、いよいよ5分間チャレンジが始まりました。1年生から3年生、それぞれの学級で、「い~ち、に~い、さ~ん・・・」と、跳ぶことに増えていく回数をカウントする声が聞こえてきました。引っかかっても、「どんまい!!大丈夫」、リズムよく飛び続けると、「その調子!!いいよ」の声。チャレンジタイムが残り少なくなるにつれ、カウントする声のボリュームが大きく鳴っていきました。そして終わりを告げるブザーが鳴り、学年ごとステージ前に集まり、1年生から記録を発表していきました。1年2組と2年生は、この時間に記録を更新し、大喜び。
最後、感想発表となりました。新記録を出した2年生からは、「協力できたから、新記録が出た」と喜びの声、3年生からはいつも通りの好記録を出すことができず、悔しさを語る姿がありました。
5分間、チャレンジする子どもたちの様子を見て、大繩を始めた頃よりも、間を空けることなく、リズミカルに跳べるようになっている姿に、時間をつくってクラスみんなで取り組んできたことが伝わってきました。児童玄関に掲示されている記録用のホワイトボードは、まだ掲示されるはずです。「他のクラスよりも」の気持ちももちろんあるかと思いますが、自分たちのクラスで掲げた目標記録の更新目指し、まだまだ頑張ってほしいと思います。
寒い中、がんばりました!!子どもたちの跳ぶタイミングに合わせつつ、上手に縄を回した先生がた、ありがとうございました。
2月19日(木) 小学校最後の参観日(参加日) ~6年生~
本日の5時間目、6年生の参観授業がありました。会場は体育館でした。
実は先日、職員室のメールボックス(個人ボックス)に、6年生が作成したお知らせ通知が入っていました。何だろうと、その通知を見ると、そこには、「6学年参加日のお知らせ」と表題が書かれていました。字の通り、授業を教室で”参観”するのではなく、保護者が”参加”し、子どもと一緒に活動する1時間のメニュー(流れ)が記されていました。内容は「風船リレー」「私は誰でしょう」「サビクイズ」、3つの活動を行うことになっていました。
当日です。体育館へ行くと、1つ目の「風船リレー」のルール説明をステージ上で担当する子たちがしているところでした。保護者が2チーム、子どもたちが2チーム、合計4チームに分かれ、段ボールで作ったラケットで風船を打ち上げながら風船を運び、それをリレー形式で繰り返していくというものでした。風船の大きさや穂数制限といったハンデもあり、冒頭から大盛り上がりでした。
2つめの活動(競技)はNGワードでしたが、時間が足りず、3つ目の「サビクイズ」も行われました。これも4チーム対抗戦で、昭和・平成・令和のヒットソングのサビ部分が流れ、それを聞いて曲名を当てるというものでした。昭和ソングが流れると、大人チームは即座に分かりホワイトボードに曲名を書き込むと、子どもチームはというと、こちらも悩むことなく瞬時に曲名を書いていました。10問近くが出され、テンポよく進んでいきました。
本日の活動も、担任が進める形ではなく、子どもたちが役割を分担しすべて自分たちで進めていました。さらに、今回の参加日は、本日をもって終了ではなく、事後アンケートをとり、今回の企画がどうだったかの感想を集め、フィードバックを行うそうです。やって終わりではなく、やったことがどうだったのかの声を聞くことで、自分たちの活動を自己評価する経験は、貴重な体験になるはずです。6年生のみなさん、お見事でした。そして、お忙しい中、ご参加いただいた保護者のみなさま、ありがとうございました。
2月17日(火) 来月の今日は・・・
1年生のベランダに咲くパンジーです。各教室のベランダには、プランターに咲く色とりどりのパンジーが置かれています。春の兆しを感じる陽を浴びて、それぞれのパンジーが寒い冬を乗り越え、1つまた1つと咲いています。
こちらパンジー、来月17日には、教室ではなく体育館のフロアにならび、一年をしめくくる、学校にとっても子どもたちにとっても大切な”行事”を見守ります。卒業式です。年が明けたと思えば1月が終わり、2月になったことをこちらの日記に綴った節分祭から、すでに2週間が過ぎようとしています。2月も後半となれば、卒業式までの日々はあっという間です。
6年生の教室、あるいは廊下には、卒業制作が並び、卒業式の呼びかけプロジェクトも動き出しました。隣の教室の5年生では、児童会を引き継ぐ日が刻々と迫ると同時に、全校で行う6年生を送る会の準備も進められています。
明日から過ごす1ヶ月は、今年度をしめくくる限られた1ヶ月となります。6年生にとっては小学校とお別れする時が迫るわけですが、1年生から5年生にとっても、その学年とお別れする時が迫ってきます。学級ならではの中核活動をしめくくり、その学年での学びをしっかりと学びきり、その学年を堂々と卒業するわたしとなって、小学校とお別れする6年生にとっての大切な3月17日を迎えてほしいと思います。6年生にとっても、1年生から5年生にとっても、明日からの限られた日々を、大切にすごしてほしいと思います。
2月17日(火) なわとびチャレンジ ~体育集会~
ミラノ・コルチナ五輪、フィギュアのペアで、日本代表の三浦・木原ペアが悲願の金メダルを獲得したという感動的なニュースが流れた朝、体育館では、低学年のなわとびチャレンジが行われました。先週金曜日には高学年の大縄チャレンジが行われ、それに引き続いての体育集会でした。
今回は、大繩ではなく個人チャレンジで、前回し跳び、後ろ回し跳び、駆け足跳び、あや跳び、交差跳びに二重跳びと、トータル6つの技の中から、一人一人がチャレンジする技を決め、決められた時間にその技を跳び続けられるかどうか挑みました。私は、あや跳びチャレンジから見ましたが、チャレンジする子の表情は真剣そのものでした。途中で引っかかるとその場で終わりとなるため、悔しがる子もいましたが、引っかからずに跳び続ける友だちに「がんばれ!!」と声をかける子もたくさんいました。
左の写真は、3年生のKさんが、交差跳びにチャレンジしている場面です。交差跳びを跳び続けることは難しいようで、一人また一人と引っかかる中、最後まで飛び続けたのがKさんでした。残り5秒くらいからはカウントダウンが始まり、終了を伝えるブザーが鳴ると、跳び続けたKさんに向けて、賞賛の拍手が送られました。Kさん、とってもうれしそうでした。
挑戦する技が一方的に決められるのではなく、自分が挑みたい技を自己決定し、大勢の前でチャレンジするということ。このこと1つとっても、子どもにとっては大きな挑戦です。4年前の北京五輪、男子ハーフパイプで平野選手と金メダルを争ったアメリカ代表のレジェンド、ショーン選手は、「大切なのは、成功するかしないかではなく、挑戦するかしないかだ」と語りました。チャレンジに大小は関係ありません。その子にとってのチャレンジが、成長につながっていくはずです。全校みんなで、まだまだチャレンジしていこう!!右の写真は、1年生の大繩にチェレンジする様子です。体育集会を終えると、教室で早速大繩を始めていました。クラスの目標回数まであと一歩のところまで来ていました。がんばれ~~~
2月12日(木) だれにとっても本日は特別な日
本日は、6年生のみ学校に残り、1年生から5年生まで、そり・スキー教室があり、奥ダボススキー場で過ごしました。天気は写真にある通り最高の天気でした。ここまで天気になる菅平はめずらしいと思います。天気に恵まれた特別な日となりました。
1、2年生はそりを思う存分楽しみました。一人ですべり、友だちと一緒に二人乗りをし、私も誘われ、何と三人乗りまでしてしまいました。ゲレンデをここまで思いっきりそりができることなんてそうはありません。1、2年生にとって特別な日となりました。
3年生から5年生までは、スキーに挑戦しました。今年度他県から転校してきた子に聞いた所、「初めてだよ」とのこと。お昼タイムにちょうど鉢合わせしたので、聞いてみたところ、「まあまあ、滑れるようになったよ」と一言。そう語る表情は、とってもニコニコでした。この子にとっても、3年生から5年生みんなにとっても、やっぱり今日は特別な日。
そして最後は6年生。学校に6年生だけで過ごせる日など、そうはありません。そのため6年生はこの日のために、担任の先生にお願いを(説得し)、2時間の時間をいただき、校内すべてを使っての学校かくれんぼと学校鬼ごっこを行いました。私は菅平へ行っていたので、その時の様子を見ることはできませんでしたが、学校へ戻り様子を聞くと、最高に楽しい時間だったとのこと。お昼もランチルームで、校内にいる先生方をお招きし、この日だけのスペシャルな時間になったそうです。これまた特別な日。
この日は、全校にとって、唯一無二の特別な一日となりました。
2月11日(水) 道の駅にて ~5年生販売活動~
9時より、道の駅あおきで、5年生が能登復興支援プロジェクトと題し、販売活動を行いました。昨日の校長日記に掲載したとおり、前日の保護者の皆様からのアドバイスをいただき、すべての商品の値段を確定させ、準備万端、オープンの時を待ちました。開店直前全員が集まり、担任のN先生は、「商品を買ってもらうことは当たり前なことではない。来店したお客さんが自分のお金を差し出して買っていただくわけだから、ありがとう、感謝の気持ちをしっかりと伝えてください」と、子どもたちに大切なことを伝えました。
いよいよ開店。早速お客さんが続々と来てくださり、子どもたちが一生懸命作った商品を買ってくださいました。子どもたち、緊張しながらも、商品の説明をしたり、輪島市のみなさまに向けたメッセージを書いてくださいと呼びかけていました。お客さんの流れがひと段落すると、子どもたち「お客さんが来ない」と心配になります。担当する場所から、「カレンダーいかがですか。能登のためにお願いします」と呼びかけるのですが、なかなかお客さんに届きません。すると子どもたち、勇気をふりしぼり、店内でお買い物をしている方のところまで行き、声をかけようとします。・・・が、はずかしくて戻ってきてしまいます。それを数回繰り返して後、意を決して声をかけていました。すると、声をかけたお客さんが商品を買いに来てくださいました。この成功体験が功を奏し、自信にもつながり、私もぼくもと、商品を手に、お客さんに声をかけるこが増えていきました。
開店から2時間、すべて完売しました。子どもたちからは拍手が起こりました。今回の売上金は、昨年の参観日で集めた募金と合わせ、赤十字社を通じ輪島市へ届けられます。今回の販売活動で、5年生大きく成長したはずです。児童会も引き継ぎます。頼もしい5年生になってきました。期待します。
当日、販売活動に足を運んでくださった、保護者の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。
2月10日(火) 参観日 ~5年生~
| |
|
5時間目、参観日がありました。予定では4年生と5年生でしたが、今回は5年生のみの参観日となりました。5時間目には授業が、6時間目には体育館で親子レクが行われました。
授業では、いくつかのグループに分かれての活動でした。明日の販売活動を控えているグループでは明日に向けた最終準備を行い、近くで参観する保護者の方に、金額設定についてや販売に向けたアドバイスをもらっていました。6年生を送る会・1年生を迎える会グループでは、プレゼントの制作などが行われ、保護者の方も一緒につくってくださいました。6時間目に行われる親子レクの進行グループは体育館で司会進行のリハーサルを行っていました。そして児童会本部役員はこれから引き継ぐ児童会に向けた打ち合わせをしていました。それぞれのグループが目的をもって活動をしている様子が伝わってきました。担任のN先生は、2学期の最後と3学期の冒頭に、学級の子どもたちに向けて、「5年生の三学期は、6年生へ向けた0(ゼロ)学期であること」を伝えていました。6年生へと向かう5年生の姿、頼もしく感じました。
6時間目には、親子レクが行われました。私は前半の少しの時間のみ参観しましたが、司会進行役が中心となって、レクを進めていました。参観したタイミングの時には、手つなぎ鬼ごっこが行われ、数分間、手をつないだ鬼に、手をつなぐ2~3人組が追いかけまわされていました。鬼役の子どもも親も、逃げ回る子どもも親も、とっても楽しそうでした。親子で手をつなぐ姿もあれば、友だちのお母さん・お父さんと手をつないでる様子もあり、ほのぼのとした時が流れていました。
5年生は、いよいよ明日、道の駅にて販売活動を行います。当日の販売をシミュレーションしても、きっとハプニングが起こるかと思います。そういった”まさか”や”どうしよう”の中に、成長へとつながる何かがあるはずです。当日参加する5年生のみなさん、がんばってください。そして、明日の天気が心配ではありますが、子どもたちの商品を購入予定の方いらっしゃいましたら、ぜひ、道の駅までお出かけください。よろしくお願いいたします。
2月9日(月) 素敵な音色に包まれて ~金管バンド~
7日(土)、上田市サントミューゼ大ホールにて、長野県アンサンブル交歓会上小大会が開かれ、青木小学校から金管バンドも参加し、演奏してきました。同日、所用があり、私自身は会場へ行き、子どもたちの演奏を聞くことは叶いませんでしたが、終了後、音楽専科のK先生より、無事終わったこと、インフルエンザの心配がある中全員がステージに上がれたとの報告を受けました。K先生の声がとても弾んでいて、その声からも満足のいく演奏ができたことが伝わってきました。
そして今日、当日配られた講評用紙(2名の専門家の方からの感想)をK先生からいただき、目を通しました。そこには、
○「学園天国」に挑戦できるのは、一人一人がしっかり自分の音を吹けていけそうだということなので
自信をもって吹いてください。
○「小さな恋のうた」と~ってもやわらかいく、あたたかい響きのアンサンブルでした。一人一人が
素直で真っすぐ音が伸びていて基礎の力がついてきていることを感じました。
○「Friend Like Me」6年生として、小学校最後の有終の美を飾ることができてとてもよかったです
ね。パートごとのバランスもよくて、中低域の音もクリアに響いてさすがだと思います。
こういった講評でした。とても温かなコメントで私までうれしくなりました。今年度の金管バンドの活動も今回の交歓会で区切りとなりました。4月からは、4年生は5年生に、5年生は6年生に、そして6年生は中学1年生になります。4、5年生は青木小の伝統を引き継ぎ、6年生は新しいステージで、新しい自分に出会ってほしいと思います。
金管バンドのみなさん、本当におつかれさまでした。そして、会場まで行っていただいた保護者のみなさま、ありがとうございました。
2月6日(金) 11日の能登復興プロジェクトに向けて ~5年生~
5年生は昨年、防災合宿を学校で行い、実際に避難生活を送る疑似体験をしました。そして、防災についての学びを深めると同時に、能登半島地震の現状に目を向け学習を進めてきました。そして、子どもたちの意識が、「未だ避難生活を送っている人たちの力に、わたしたちがなれないか。わたしたちにできることはないか」と思いが膨らみ、能登復興のための義援金を集める活動が生まれました。
3学期に入り、子どもたちは急ピッチで商品を作っています。ペットボトルを利活用した小物入れ、綿でつくったボンボンキーホルダー、木製クリップをアレンジしたマグネット、そして写真に写る自分たちが図工の時間に行った”版画作品”を活用した2026年カレンダー、それぞれ分担し、能登に暮らす人たちのことを思い、心を込めて製作しています。
こういった商品を、今週11日(水)、青木村の道の駅あおきで販売することになりました。道の駅あおきの社長様のご厚意で、先日地域に配布されたチラシにも今回のことを掲載していただき、子どもたちの願いで、上田ケーブルテレビでも宣伝をさせていただきました。商品を精一杯作っていますが、数にはどうしても限りがあります。場合によっては、オープンしてすぐに売る切れてしまうかもしれません。そういったことは当日になってみないと分かりませんが、当日、子どもたち手作りのものをご購入していただける方いらっしゃいましたら、ぜひ道の駅あおきまでお出かけください。よろしくお願いいたします。
2月6日(金) 明日に向けて ~金管バンド~
本日朝、音楽室へ向かうと、金管バンドの音色が聞こえてきました。そして、音楽室へ入ると、4年生、5年生、6年生それぞれに分かれ、明日、サントミューゼで演奏する曲の最後の練習をしていました。4年生は『学園天国』、5年生は『小さな恋のうた』、そして6年生は『フレンド ライク 三―』を演奏します。音楽室の空間で3つの演奏が同時に行われ、他の曲が耳に入り、演奏しにくいのではと思ったものの、演奏する子どもたちを見ると、他の音など気にする様子もなく、それぞれで音色を合わせ演奏を続けていました。
6年生にとっては、小学校生活最後の演奏会になります。夏祭りでの演奏、音楽会での演奏、交歓音楽会での演奏、そして先月行われたありがとうコンサートと続いての、クライマックスとなります。悔いなく、そして楽しく、それぞれの音を感じながら、友を感じながら、学校の代表として堂々とステージたち、私たちの音色ここにありの意気込みで、演奏しきってほしいと思います。私は、明日、会場に足を運ぶことができません。金管バンドのみなさんごめんなさい。週明け、インタビューをする中で、当日の様子を感じたいと思います。
保護者の皆様、地域の皆様、興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひサントミューゼまで足をお運びください。がんばれ!!金管バンド!!
2月5日(木) 6年生がやってきて・・・ ~オリジナル企画~
| |
以前、6年生2人が校長室へ来て、「スキー教室がある日、この日は私たち6年生しかいなくて、そんなことめったにないことだから、何かを企画して、やりたいんですけど」という6年生からの訴え、いや望みを聞きました。すぐに「いいよ!」とは答えず、安全面に気を付けることを前提に、担任の先生と相談をして企画書のようなものを持ってくるように伝えました。
そのやりとりがあっての本日二時間目休み、コンコンというノックの音が聞こえ、タブレットPCを手にした4名が入ってきました。「企画書をまとめてきたので見てください」とのこと。早速タブレットを駆使した4名のプレゼンテーションが始まりました。それよりも前に校長室に遊びに来ていたけん玉少年も、けん玉をやりつつ聞き入っていました。
企画は、ざっくりとした説明になってしまいますが、3時間目から4時間目を使い、校舎内すべてをフィールドに○○と○○をすること、お昼はその日勤務されている先生方をランチルームに招待し、楽しい給食の時間を過ごすことでした。説明はただやることだけを示すのではなく、なぜその活動をするのか、する上でどんなメリットとデメリットがあり、デメリットに対してどう対処するのか。そういったところまでの説明がありました。プレゼンテーションの完成度に驚かされました。一緒に聞いていた4年生のKさんは、4人が校長室を去ったあと、「おれも、真似したいな」と口にしていました。
スキー教室のある日は、6年生以外が菅平のスキー場へ出かけ、思う存分冬を味わいます。6年生は、5年生以下が冬を味わっているその時に、”この仲間たち”と、”今”しかできないことを企画し、先生たちも巻き込みかけがえのない時間を過ごします。私はと言いますと、菅平へ向かい”そり隊”を見守ります。どこもかしこも、楽しいことが満載!!どちらも好天に恵まれますように!そして・・・、インフルエンザが流行しませんように・・・!!
2月3日(火) 春もだけど・・・福も来い ~青木村節分祭~
2月となりました。「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」と耳にしますが、3学期が始まったと思ったら、もう2月です。本当に時が経つのが早いです。
本日は、村役場の駐車場を特設会場に、恒例の第31回節分祭が開かれ、学校からも全校ではありませんが、低学年を中心に福をいただきに、鬼を追い払いに出かけました。この節分祭は村が主催ではなく、村内のどんぶりの会という団体の皆様が主催する節分祭です。どんぶりの会の皆様は、村内のりんご園でりんごを所有され、収穫したりんごを2007年より青木村の姉妹都市提携を結ぶ静岡県長泉町まで運び、そこでの売上金をもとに節分祭を運営しています。この日の準備では、会場から投げる福袋を3000袋用紙したそうです。袋の中には、落花生、飴玉、クリップ、お菓子などが入っていて、すべての袋に同じものが入っていないため、子どもたちは、福も詰まった福袋を1つでも多くゲットしようと、競うようにキャッチし、時に拾っていました。子どもたちの傍らには、色とりどりの鬼さんがいて、会場を盛り上げてくださいました。怖い鬼は青木村にはいないようで、子どもたちにとっても優しい鬼さんたちで、子どもたちは鬼さんとすぐに意気投合していました。
最後は、大鍋で作られた豚汁を一人一人いただきました。心もからだも温まる、優しい味の豚汁でした。参加した子どもたち全員が大満足の節分祭となりました。そして、当日参加しない、高学年のために、事前に福袋と福もちとクリアファイルを届けてくださったどんぶりの会の皆様、本当にありがとうございました。
1月30日(金) 有終の美 ~1月校長講話~
今年度最後の校長講話(1月講話)がありました。マイナスの世界の体育館なので、防寒をしっかりして体育館へ集まりました。
1月の講話であること、そして今年度最後の講話にふさわしい話は何なのか?冬休みに到達する頃から考えていました。これはどうだろうか、こっちはどうだろうかといくつか考えているとき、新聞のスポーツ欄に掲載された、白馬村出身で6度目のオリンピックに挑む、複合の渡部暁斗選手の記事に巡り会いました。記事を読み、もっというと記事の読み途中で、「これだ!」と思い、話の構想を考えました。
渡部選手は、2006年トリノオリンピック、当時17歳の若さで出場し、そこから5度の五輪を経験し、今回の五輪をもって一線を退くことを決意しました。銀メダルと銅メダルは手にしていながら、唯一手にしていない光り輝く”金”のメダル獲得をめざし、前回の北京オリンピックからの4年間、すべてを競技に捧げ、今回の大会を迎えることを子どもたちに紹介しました。
そして、渡部選手のストーリーの中に位置づけたのが”有終の美”の言葉です。意味は、「物事を最後まで立派にやり遂げ、素晴らしい成果を上げて終わりを飾ること」です。子どもたちには、この中の前半部分、「物事を最後まで立派にやり遂げようとする」ことのすばらしさ、格好良さを伝えました。続けて、
「残りの2か月、わたしが立派にやり遂げることは何ですか?クラスで立派にやり遂げることは何ですか?」と問いかけ、3月の終業式のそのときには、一人一人が決意したことを立派にやり遂げ、終業式を迎えようと呼びかけ、話を終わりにしました。
日本選手の活躍を期待しつつ、一人一人の選手のそのスポーツにかけてきたストーリーにも出合いたいと思います。子どもたちには、イタリアと日本の時差については伝えていません。そこはあしからず・・
1月28日(水) 大勢を前にして ~ダンスクラブパフォーマンス~
水曜日は、清掃の時間がないため、お昼休みのおよそ30分間、思いっきり遊び、自由に過ごせる時間です。今日は、この時間に、ダンスクラブの発表がありました。事前にこの時間に体育館のステージで発表することをお昼の放送で告知していたため、時間前から大勢の子どもたち先生方が集まりました。また、ダンスクラブの指導をしてくださった佐久市でダンススタジオを運営し、プロのダンサーでもある講師の先生(青木小中出身)も急きょかけつけていただき、サプライズでプロのダンスを披露してくださいました。Hさん、キレッキレの格好いいダンス、ありがとうございました。
ダンサーのパフォーマンスが終わり、ダンスクラブメンバーの出番となりました。音楽が流れはじめ、メンバーがステージ中央に並び、踊り始めました。息のそろった振り付けに隊形移動と、見る人たちを魅了するすばらしいダンス(表現)でした。息をそろえつつも、メンバー一人一人が際立っていました。限られた練習時間の中で、ここまで表現できるのかと感心してしまいました。メンバーのみんな、本当にすごかったよ。
最後、「見ている人もステージに上がって、一緒に踊りましょう」と司会のK先生の声に誘われ、一人また一人とステージに上がり、見様見真似でダンスを踊り始めました。その中には1年生もいました。できるできないではなく、雰囲気にのみ込まれ、自らの体が動き出し、一瞬一瞬に応じながらダンスをする姿に、本当に、心もからだも開かれた子どもたちであることが伝わってきました。
全校のまで、やりたいこと、好きなことを披露する時間、本当に素敵な時間でした。発表したダンスクラブのみなさん、そして、ステージに上がって盛り上げてくれたみんな、発表を見守ってくれたみんな、ありがとうございました。
1月27日(火) みんなを待ってるよ! ~来入児体験入学~
1,2時間目に、来年度、本校に入学予定の園児(年長さん)のみなさんをお迎えして、体験入学が行われました。進行を務めるのは、もちろん1年生です。体育館隣にあるミーティングルームという部屋に集まり、はじめの会が行われました。1年生の姿を見て、1年前を思い出しました。園の帽子をかぶっていた当時の年長さんたちが、今は立派な1年生(もうすぐ2年生になる1年生)に成長している姿に、感動しました。Aさんが立派にお迎えのあいさつをし、私もあいさつの時間をいただきました。「学校へ入学したら、勉強もあるけど、”遊びの天才”にもなってくださいね」と話し、最後に、自分自身が校長室でけん玉大好きな子どもたちと一緒にけん玉をしているので、リクエスト技を披露しました。1つ目の技「飛行機」は一発で成功し、2つ目の技をリクエストすると、「世界一周やって」の声が上がったので、「世界一周」を最後に披露しました・・・が、・・・失敗してしまいました。ガックリです!!
はじめの会の後は、それぞれ手をつないで教室へ移動し、工作『パッチンがえる』を2つの教室に分かれ行いました。牛乳パックとハサミとえんぴつが用意されていて、早速始まりました。席に座る年長さんに1年生が、一生懸命に、そして優しく声をかけていました。「はさみ持ったことある?」「大丈夫?」「切ってあげようか?」「そうそう上手!!」「そこが終わったらこっちだよ!」「絵は何を書きたい?」などなど、それぞれが、目の前にいる年長さんのおねえさん、おにいさんになっている姿でした。
私は、冒頭だけしか見れませんでしたが、完成したあかつきには、楽しくパッチンガエルで遊んだはずです。最後は、体育館へ場所を移し、鬼ごっこなどをして体験入学が終わりました。4月の入学から数えて、10か月が終わろうとしています。時間の経過が1年生ひとりひとりを育てたのではなく、入学してからの日々の中で、共に学び、共に遊び、共に悩み、共に楽しみ、その時その時の出来事(エピソード)を通して一人一人が成長してきてきました。4月から2年生になるみんなが、本当に頼もしく、格好よく見えたひとときとなりました。
1月22日(木) 耳を傾け ひとりを決める ~児童会選挙~
本日の6時間目、来年度の児童会長及び役員を決める立会演説会・投票が行われました。児童会長候補者4名、責任者4名が全校の前に立ち、会長候補者の4名は会長としてどのような学校にするのかを伝え、責任者の4名はそれぞれの会長候補者の良さと強みを投票する3年生以上に伝えました。緊張しながらも、自分の言葉精一杯に演説をする姿がありました。目指す学校を実現する具体的な活動として、全校や縦割りで遊ぶ時間を設けたり、自然と触れ合う活動を行ったり、意見箱を設置したり、悩みなどを共有できる機会を設けたりと、候補者それぞれが考える具体的な取り組みが紹介されました。どれも実現させほしいものばかりでした。
演説会が終わり、いよいよ投票です。村が選挙で活用する投票箱をお借りし、本物の投票箱に一票を投じました。即座に○をする子もいれば、机の前でしばし考えてから○をする子もいました。投票している間、候補者と責任者のもとへ行き、「お疲れ様」と声をかけました。そして、候補者には、「やり残したことはないかな?」、責任者には、「候補者の良さを伝えきれたかな?」と、それぞれに聞いてみました。すると、一人の責任者の子が、
「もし○○さんがダメだったら(会長になれなかったら)、それは自分の責任だな」
と口にしました。このつぶやきに、「推薦する候補者に、会長になってもらいたい」という強い思いを原動力に、選挙活動を真剣に行ってきたことが伝わってきました。この気持ちはすべての責任者も同じだと思います。
選挙なので、会長になれる子は1名です。会長になれなかったとき、今まで抱いたことのない感情になるかと思います。その感情を理解し、その感情と折り合いをつけることに、大きな学びと成長があるように感じます。会長となった子には、会長になれなかった仲間の思いを受けとめ、自信をもって現児童会長からの引き継ぎをしてほしいと思います。立候補した4名、責任者の4名、そして、選挙管理員会のみなさん、お疲れさまでした。
1月19日(月) 安全と安心を意識して ~交通安全~
本日、長野県交通安全教育支援センターの方がお見えになり、写真の「ストップマーク」を届けてくださいました。
昨年、本校で行った交通安全教室で、子どもたちは『交通安全目標』を一人一人たてました。その目標を教育支援センターへ応募していて、そのお礼としてストップマークが贈られました。一人一人が立てた目標が明記された用紙も返却されたので、どのような交通安全目標を立てたのか、改めて確認してみました。次のような目標が記されていました。
○横断歩道を渡るとき、右、左を見て渡りたい(低)
○信号が”青信号”でも見てからわたる(低)
○内輪差 車とのきょり 気をつけよう(高)
○焦らずまわりを見て、自分も他の人も安全に、笑顔で過ごす(高)
登下校時はもちろん、公道を歩くとき、あるいは自転車に乗るときなどに気を付ける具体が記されていました。子どもたちの目標を見ながら、1つ思うことがありました。それは、安全が保障されるには、歩く側だけでなく、自動車を運転する側の意識も関係するということです。ゆとりをもった運転、常に周囲の状況を確認しながらの運転、そして、譲り合うこと。
子どもたちの安全は、子どもと社会、双方の意識によって成り立ちます。安全運転を心掛けなければと子どもたちの目標と出合い、再確認することができました。
「ストップマーク」前回いただいたものは校庭とつながる南玄関に貼られています。今回いただいたストップマークも、校内に貼らせていただきます。
1月17日(土) 素敵な演奏会 ~ありがとうコンサート~
9時30分から、体育館を会場に、”ありがとうコンサート”が開かれました。フロアには、金管バンドの演奏を聞こうと、保護者の皆様を中心に70名ほどが来校され、大勢の方に見守られる中、素敵な演奏が響き渡りました。オープニング曲から数えて、12曲を演奏しました。
体育館入り口には、手作りのプログラム(チラシ)が用意され、スクリーンには、曲に合わせた画像が映し出されました。どちらも6年生が自主的に行ったそうです。さすが6年生です。構成も工夫されていて、3部構成となっていました。第1部はメンバー全員で演奏し、第2部では4年生、5年生、6年生と学年ごとに演奏し、第3部で再びメンバー全員となり、最後に、これまで一番練習を続けてきた『千本桜』を演奏し、コンサートが終わりました。盛大な拍手が沸き起こりました。
その後、6年生から、4月より指導をしてくださった担当のK先生に感謝の気持ちを伝える花束の贈呈があり、コンサートの終わりにK先生が挨拶をする場面がありました。「このメンバーは、本当に音楽が好きな子どもたちが集まっています。技術的には細かく見ていけば課題ももちろんありますが、一人一人が集まって音を鳴らすと、素敵な演奏になるのです。」とメンバーをたたえました。この言葉に付けたしをしてよいのであれば、「音楽な好きな子どもたちと、音楽をこよなく愛するK先生がコラボすることによって素敵な音楽が生まれてくる」と私は思いました。
あっという間の一時間でした。来月のサントミューゼで開かれるアンサンブル交歓演奏会が、今年度最後の活動となり、6年生はいよいよ引退となります。残り1ヶ月、思う存分がんばってください。金管バンドのみなさん、素敵なコンサートをありがとう。そして、休日にもかかわらず、演奏を聞きに来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。
1月16日(金) 明日に向けて ~金管バンド~
朝の時間に、金管バンドの演奏を聞きました。金管バンドは明日、学校の体育館で感謝コンサートを行います。昨年のサントミューゼでの発表を終えてから、金管バンドのメンバーは明日行われる感謝コンサートに向け、平日はもちろん、休日練習も継続的に行ってきました。その積み上げてきた練習の成果を、コンサートを控えた前日の今日、全校の前で2曲を披露してくれました。
始まる前、あいさつをしたYさんは最後、「今、とても緊張しています。それではお聞きください」と全校に伝えました。よりよい演奏を目指し、楽器とその楽器から出される音色と向き合い続けてきたからこそ緊張が湧いてきたのだと思います。
担当のK先生が指揮台に立ち、演奏が始まりました。夏のお祭りでの演奏、10月の音楽会とサントミューゼでの演奏を聞いてきましたが、その時よりも、音量がアップし、音の力強さと、強弱が付いたことで生まれる柔らかさが加わり、一段と聞き応えのある演奏に聞こえてきました。演奏を聞く全校も、金管バンドのメンバーが生み出す音色に聞き入っていました。
明日の感謝コンサートは9時30分から体育館にて行われます。保護者はもちろん、多くの方に聞いていただけたらと思います。聞きに行こうと思っている方いましたら、直接体育館へお越しください。お待ちしております。
1月9日(金) ひとりでみんなで縄跳びタイム ~体育集会~
朝の時間に体育集会が開かれました。今回は体育館に集まらず、各教室から画面を通じて参加する集会でした。3学期の体育集会は、”なわとび”が行われます。一人でいろいろな跳び方にチャレンジする集会と、クラスみんなで八の字跳びを行い、制限時間内に何回跳べるか、各クラスの目標回数に挑戦する集会の両方があります。2学期の終盤には、八の字跳びの練習を始めている学級もありました。
この日の集会では、体育主任のT先生から個人が挑戦する様々な跳び方の紹介がありました。写真は1年生の教室の様子です。画面に映る色々な跳び方に出合うと、思わず立ち上がり、画面の中で跳ぶ人のタイミングに合わせ、なわとびの縄を持っているかのように手を回し始める姿がありました。思わず跳びたくなったのだと思います。
昨年の体育集会では、前回し跳びやあや跳びなど、全校一斉(その跳び方にチャレンジする人全員)に「よ~いはじめ」で跳び始めました。そして、縄が引っかかってしまい一人また一人と床に座り、じょじょに跳び続ける人が減り始めると、自然と近くで跳び続ける友だちに、「がんばれ~~、がんばれ~~」と応援する声が聞こえてきました。きっと、今年の体育集会でも、同じように、チャレンジし続ける姿や友を応援する姿に出会えると思います。チャレンジし、応援する。そういった光り輝く子どもたちの姿に出会えるかと思うと、ただそれだけでワクワクしてきます。
マイナスの寒い寒い中でも、縄跳びに挑戦し、心と体を燃やしましょう。がんばれ、みんな!!
1月8日(木) いよいよ始まる ~三学期開始~
令和8年、2026年が幕を開け、本日より3学期が始まりました。朝、学校前の信号機に立ち、子どもたちを待っていると、「おはようございます」の前に、「あけましておめでとうございます」のあいさつをする子が多くいました。私からも、「今年もよろしくお願いします」とあいさつをしました。横断歩道を渡る子の中に、横断歩道を渡り終えると、歩き方がスキップに変わり、玄関へと向かう子がいました。その後ろ姿に、今日を待ちわびていたこと、そして友だちや先生に会えることを楽しいにしていたことが伝わってきました。
8時ころになると、写真にあるように一人また一人と校庭へ飛び出し、サッカーをしたりマラソンをしたり歩いたりするそんな姿がありました。3学期が始まるという特別感のある日であっても、子どもたちの様子を見ていると、これまでと何ら変わることのない、”いつもの学校”が始まりました。
始業式では、1年生のIさんが、漢字と百人一首とマラソンを頑張りたいこと、3年生のHさんが、漢字と整理整頓を頑張りたいことを、それぞれ発表しました。ぜひやり遂げて、”あらたなわたし”になってほしいと思います。頑張れ、Iさん、Hさん!!
私からは2つのことを話しました。1つは、村の成人式に参加し村長さんと村議会議長さんのお祝いの言葉の中にあった、「失敗をおそれずに、チャレンジしてほしい」というメッセージを伝えました。2つ目は、来月全国で公開される映画の脚本を、青木小学校の卒業生が担当したことを紹介し、その映画の原作本の一節を引用し、「この仲間と過ごせる今を大切にしとほしい」こと、「家族と過ごせるこの時を大切にしてほしい」ことを伝えました。
3学期はあっという間の三か月です。だからこそ、一日一日を大切にし、素敵な3学期を、しめくくりの3学期を、子どもたちと共に、保護者の皆様に支えられながらつくっていきたいと思っています。3学期(も)、よろしくお願いします。
12月25日(木) いよいよ冬休み
85日間の、夏から始まり冬を迎えた2学期が無事終了しました。終業式の発表では、1年生のMさんが音楽会の太鼓をがんばって、みんなに褒めてもらえた喜びと3学期がんばりたいことを全校の前で発表しました。Мさんに発表前、「がんばってね」と伝えると、「昨日の夜、すごく緊張してお家で5回練習したんだよ」と、そうっと私に教えてくれました。「Mさんの発表、ばっちりだったよ!!」
6年生は、タブレットPCを活用して、Sさん、Aさん、Nさんの3人で発表しました。修学旅行の発表で、思い出を伝えつつ、東京の魅力を発信してくれました。3学期への意気込みも、最後に三人で声を揃えて発表しました。こちらも素敵な発表でした。
子どもたちの発表後、私も時間をいただき、2学期のしめくくりと話をさせていただきました。お仕事ゼミにの感想(お礼の手紙)を紹介し、その手紙が届いた業者の皆さんが、お手紙に対しての喜びを感じ、子どもたちからのメッセージによって頑張る意気込みが増したというエピソードを紹介しました。そして、これから迎える年の瀬には、やってほしいことが2つあることを伝えました。
① 自分にとっての”この1年”、学級にとっての”この1年”、家族にとっての”この1年”を振りかえる
② ”この1年のありがとう”を伝える(家族に)
この2つのことについてお願いをしました。「みんなは、家族に、この1年のどんなありがとうを伝えますか」と聞くと、2年生のKさんは、「お母さんに、毎日おいしいごはんを作ってくれたありがとうって伝えたい」、3年生のKさんは、「イベントを企画してくれたり、ごはんを作ってくれたり、そういうことへのありがとうを伝えたい」と全体の前で思いを語ってくれました。一人一人の子どもたち、今日の夜なのか、明日なのか、それとも大晦日なのか、その子ならではの言葉で家族に感謝を伝えてくれることを期待します。
話の最後、私からも全校へ向けて、「1学期も2学期も、楽しくてたまらない、また明日もみんなに会いたくなる、そんな毎日をつくってくれてありがとう」と伝え、全校で元気に校歌を歌って、終業式を終えました。
今回が令和7年最後の校長日記となるため、この場を借りて多くの方への感謝を伝えます。保護者の皆様、一年間、学校の様々な活動にご賛同いただき、ありがとうございました。地域の皆様、お仕事ゼミ、クラブ活動をはじめ、様々な場面で子どもたちを支えていただき、ありがとうございました。そして、この校長日記を読んでくださっている皆様、本当にありがとうございました。年が明けましても、拙い文章、長々な文章続くかと思いますが、引き続きよろしくお願いします。
新しい年を迎える3学期も、皆さまよろしくお願いいたします。
12月24日(水) 楽しく、和気あいあい ~クリスマス会~
本日はクリスマスイブ。クリスマス会が行われている学級がいくつかありました。昨日は、廊下を歩いていると、1年生が飾りつけをしていて、「校長先生手伝って~~」と言われ、廊下の飾りつけのお手伝いをしました。
2年生の教室では、サンタやトナカイの格好をする子もちらほら。楽しいクリスマス会が行われていました。司会係の二人が前に立ち、「これからクリスマス会を始めます」のあいさつがスタートの合図。担任のK先生からビンゴカードが配られ、1から24までの数字を4×4の16マスに、思い思いに記入していきました。全員が書き終わると、いよいよ数字がコールされます。モニターにはその数字がランダムに登場し、「もうリーチだ」「これダブルだ」「うわあ、リーチなのに、またビンゴにならないよ~~」など、四方八方から、ワクワクとドキドキが入り混じった声、声、声が飛び交っていました。
そして、Iさんから、「ビンゴ!!」の声。ビンゴ第一号です。このビンゴを皮切りに、一人また一人とビンゴになっていきました。体も跳びはね大盛り上がりでした。右写真に写るサンタさんは、2年生がクリスマス会の後半に、届けに来てくれました。Yさん手作りのサンタさんです。Yさんありがとう!!
サンタさんの隣にあるおいしいカップケーキは、3組Aのみんなが作ったケーキです。1時間目から卵を割ったり、分量を量ったりと協力しながら仕上げたオリジナルカップケーキです。こちらは、TさんとKさんがおぼんにケーキを乗せて届けてくれました。この日の給食のデザートとして食べました。スポンジケーキも生クリームも、どちらも私好みの甘さで、おいしくいただきました。3組Aのみんな、おいしいかっぴケーキをありがとう。
今週は、子どもたちの会話からサンタさんの話が聞こえてきました。サンタさんはいるのかいないのか。私はいると思っています。ただ、サンタさん=プレゼントを届けてくれる特別な人、とは思っていません。常日頃から家族からの愛情を、無償の愛をもらっている子どもたちの中に、その子にとってのサンタさんがいるのです。だから見えないし、現れないのだと思います。今日の夜、子どもたちの心の中に、その子が思っているサンタさんが現われますように・・・
12月23日(火) 夢は・・・ ~6年生~
6年生の教室へ向かうと、廊下に、図工の作品が飾られていました。”夢”を形にした作品でした。紙粘土で未来の自分を表現する造形物でした。まだ製作中の子もいたので、全員の作品は並んでいませんでしたが、1つ1つの作品を見つめると、「その作品の中にはその子がいる」ことが伝わってきました。スポーツ選手、ダンサー、作家、レフェリーなど様々でした。作品の下部分に明記された名前を先に見てから作品を見るのではなく、作品(未来の自分)を見て、「この夢を表現したのは〇〇さんかなあ」と予想しながら見つめました。作品を見て、その後名前を確認するたびに、「やっぱりそうだよなあ」と思う自分がいました。
しばらく眺めていると、Kさんに、「あ、先生じゃん」と声をかけられ、Kさんの作品を見ながら少し会話をしました。そして最後、1つ質問をしました。エアマイクを自分の口元にあて、「夢は見るものではない」と言った後、そのエアマイクをKさんの口の近くへ向けると、「かなえるもの」と答え、私を見つめニコッとしました。
「一人一人が描いた作品そのものの”夢”を、これからも持ち続けてほしい。そして、かなえてほしい。そのために、応援し続けたいなあ」と思ったひとときとなりました。
12月19日(金) 楽しい時間は 瞬く間 ~児童会まつり~
本日、1時間目と2時間目にかけて、全校が、特に低学年が楽しみにしている『児童会まつり』が行われました。6つの委員会が、委員会活動の内容に関係ある体験コーナーを運営し、本部会は全体の運営ならびに迷子センターを設置し、縦割り班からはぐれてしまった子がいたら放送で呼びかける活動を行いました。
6つの委員会の体験コーナーを簡単に紹介します。
学校を明るくする委員会
→メッセージの1字が書かれたカードを持って教室や廊下に隠れている人を探
学校をきれいにする委員会
→バイキンが描かれたミニカードを時間内に見つける(カードの裏には+-の得点が明記されている)
健康委員会(ランチルーム)
→①ウイルスが描かれた紙パックをやっつける(射的)、②体力を回復させる働きのある食品カード探し
体育委員会(体育館)
→スポンジ棒をもった鬼(委員)から、時間内に逃げ切れるか
図書委員会(図書館)
→本のタイトルが書かれたカードを1枚引き、その本を本棚から見つけ出す
放送委員会(理科室)
→毎年恒例のお化け屋敷。暗闇となった理科室から無事脱出できるか
こういった体験コーナー(アトラクション)が用意され、全校が縦割り班になり楽しく巡ることができました。
学校をきれいにする委員会では、カード探しに挑戦するグループが廊下で待機している間に、教室内のいたるところに手作りカードを隠す準備をしていました。棚の前や棚の上、黒板に貼られた掲示物の隙間など担当一人一人が思い思いの場所に置いていく中、5年生のTさんが「見つかりやすいところにも置こうよ!その方がおもちろいじゃん」と仲間に伝える場面がありました。自分たちが隠したカードが見つかるかどうかを楽しむというよりも、カード探しをする人たちがたくさん見つけることができる楽しさを優先させようとしている姿に見えました。
それぞれの委員会が工夫を凝らし、1つでも多くのアトラクションが楽しみたくなる、素敵な児童会まつりとなりました。本部会役員のみなさん、各委員会のメンバー、準備から当日の運営まで、お疲れさまでした。
12月18日(木) 子どもたちの安全のために ~街頭指導~

本日の朝、青木村にあるスクランブル交差点に上田警察署の方3名が、街頭指導を行いました。前日の登校時、この交差点で”ひやり”とする事案があったため、安全運転を呼び掛けようと、急きょ来てくださいました。スクランブル交差点は通常の交差点の信号の動きと違うため、見切り発車をしようとすると思わぬ事故になる可能性があることを教えてくださいました。7時過ぎから8時までの概ね1時間、停車する車の運転手の方に、直接安全運転を呼び掛けてくださいました。
警察の方の素早い行動力はもちろん、地域(青木村)の子どもたちの安全のために、ご多忙な中、時間をつくっていただいたことに感謝の気持ちでいっぱいになりました。交差点を渡る子どもたちも、警察の方3名が信号機に立っている姿を見て、いつも以上に安全を意識して登校できたかと思います。
子ども達に安全な登校を学校からも呼びかけつつ、保護者の皆様にもお家で話題にしていただき、保護者の皆様も私たち学校職員も、車のハンドルを握る時には安全運転をこころがけたいと思います。寒い中、街頭に立っていただいた、駐在所長はじめ上田警察のみなさま、本当にありがとうございました。
12月15日(月) 1年生からのおくりもの
お昼休み、パソコンと向き合っていると、校長室を「トントン」とノックする音が聞こえてきました。けん玉を楽しむ子たちが校長室をノックする時には、強めのノック音が聞こえると、間髪入れず、「しつれいしま~す」と入ってくるのですが、今回の「トントン」はとても小さな音だったので、「いつもの子たちではないな」「低学年かな」と思いました。しばらくすると、そ~~っと扉が開きました。開けたのは、1年生のSさんとKさんでした。Sさんの手にはビニール袋がありました。「何だろう?」と思っていると、「スイートポテトを作ったので、もってきました」と一言。そして、スイートポテトの入った袋を私に差し出しました。「ありがとね」と伝えると、2人一緒に軽やかなに教室へ戻っていきました。
さっそく食べました。あま~くて、とってもおいしく、どうやって作ったのか知りたくなり、1年生の教室に取材に行きました。「スイートポテト、あまくてとってもおいしかったよ。どうやって作ったか教えて」と伝えると、「ほとんど先生がやったよ」と言ったので、そんな訳はないと詳しく聞くと、サツマイモをふかし、皮をむき、適当な大きさに切るところまでは先生がやり、
①芋をつぶす ②バターを入れる ③混ぜる ④アルミホイルに適量に分け入れる
ここの工程は、全部自分たちでやったことが分かりました。教室にいた多くの子が、「○○はやったよ」と教えてくれました。その伝え方に、スイートポテトづくりの時間が楽しかったことが伝わってきました。
SさんKさん、スイートポテトを届けてくれてありがとう。1年生のみなさん、ごちそうさまでした。
12月11日(木) そうさせているものは何なのか
今週は、多くの学年で、パンジーの苗をプランターに移す活動が行われました。この写真に写るパンジーは1年生の窓側に置かれたものです。朝の陽ざしを気持ちよさそうに浴びて、「お日様の太陽の光、あったかいなあ」と話しているようでした。
9日(火)のことです。廊下を歩いていると、パンジーの移植を終え、教室へと向かう3年生のHさんに会いました。ただ会話をするのではなく、お花とからめて何かできないかと考え、花の活動を終えたばかりのHさんだったので、「Hさん、お花を表現してみて!」と声をかけると、両手を大きく広げ、どことなく目線を遠くし、両手をゆらゆらと揺らし、花を表現してくれました。晴天の空の下、一輪のお花が風に揺られている様子をしたのだろうなあ」、そんなことを表現するHさんを見つめながら思いました。
そして次は、私の番です。「Hさん、先生もあるお花をジェスチャーするから当ててみて!」と伝え、次のようにジェスチャーをしました。
①両手を目の前で”パン”とたたく ②少し腰を屈め、”じ~”っとHさんの顔を見つめる
分かりましたか。そうです。パンジーです。Hさんは最初、不思議そうな表情をしていましたが、2つのジェスチャーがつながったのか、「分かった!パンジー!」と答えました。私のジェスチャーはHさんの表現には到底およびませんが、Hさんの素敵な表現に出会えたひと時となりました。
今日のことです。出品した子たち数名に、2時間目休みに賞状を渡すことになっていて、Hさんが校長室へとやってきました。ぐるっと様子を眺めると、Hさんは、「ああ~けん玉だあ!けん玉コレクションだね」と一言。校長室には色とりどりの玉のけん玉が並んでいます。その”色とりどりさ”に出会い、Hさんはこの様子を”コレクション”と表現しました。
Hさんの花の表現、そしてけん玉が並ぶ様子をコレクションと表現するHさんを目の当たりにし、子どもの表現力は、やっぱり豊かであり、素敵だなあと思わされました。もっと、も~~っと、子どもとかかわり、素敵な表現をするその瞬間に出会いたいと思ったひとときとなりました。
12月11日(木) 役場の方のおかげで・・・ ~6年生のチラシが~
本日、役場の方から連絡をいただきました。内容は、6年生が修学旅行に向けて制作した”チラシ(ポスター)”を、役場1階エントランスの窓(両面)に飾ったというものでした。連絡をいただいたメールにはその様子が分かる写真が添えられていました(上の写真がそれ)。
6年生は修学旅行に向けて、ふるさと青木の良さを東急電鉄渋谷駅のみなさんに伝えるために、チラシ、プレゼン、動画など、自分が伝えたい方法で取り組んできました。修学旅行を終え、活動を振り返り、そこで一区切りとなっていたのですが、思いのこもった活動は、終わっているようでいて、終わることはありません。役場の方が、子どもたち手作りのチラシを見て、「地域の人たちにも見てもらう機会を設けたい」そういった温かな思いが、役場での掲示につながりました。掲示してくださった役場の皆様、本当にありがとうございます。
実は、今回掲示いただいたチラシは、東急渋谷駅の皆様のご厚意で拡大印刷していただき、渋谷駅構内にも期間限定で掲示していただいています。東京へ行く機会はなかなかありませんが、もし、東京渋谷方面に出かけた際には、ぜひ探してみていください。
12月9日(火) 飾りつけも クリスマスに
事務室入り口の扉の飾りつけが模様替えしました。ご覧のとおりサンタが登場しました。事務室前の装飾は、事務のK先生と清掃担当の6年生が一緒に作っています。夏はスイカが登場し、秋は木の実が並び、そして今回の冬バージョンとなりました。清掃の時間に、掃き掃除などが終わると、パソコンの動画とにらめっこしながら、K先生と一緒に楽しそうに作っています。清掃の時間はたった15分間ですが、その短い時間の中でも、清掃の時間なので和気あいあいとした会話はできませんが、制作する上で必要な対話をしつつ、その季節ならではの飾りをつくっています。何とも言えない温かな空気が、そこには生まれています。
各教室や廊下に目を向けると、そこにも冬を感じるアイテムがあります。4組の教室にはTさんが先生たちと一緒につくったクリスマスツリーが飾られ、1年生と2年生の廊下には、手作りのクリスマスリースが飾られています。十観山のてっぺんが白くなる様子を2回ほど見ました。ということは、そろそろ青木小学校の校庭も雪景色になる予感がしてきます。もうすぐかなと思っていた”冬”はすでにやってきました。次は、いよいよ子どもたちが楽しみにしている”雪”です。雪が積もったときには、私も子どもたちの雪遊びに混ぜてもらって、子ども以上に遊びたいなあと思ってしまいます。
多くの来校者の方が、まずは声をかける事務室の入り口を彩ってくれた6年生のみなさん、いつもいつもありがとう!!
12月4日(木) どれも美味しいね ~バイキング給食~
本日の給食は、年に一回のバイキング給食の日で、6年生と村長さんをはじめ日頃お世話になっている地域の方々と一緒に給食を食べました。グループの中に地域の方が2人入り、和気あいあいと楽しい会話を弾ませながら食べる姿がありました。
メニューはと言いますと、写真には写り切らないほどのメニューが並びました。
主食:わかめおにぎり、塩むすび、チーズパン、バターロール
主菜:たこ焼き、ほうれん草のキッシュ、鶏揚げ、エビフライ、ホキのハーブパン粉揚げ
副菜:海藻サラダ、ごぼうサラダ、ミネストローネ、ミニトマト、ブロッコリー、フライドポテト
果物:みかん1/2、りんご一切れ、パイナップル一切れ
デザート:いちごゼリー 飲み物:ジョア
以上の中から、好みのものを数種類を選び(子どもたちは既に選ぶものが決まっていました)ました。もちろん私も選び(検食があるので全種類)食べましたが、本当においしいものばかりでした。
私が食べた班には、北村村長さんもいて、子どもたちは村長さんに修学旅行の思い出話を伝えたり、好きな教科や得意なことを聞かれ、一人一人大好きな教科を伝えたりしていました。楽しい時間はあっという間で、美味しい料理が載っていたお皿は、どのお皿もほぼほぼ料理がなくなっていました。美味しい料理が子どもたちのお腹の中に、たくさん飛び込んでいった証拠です。
ごちそうさまをし、ランチルームの片づけを終え、最後は本日はもちろんのこと、日頃美味しい料理を作ってくださっている調理員さんのI先生、H先生、H先生と、栄養士のW先生に感謝の気持ちを伝えました。6年生にとって最初で最後のバイキング給食デーは、最高の日となりました。
12月3日(水) 先生たちも学び合う ~4年生研究授業~
3時間目に校内研究授業が行われ、校内の先生方が4年生の授業を参観しました。今回は研究授業のため、指導者として長野県教育委員会所属の指導主事もお招きしました。
4年生は1学期の運動会でのダンス、2学期の音楽会での義民太鼓とゴジラの演奏を経験し、更にクラスのみんなと踊ったり演奏したりして、それを「全校の前で発表したい」という思いになりました。今回は、そこから生まれた活動の1時間を見させていただきました(私は出張と重なり、残念ながら授業を見ることができませんでした。I先生、4年生のみんな、ごめんなさい。)
4つのグループに分かれての活動で、縄跳び、ダンス、楽器、けん玉の4つのグループがそれぞれ活動しました。前の時間にクラス内で発表を見合い、見ての感想を書き合ったので、その感想からこれからどうしていくかを決めだしていく1時間でした。子どもたちは書かれた感想用紙とにらめっこし、「もっとどうしたらいい発表になるのか」を考えていきました。それぞれのグループが今後どうしていくについては長くなるので示しませんが、指導主事からは、友だちからもらったアドバイスをどうやって整理し分類するのか、ここを授業者の先生が示すことができれば、よりよい話し合い、活動になったことを放課後の授業研究会でご指導いただきました。指導主事からは、授業者のI先生が、子どもの思いに寄り添い、また、子どもたち一人一人の思いや願いを先生がしっかりと把握していて、共感的に言葉をかけている姿のすばらしさもお伝えいただきました。
授業研究会では、先生方お一人お一人が、I先生の授業がどうだったのかだけでなく、自分自身の授業にどう生かすのか、どうよりよくするのかを真摯に考えている姿がありました。子どもから学び、一人の先生からも学び、職員全員で、よりよい授業を目指していきたいと思います。校内の先生方に授業を公開してくださったI先生、4年生のみんな、そして青木小学校のためにお越しいただいた指導主事のI先生、ありがとうございました。
12月1日(月) よりよい授業をめざして ~職員研修~
早いもので、令和7年、2025年も残すところ1ヶ月となりました。校庭の銀杏をはじめとした木々の葉もすっかりと落ち、冬本番を感じさせる日々となりました。
1年をしめくくる12月には、6年生のバイキング給食があり、希望個別懇談があり、19日(金)には児童会主催の児童会まつりが行われ、25日(木)の終業式を終えると、子どもたちが楽しみにしている冬休みとなります。2学期をしめくくる12月も、職員一同、子どもたちとともに、大切な一日一日を過ごしていきます。
そんな12月には、私たち職員にとって、貴重な学び合いの機会があります。3日(水)に行われる研究授業です。4年生の総合的な学習の時間(中核活動)の1時間を職員全員で参観し、授業のねらいが達成されたのか、個の学びはどうだったのか、担任のI先生のかかわり、支援はどうだったのかなど、ひとごとではなく、”自分ごと”として授業を見つめ、授業後の授業研究会で意見交換をします。
本日は、児童下校の授業ミーティングで、3日に行われる授業について最後の意見交換をしました。当日行う授業の1つ前の授業を本日5時間目に行ったので、授業の様子を共有しながら、次の研究授業をどうしたらよいか、みんなで考え合いました。今年度、最初で最後の研究授業です。公開研究授業ではないため、授業を参観する先生は校内の先生方になりますが、教育事務所から指導をしてくださる先生をお招きしています。子どもの姿から学び、I先生からも学び、そして、指導してくださる先生からも多くの学びをいただきたいと思います。
4年生のみなさん、授業を公開していただきありがとうございます。いつものみんなの素敵な姿を見せてください。
11月29日(土) 歩くことでポジティブな自分に ~子育てフォーラム~
29日(土)青木村文化会館講堂にて、子育てフォーラムが開かれました。今年度は、松本市波田を拠点に、”ウォーキングが健康づくりだけでなく、その人の人生を豊かにする”ことを広めているポジ◎ラボの丸山ご夫妻にご講演いただきました。丸山ご夫妻の講演を聞こうと、職員、保護者、子どもたち、そして地域の方80名以上の方が集まりました。
講演では、歩くことが筋力をアップさせるにとどまらず、ネットやスマホからの回避につながり、よりよい歩き方ができるようになると自信にもつながり、人生を豊かにしてくれる、こういったお話をしていただくとともに、写真右にあるとおり歩き方講座も行ってくださいました。私も、丸山さんのアドバイスの通り歩き方を意識していくと、自分自身の歩き方が変わり、自信が漲る感覚を味わうことができました。歩く姿勢だけでなく、座る姿勢、立ち姿にも意識を向ける大切さもお伝えいただきました。丸山ご夫妻、青木村にお越しいただき、素敵なご講演をしてくださりありがとうございました。
講演の後半は、前半でレクチャーいただいた歩き方を意識し、文化会館周辺を歩くとともに、歩きながら”推しフォト”を撮影しました。撮影にあたり、村内カメラマンの丸田さんに撮影のポイントを教わり、みんなで外へ出かけました。雲一つない好天にも恵まれ、思い思いの写真を撮影しました。青木三山をバックに、中学生が戯れる後ろ姿をアングルに入れたり、太陽の光から生まれるグラデーションを撮ってみたりと、楽しく写真撮影することができました。最後は、それぞれが撮影した写真をスクリーンに映し、参会者全員でシェアしました。様々な視点からの写真があり、どの写真にも味があり、素敵な写真ばかりでした。
午前開催のフォーラムは、あっという間でした。今回のフォーラムを通して、歩き方にもその人があらわれ、写真にもその人がいることを改めて感じることができました。フォーラムに来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。そして、今回のフォーラムをきっかけに、これまで以上に村内を歩き、巡り、青木村を五感で味わってほしいと思います。
11月28日(金) 本にふれ、本を味わう ~読書旬間~
| |
 |
”〇〇の秋”、のフレーズには、ご存じの通り様々あります。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋等々。晩秋から初冬にかけての今、本校では読書旬間が始まっています。
今日の朝は、図書委員会主催の児童集会が行われました。本の一節を紹介し、これを聞いてほんのタイトルを当てるというものでした。私はそのフレーズを聞いても全く持って見当がつきませんでしたが、子どもたちは、「ハイハイ!!」と元気に手を挙げ、委員の子がマイクを持ち駆けまわり、正解を答えると、拍手が沸き起こりました。最後の問題は、『〇〇字のものがたり』の〇〇の数字を当てる問題でした。6年生で分かっている子たちがいましたが、会場を盛り上げるため、5年生以下の子どもたちが回答し、たくさんの数字が登場し、最後の最後に正解にたどり着きました。
また、給食も読書旬間に合わせ、絵本に登場するレシピが給食にも登場するという、”コラボ給食”が続いています。今日は、ノラネコぐんだんのカレーが登場しました。普段とは違う具が入っている特別なカレーをいただくことができました。給食室前には、コラボ給食で登場するメニューが掲載されているページが掲示されていて、子どもたちは立ち止まり、そのページを眺めています。コラボ給食は来週も続きます。いつも楽しみな給食の”楽しみ度”が倍増です。来週は、何が登場するのかな・・・
栄養士の先生、調理員の先生方、いつもいつもおいしい給食、ワクワクする献立、本当にありがとうございます。
11月25日(火) チャレンジ防災合宿 ~5年~
 |
21日(金)から22日(土)にかけて、5年生が防災合宿を行いました。”合宿”ですので、もちろん学校に宿泊しました。5年生は3つのプロジェクトチームに分かれて中核活動を行っているので、今回はその中の『合宿チーム』がプロデュースしました。当初、5年生から「学校に泊まりたい」という願いが届きました。私は、”楽しむだけ”のお泊りは認められないと伝え、そこから合宿チームの試行錯誤がスタートしました。そして数日後、「学校は避難所になっているので、実際に避難所となる所に泊まり防災について考える合宿」という提案が子どもたちからあり、実現しました。
一度下校を済ませ、17時に学校へ集合し、防災合宿が始まりました。実は今回の合宿が始まる一週間前に、宿泊に向け段ボールを集めていることを知った役場の防災担当の方から段ボールベットを製造している上田市のK社を紹介いただき、段ボール製造会社から段ボールベットを寄付していただきました。子どもたちは搬入された段ボールを組み立て、ベットが出来上がるとそこに寝転がり段ボールベットの寝心地を味わいました。普段寝ている布団(ベッド)とは違うので、寝つくまでに時間を要したようですが、寒さに耐え、無事1日目を過ごすことができました。
二日目を迎えます。眠気まなこをこすりつつ、朝の陽ざしを浴びました。朝食を済ませ、しばしレクを楽しみお昼を迎えます。二日目のお昼は焼きそばを作りました。防災合宿チームが担当し、家庭科室で野菜を切り、麺を炒め、おいしい焼きそばの完成です。美味しそうに食べていました。午後には、役場の防災士の資格のあるTさんが、子どもたちのために『防災クイズ』と題し、青木村の過去の災害の様子を写真で紹介しながら、防災についての授業を行ってくださいました。クイズを交えての授業だったので、子どもたちは楽しく学ぶことができました。素敵な授業をしてくださったTさん、ありがとうございました。
本日の出欠席の連絡欄には保護者の方からの感想が届いていました。「最初は不安そうでしたが、帰ってきたら楽しかったと合宿の様子を話してくれました」「食べ物や電気、水のありがたみ、みんなで協力することなど大切なことをたくさん学ぶ事ができたと思います」などなど、感想からも子どもたちにとって有意義な合宿であったことが伝わってきました。合宿にご協力いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。
11月21日(金) 予告なしの避難訓練
三回目の避難訓練がありました。今回は、予告なしの避難訓練で、休み時間中に緊急放送が流れました。校長室には、いつものようにけん玉を楽しむ3,4年生がやってきて、いつものように楽しんでいました。その最中に、放送が流れました。けん玉を手にしていた子どもたち、さっと床にしゃがみ、机の下に入る子もいました。放送も静かに聞き、避難の指示ができると落ち着いて校庭へと向かいました。
私も一緒に校庭へでると、校舎の複数の出入り口から学年が混ざり避難するところでした。多少の声は聞こえてきましたが、落ち着いて速やかに避難することができました。今回の避難訓練は、”理科室の火災”が原因で避難するというものでした。数日前に九州の大分県で大規模火災が起こっていたので、この火災を話題に上げ、2016年に起きた糸魚川の大火災の時にボランティアに参加した当時の教え子の話をして、火災、災害について考えるきっかけをつくりました(つくったつもりです)。
災害のニュースを見るたびに、「人間が開発する優れた技術が更新され続けても、自然(災害)には抗えない」と思い続けています。しかし、いざ災害が起きた時の自分自身にとっての被害を軽減することはできます、そのためには今回のような避難訓練が大切です。災害について、避難について考える貴重な時間となりました。
11月20日(木) すきなことを”とことん” ~クラブ最終会~
5,6時間目、今年度最後のクラブ活動が行われました。今年度は、地域の方にクラブ講師をお願いし、9クラブのうち、6クラブ(サッカー、そば打ち、手芸工作、が地域講師をお招きしてのクラブ活動となりました。合計4回のクラブ活動を通して、「このクラブだからこそ生まれるかかわり」をつくることができました。全クラブの最終回の模様をほんの少し紹介します。
〇サッカー:AとBチームに分かれ思う存分試合を行いました。コーチも職員も混ざって楽しく行いました
〇バトミントン:ラリーを少しだけして、最後のダブル戦を行いました。どのコートも大盛り上がり
〇そば打ち:育てたタチアカネの粉が混ざったそば粉で2班に分かれ蕎麦打ちをしました。大成功
〇手芸工作:前回のうさぎのぬいぐるみに続き、季節ならではの人形をつくりました。お家に飾ります
〇イラスト・ゲーム:村から依頼のあったポスター制作、模写、カードゲームなど大盛り上がり
〇ダンス:プロダンサーに最後の振り付けを教わり、通して踊りました。3学期、全校の前で発表します
〇パソコン:最終回はオリジナルカレンダー制作。誕生日に特別な印をしている子もいました
〇カラオケ:音楽室をステージに、一人一人が思い思いの曲を大熱唱。高得点めざし歌いました
〇パン:好みの形と好みのトッピングで『ロシアンパン』づくりに挑戦。おいしい香りが漂いました
来年度は、今年以上に地域講師をお招きし、クラブ活動を行おうと考えています。地域の方で子どもたちに「これを一緒に楽しもうかな」というものあれば、ぜひ、お問い合わせください。
今年かかわってくださった地域講師の皆様、素敵な時間を子どもたちにプレゼントしていただき、ありがとうございました。
11月20日(木) 走って落ち葉とたわむれて ~チャレンジマラソン~
今月は、あおきっ子チャレンジマラソン月間です。朝の時間、二時間目休みを中心に、子どもたち元気に走っています(もしくは歩いています)。全校にはマラソンカードが配付され、走った分だけ色が塗れるシステムなので、走ることが大好きだから走る子、歩きたいから歩く子だけでなく、走って歩いて、カードに色塗りがしたいからと頑張っている子たちもいます。
今日の朝は、私も走りました。いや、歩きました。校庭の銀杏の木の葉が一斉に落ち始め、雨のように落ち、「風が吹かなくとも葉はこんなにも落ちるのかあ」と不思議に思いつつ、「この、銀杏のじゅうたんを見つけたら、子どもたち、きっと”あれ”をするだろうなあ」と期待しつつ、子どもたちの登場を待ちわびました。
玄関開錠となってしばらくすると、2年生のMさんとSさんがやってきました。靴を履き替え、校庭のまわりを走りはじめます。そして・・・、そうです”あれ”が始まったのです。銀杏の葉が積みあがっていることを発見すると、その場まで加速し、たどり着くと急ブレーキをかけピタッと止まり、止まった途端体を屈め、銀杏の葉をわしづかみにし、天に向けて銀杏の葉を投げ上げました。舞い上がった途端自分の体に落下し、銀杏の葉っぱシャワーを浴びました。「そうそう、これこれ!!」と、迷わずシャッターを押しました。
一人また一人と”これ”をやる子が増え始めたので、「校長先生も混ぜて~~」と仲間入りし、”銀杏の葉っぱシャワー隊”と命名し、何人かの先生に立ち止まってもらい、シャワーをプレゼントしました。子どもたちは、「次はだれにする~~」と、周りを見回し、次々にシャワータイムを楽しみました。
走ったり、時に歩いたり、銀杏の葉で立ち止まり葉っぱシャワーを味わったりと、今日しかできない最高の遊びを子どもたちはしていました。子どもたちの反応、声、歓声、最高のひとときとなりました。
11月18日(火) お仕事へのあこがれ ~夢の種まきお仕事ゼミ~
本日、1時間目から4時間目までの時間を使って、「夢の種まき お仕事ゼミ」が開かれました。今年度、地域で働く方々を学校へお招きし、子どもたちに向けた、将来につながる授業をしていただきたいとお願いしたところ、村内の17の企業・事業者の方々に賛同いただき実現した、学校として初の試みです。
まずは、ご対面です。体育館に全校が集まり、講師の皆様に入場していただきました。「誰が授業をしてくれるんだろう」と、この段階から子どもたちは興味津々でした。
ご対面の後は、17か所の会場に分かれて、それぞれの会場で魅力あふれる授業をしていただきました。木材をとことん磨いてナイフをつくったり、瓦を並べたり、大型機械に乗車したり、旅館の魅力を知ったり、オリジナルコーラを作ったり、図書館の魅力を知ったり、顕微鏡でミクロの世界を覗いたり、未来の家を考えたり、体のメカニズムを知ったり、手打ちそばを味わったり、春巻きを巻いて味わったり、車いす体験をしたり、アルミ製品を触ったり、ヒノキを香りを味わったり、木登りチャレンジをしたり、カメラを撮ってみたり、美容師体験をしてみたりと、(○○たりが多くなってしまいすみません。)どの会場にお邪魔しても、子どもたちのからだは前のめりで、嬉々とした表情で参加していました。
最後は、もう一度体育館に集まって、終わりの会を行いました。講師の皆様の前で、楽しかったこと、すごいって思ったことなど、その子ならではの言葉で感想を伝えることができました。きっと、子どもたちは家に帰って、今日体験した思い出を、たくさん家族に話していることと思います。
子どもたちのために、お忙しい中子どもたちに授業をしてくださった講師の皆様、本当にありがとうございました。初の試みでしたが、ご賛同いただいた皆様のおかげで、すばらしい時間となりました。
11月16日(日) 産業祭AKBで子どもたちも大熱唱
15日、16日の両日、青木村ふるさと公園を主会場に、恒例の青木村産業祭が行われました。ステージ発表があり、様々な体験コーナーがあり、たくさんのお店も出店していて、天候にも恵まれ、両日ともに大盛況でした。
この産業祭二日目には、第3回あおきカラオケバトル(AKB)が開催され、なんと今年は、小学生もステージに上がりました。3年生のМさんは単独で出場し、5年生のNさんとМさんは二人でステージにあがり、カラオケクラブと有志メンバーでもステージにあがりました。今年度は11組がエントリーし、その内3組が小学生でした。主催した役場担当者の方も、小学生がステージに上がり盛り上げてくれたと大喜びでした。
カラオケクラブがステージにあがったとき、私も一緒にステージにあがり、担当のK先生と、ステージ上で歌うカラオケクラブのみんなを見守り、手拍子で声援を送りました。ステージから見つめる会場は満員御礼でした。多くの人の前で歌い切ったことは、きっと自信につながったはずです。村内のカラオケをこよなく愛する歌自慢のみなさんが集ったので、残念ながら決勝進出は果たせませんでしたが、大いに会場を盛り上げました。5年生の二人に、「来年もエントリーするの」と聞くと、「出ます!」と即答でした。次こそ、決勝進出です。
この日は、ダンス教室の発表タイムがあり、ここでも本校の子どもたちが素敵なダンスを披露していました。また、多くの保護者の方にお目にかかったりご挨拶したりと、この週末は多くのご家庭が産業祭三昧だったことが推測されます。産業祭が終わると、いよいよ冬本番です。そんな寒い朝の時間。子どもは風の子、学校では”あおきっこマラソン”が始まりました。寒さに負けず、体を動かしましょう。
11月14日(金) やりたいことをとことん ~第3回クラブ~
本日、第3回目のクラブ活動がありました。前回紹介できなかったクラブの様子になります。
【バドミントンクラブ】
クラブ員の人数に合わせ、3面ネットをはり、シングル戦とダブルス戦を行っています。ラケットが余っていたので、私も5分程度6年生と一緒にラリー(練習試合)を楽しみました。6年生のNさんとペアを組み、サーブにレシーブにスマッシュに、大人げないプレーもほんの少し?して楽しみました。5分程度でしたがほんのりと汗が出てきました。子どもたちはずっとやり続けるので、終わった頃は汗びっしょりだったと思います。
【イラストマンガボードゲームクラブ】
やりたいことが混ざったクラブなので、それぞれがやりたいこと、楽しみたいことに没頭してました。11月末〆切の村から依頼されたごみ減量と路線バスに乗ろうポスターを描く子、タブレットで描きたいイラストを見つけ模写している子、ボードとカードゲームでのバトルを楽しむ子などなど、思い思いの活動を楽しんでいました。
【パソコンクラブ】
ICT支援の先生に担当いただき、パソコンで色々なことを楽しむクラブです。この日は、プログラミングをしている子たちもいれば、作曲を楽しむ子たちもいました。ドラムに金管楽器にと楽器の絵をクリックするとその楽器の音が鳴るようになり、楽譜にどんなリズムで鳴らすかをインプットしていきました。数種類の楽器の音を入力しプレイボタンを押すと、オーケストラのような音色が流れてきました。
【パンクラブ】
今回挑戦したパンは、ロシアンパンでした。パン作りを専門にする保護者の方に講師をお引き受けいただき実現しました。ロシアンルーレットの如く、パンの中にチョコ、コーン、チーズ、あんこなどを包み、フライパンで焼きました。実際に食べる時には何が入っているのか分かりません。選んだパンからどんな中身(餡)が現われるの、わくわくしながら食べました。私もいただきました。チョコでした。次回は、生地に混ぜる食材、パンに入れる食材を自分で決めて最後のパンを焼くそうです。
写真を載せることはできませんでしたが、カラオケクラブは地域の福祉施設へお邪魔し、カラオケ交流をしてきました。一緒に歌う姿に、感動でした。とっても素敵な交流会になりました。
来週が今年度最終会のクラブ活動になります。学年の枠を超えた仲間たちと、めいいっぱい楽しんでほしいと思います。
11月13日(木) 焼き芋&焼き芋 ~1年生・2年生~
昨日は2年生、そして本日は1年生が、夏に育てたサツマイモで焼き芋を行いました。
昨日の2年生は、焚き木の準備から自分たちで行い、ほくほくの甘い焼き芋ができました。左の写真は、焼き芋はまだかまだかと待ちきれず、たき火の周りを囲み担任のK先生と楽しく会話を弾ませている様子です。焼き芋が出来上がる間、K先生からのお題があり、探検バックには、黄色、赤色など色とりどりの秋を感じされる落ち葉が集められていました。校庭の銀杏の木も黄金色に染まりつつあります。お昼前には、校長室にHさんが出来立ての焼き芋を届けてくれました。甘さたっぷりの美味しい焼き芋でした。2年生ありがとう。
本日の1年生は、来年入学する年長さんを招待し、焼き芋会を行いました。庁務員のS先生のサポートをいただき、前日には自分たちでサツマイモを新聞紙とアルミホイルでくるみ、準備万端でした。年長さんが到着すると、早速アルミホイルにくるまれたサツマイモをたき火に投入し(投げ入れの式)、出来上がるまでひろ~い校庭で”だるまさんがころんだ”を楽しみました。焼き芋が出来上がると、ペアになって焼き芋をもらい、食べ始めました。口に入れた途端「うまい!!」の声が聞こえてきました。じっと様子を見つめていた私に気づいた子が。「校長先生も食べる?はいっ!」と手渡してくれました。こちらの焼き芋も最高に美味しかったです。
校長室から見える銀杏の木も夫神岳も、秋色に染まっていますが、子どもたちの活動も秋色に染まりました。短い秋をもっともっと堪能してほしいと思います。
11月12日(水) 『なかよし読書』で仲良く読書 ~姉妹学級読み聞かせ~
朝の時間に、姉妹学級ごとの読書(読み聞かせ)がありました。15分間という短い時間でしたが、読み聞かせが行われている時間は、あったかな時間となりました。
私は、1年生の教室にお邪魔し、6年生のお兄さんとお姉さんが、ペアになって1年生に読み聞かせをする場面を見つめました。向かい合っての読み聞かせ、横に座っての読み聞かせなど、それぞれの心地よい立ち位置(座り位置)で読み聞かせを行っていました。1年生の表情を見ていると、途中で笑顔を見せたり、絵やお話で不思議なこと、気づいたことがると、思わずつぶやき、そのつぶやきを6年生が拾って、開いたページを一緒に見つめたり、疑問を一緒に考えたりする、そんな様子もありました。
1年生と6年生のような、見ている側が心地よくなる、そんな読みきかせがどの教室でも行われたと思います。絵本の世界、とっても素敵です。お子様に読み聞かせを継続して行っているご家庭も多々あるかと思いますが、これからも、我が子への読み聞かせ、よろしくお願いします。
11月8日(土) 土曜日ですが 登校日 ~土曜参観日~
| |
|
本日は土曜日ですが登校日でした。その理由は、参観日だったからです。また、なかよし旬間に合わせ、2時間目に参観授業を行い、3時間目に東信教育事務所学びの共創課の指導主事を講師にお招きし、人権講演会も行われました。
参観授業では、友だちのいいところ(授業では”ええところ”)を見つける授業があったり、読み物資料で登場人物の葛藤場面を考える授業があったり、自分にとって大切な友だち像はどんな友だちかを紹介し合ったりなど、人権にかかわる授業を行った学級も多くありました。また、今回の参観日に合わせ、親子レクを企画した学級もありました。2年生は理科室でスライムづくり、4年生は体育館でボッチャを体験しました。どちらもとても楽しそうでした。休み時間には(2時間目も開きましたが)、3組4組の販売活動が体育館入り口で行われました。キーホルダーに梅シロップに紙だるまなどなど、飛ぶように売れていきました。店員さん役の子どもたち、とってもうれしそうでした。
3時間目の人権講演会では、違いについて考え合ったり、動物の言い争い場面が取り上げられ、どうしたらモグラと鳥が言い合いを防げたのかを、4~6人ぐらいの縦割り班になって考え合ったりしました。保護者の皆様にも参加(サポート)いただき、どのグループも大変盛り上がっていました。最後、講師の先生から、「人は自分との違いに目を向け、違いを見つけようとしますが、そうではなく、お互いの共通点に目を向け、共通点を探すことを心がけましょう」とお言葉をいただきました。違いを認めることはもちろん、互いの共通点に目を向けられるよう、自分自身も心がけたいと思います。
講演会の後には、私が保護者の皆様に話す時間をいただきました。3つの根っこの育ちの具体、『村民憲章』がうたう”あたたかな家庭”とは、そして「今思うことは」と題し、読書離れとメディアとの付き合い方に触れながら、これからの親子のかかわりなど話させていただきました。多くの保護者の方が体育館に残ってくださり、大変うれしかったです。ありがとうございました。
11月7日(金) 全校走って、ジャンケンポン ~体育集会~
秋空の下、朝の時間に体育集会が開かれました。本日は、暦の上では『立冬』で、寒さも感じられましたが、子どもたちを見ると、防寒対策している子がいるかと思えば、半そで、さらには半ズボンの子もいました。子どもは風の子です。
運動は、じゃんけんをして勝ったら隣のサークル移動し、3つのサークルを回ると一周するというものでした。体育主任のT先生の「用意、スタート」の合図で一斉にジャンケンが始まりました。先生たちも混ざって行いました。クラスの子と手をつなぎながらジャンケン巡りをする子、「最初はグー」をぴょんぴょん跳びはねながら始める子、勝った途端に隣のサークルへ猛ダッシュする子、スキップしながら隣のサークルへ向かう子、姉妹学級の友だちで巡る子などなど、色々な巡り方でジャンケンを楽しんでいました。私もちょっとだけ参加しましたが、サークルの外から、全校が楽しむ様子をメモをしながら見つめていました。子どもたちは、外側にいる私にも「ジャンケンしよう!!」と言ってきたので、後半はジャンケンだけをしました。メモをとるので利き手でボールペンを持っていたので、「ボールペン握っているから、出せるの決まってるよ」と伝え、子どもはチョキを出し、負け続けました。ただし、途中途中、”チョキ”を出すこともあり、その時は、「ああああ~~~」と睨まれてしまいました。ごめんなさい。
およそ十分間、走って、ジャンケンして、勝って負けての繰り返し、ただそれだけでしたが、十分に楽しく、そして程よい運動となりました。今週から『なかよし旬間』が始まっています。休み時間など、学年の枠を超え、異学年同士でたくさん遊んでほしいと思います。校長室では、これまで通りに異学年同士でけん玉バトルを楽しんでいます。
11月5日(水) 二日目も満喫 ~6年生~
修学旅行、二日目を迎えました。二日目ということは最終日でもあります。時間通りに起床し、ホテルの朝食をいただき、体験別グループ見学が始まりました。
江戸切子体験班は、実際にグラスを手に、思い思いの模様をあしらい、削る機械を使ってグラスを削っていきました。最初は恐る恐るやっていた子どもたちも、やっていくごとに力の入れ具合が分かってきて、綺麗な模様を描くことができました。
食品サンプル班は、ろうを使って、野菜と天ぷらのサンプルづくりを体験しました。説明を聞き、本物そっくりの野菜(キャベツ、レタス)とエビの天ぷらが完成しました。私は江戸切子を引率したので、様子が分かりませんでしたが、体験したYさんに聞くと、丁寧に説明をしてくれました。
チームラボボーダレス班は、仮想空間での芸術を楽しみました。館内が迷路のようになっていて、出口を見つけようとしてもなかなか見つからない、そんな場面もあったようです。仮想空間を満喫したからこその、素敵なつぶやきが聞こえてきたことを、担任のN先生がうれしそうに教えてくださいました。
それぞれの班で行動を終え、お昼の会場である浅草のしゃぶしゃぶ屋さんに無事?合流し、おいしいお肉と野菜とデザートをいただき、最後の見学場所である国立科学博物館に到着しました。ここでも班ごとに分かれ、思い思いの展示会場を巡り、地球の誕生や生き物のことなど、興味津々見つめていました。
博物館を出た頃には、辺りがだいぶ暗くなり、夕暮れにそびえるスカイツリーを眺めながら上野駅へ到着し、無事予定通りの時間に、ふるさと青木小へ戻ってくることができました。バスを待つ保護者を見つけると、駆け足で向かい、早速”あんなこと””こんなこと”のお土産ばなしが始まっていました。
手作り感あふれる、今年ならではの修学旅行、無事終えることができました。6年生の皆さん、計画段階から本当にがんばりました。そして、遅い時間にもかかわらず、愛してやまない子どもたちをお迎えいただいた保護者の皆様ありがとうございました。8日(月)の土曜参観には、この2日間の出来事をプレゼンを駆使して、発表するそうです。お楽しみに・・・。
11月4日(火) 待ちに待った東京への旅 ~6年生~
 |
 |
 |
 |
本日から2日間、学校を支える6年生は、修学旅行へ出かけてきます。本日は、その初日でした。
朝早くに学校へ集合し、大好きな家族に見送られ、上田駅へと向かい、上田駅からは新幹線に乗車し、上野駅へと向かいました。天気がとてもよかったので、車窓からは富士山を見ることもできました。
最初の目的地は五島慶太翁が創業者の東急電鉄渋谷駅ビルでのプレゼンタイムでした。前半は東急電鉄さんの説明でしたが、その説明に続いて、みんなの”ふるさと青木”プレゼンが始まりました。動画も駆使したすばらしいプレゼンで、東急電鉄の皆様も驚かれていました。プレゼン後には、マスコットキャラクターの”のるるん”が登場し、記念写真撮影会が開かれました。
渋谷の次は、国会議事堂に向かい、お昼を食べ、参議院の議場に入りました。実際に国会が開かれる場所を見つめ、熱心に説明を聞いていました。
議事堂の次は東京タワーに向かいました。ここでは、高さとエレベーターの速さに驚いていました。お土産も買いました。予定したものを見つけ出し、なんだかとっても楽しそうでした。
お土産をゲットした次は、お楽しみの東京ドームシティアトラクションズです。たくさん歩き、体も疲れていましたが、子どもたちは、楽しみにしていた乗り物に乗れることから、疲れを吹き飛ばし、お気に入りの乗り物にたくさん乗ることができました。
そして、去年の6年生も泊まったホテルにチェックイン、1日目のすべてを終えました。今年の修学旅行は東京の移動にバスを利用することなく、電車(地下鉄)を乗り継ぎ目的地へと向かいました。「こんなに歩くのか~~」という位歩きました。子どもたち、がんばりました。1日目はこれにて終了。明日は班別体験学習から始まります。本当にたくさんあるいたので、きっと子どもたちはぐっすりです。もちろん私もです。
10月29日(水) 教育委員会のみなさんが本校を見学
1時間目と2時間目の時間に、教育長をはじめ教育委員(4名)の皆様が、学校訪問にお見えになりました。短時間ずつではありましたが、すべての学級の授業の様子を参観してくださいました。
子どもたちにとって教育長は、とっても身近な存在なので、緊張している素振りを見せる子は誰もいませんでした。いつも通りの子どもたちの姿を見ていただきました。
算数の授業での発言をする場面、理科の授業では虫眼鏡で太陽の光を集め、その光を黒色に塗られた紙にあてて、焦げていく様子を一人一人が食い入るように観察する場面、タブレットを活用し、調べたことをまとめる場面も見ていただきました。授業場面はもちろん、廊下に掲示された習字や絵の作品も見ていただき、「作品が、本当にすばらしい」「ひとつひとつ個性があっていいですね」と感想をいただきました。
参観後は、校長室で短時間懇談をさせていただきました。
○子どもたちも先生方もとても明るくて、落ち着ていること
○授業の中で、つぶやきがたくさん聞こえてきたことのよさ
○子どもたちが主体的に学びにむかっていることのすばらしさ
など、好意的な感想をたくさん伝えてくださいました。この日は、特別な授業をしている学級はありませんでした。日常の一端を見ていただき、好意的な感想をいただけたこと、とてもうれしかったです。
これからも、子どもと私たち教師が共に学び合う関係性で、学校のくらし、学級のくらしをつくっていきたいと思います。来週は土曜参観(地域参観)が行われます。ここでも、日常の子どもたちの姿を見ていただけたらと思っています。
ぜひ、ご来校いただき、子どもたちの姿をご参観ください。
10月23日(木) やりたいことをとことん ~第2回クラブ~
| |
|
| |
|
第2回目のクラブ活動が行われました。今回は、4つのクラブの様子を紹介します。
【カラオケクラブ】
前回は、音楽室でのカラオケオンステージでしたが、今回は場所を、村外(上田市内)のカラオケ設備の整ったお店にお邪魔しました。お店を営む方が青木在住の方で、カラオケクラブの子どもたちを快く受け入れてくださいました。11月に行われる産業祭あおきカラオケバトルで歌う曲をみんなで歌ったり、一人一人がお好みの曲を歌ったりと、楽しい時間を過ごすことができました。次回は、村内の福祉施設へお邪魔し、歌を通じて交流します。
【工作・手芸クラブ】
今回から、青木在住で洋服のリフォームをお仕事にされている方が地域講師になってくださり、子どもたちと初対面しました。事前に、このようなものなら子どもも作れるのではないかと、試作品を持ってきてくださり、子どもたちにも示して、軍手を活用したうさぎ人形を作ることになっていました。講師の方の説明を聞き、少しずつうさぎの形が見えてきました。綿を詰め、うさぎの耳がピンと立ち、かわいらしいお人形になりそうです。次回が完成予定です。
【ダンスクラブ】
こちらは、佐久市在住の青木小学校を卒業したプロのダンサーが講師として来てくださいました。前回、子どもたちと選曲し、振り付けを考える分担まで決めていたので、今回は、それぞれが考えた振り付けを合体させ、実際にダンス練習が始まりました。実際に大勢を前にして発表するのか、それとも動画を撮影し、動画を視聴していただく形で発表するのか、どちらになるかはまだ分かりませんが、プロのダンサーから教わる機会はそうはありません。熱心に取り組むことができました。
【サッカークラブ】
サッカークラブの講師は村内のサッカーチームのコーチの方で、今回は2名で来てくださいました。様子を見に行った時には、スローインの正しいやり方とそのスローインのボールをトラップする練習をしている場面でした。サッカーチームのコーチをされている方なので、分かりやすく教えてくださっていました。クラブ担当のI先生も、子どもたちと一緒に活動していました。終盤の試合形式の練習場面を見ることはできませんでしたが、前回は雨でサッカーができなかったので、子どもたちは、前回分も合わせて楽しんでいるようでした。
今回紹介できなかった5クラブ(イラスト、ボード・カードゲーム、パソコン、バドミントン、そば打ち)の様子は、次回と最終回との2回に分けてお伝えする予定です。
10月23日(木) どっちもうまい ~セレクト給食②~
本日の給食は第2回目のセレクト給食でした。前回同様に、青木にある工場で製造された冷凍春巻き2種類から好みの春巻きを選べるシステムです。今回は、「ピザ春巻」と「サモサ春巻」でした。私は、迷わずサモサ春巻を選び、検食をするので子どもたちよりもひと足先に食べました。検食をお盆に乗せ、校長室まで運ぶ途中、1年生とすれ違い、「給食見せて」とせがまれ見せると、「校長先生の春巻はどっち?」と聞かれ、「サモサ春巻だよ」と伝えると、「私はピザだよ」と教えてくれました。サモサ春巻の味は最高でした。
学級の給食の時間に合わせ、1年生と2年生の教室へお邪魔すると、ちょうど食べているところでした。パンに挟み美味しそうに食べていた子が何人かいたので、思わずその挟みパンを見せてもらいました。こちらもおいしそうでした。2年生の教室では、ちょうど「いただきます」をするタイミングでした。当番に合わせいただきますが終わると、前に座っていたSさんが、お箸をもつやいなさ、「さっそく、は・る・ま・き、たべよ~~」と、小気味よいリズムでつぶやき、パクっと食べる瞬間に出合いました。最高の笑顔を見せ、「おいしい~~」と一言。本当に美味しそうに食べていました。
今年度のセレクト給食は終わりとなりますが、次回の冷凍春巻きは、6年生が考案する春巻が登場する予定です。こちらも楽しみです。
調理員の先生方、いつも美味しい給食ありがとうございます。そして、冷凍春巻きも美味しいですが、調理員さんお手製の手作り春巻き、こちらも美味しくいただいています。
10月22日(水) 夢中になるひととき ~1年生~
|
|
朝の時間、1年1組の教室に向かうと、鍵盤ハーモニカが机の上に準備されている中、けん玉タイムが始まりました。赤色、黄色、青色、色とりどりのけん玉を手に、習いたてのけん玉技合戦が始まりました。私自身、けん玉が大好きで、ある程度の技ができることを1年生は知っているのか、「○○技やって~」とせがまれ、その技を披露すると、「わ~、すご~い!!」の反応。認めれる喜びを感じた瞬間でした。せっかくなので、1年生に、玉を剣に乗せなくても楽しめる、『たこ焼き一丁』と『金魚すくい』という技を教えました。とっても楽しそうにチャレンジしていて、ほんわかとした気持ちを1年生からいただきました。1年1組のみなさん、またお邪魔いしちゃいますよ!!
5時間目には、1年2組のみんなが担任のT先生と外へ出かけて葉っぱ拾い(葉っぱ集め)を楽しんでいました。どうやら色とりどりの葉っぱを集めて、”葉っぱでデザインアート”をするようです。素敵な形のもみじの葉を見つけると、群がるように集め始めました。大きい葉、逆に小さい葉、もみじの小さな実を見つける子もいました。発する言葉はというと、「赤色だよ、見て!」という子もいれば、「オレンジだよ」という子もいて、私からするとどちらも同じ色に見えていても、子どもが感じる色の世界はやっぱり違うこと、感じ方が豊かであることを改めて感じました。どんなアートが完成するのか楽しみです。参観日には飾られるのかな?お楽しみに・・・
10月18日(土) もっと多くの人たちに届かせたい ~金管バンド~

金管バンドのメンバーが、上田市サントミューゼでの上小小学校管楽器交歓演奏会に青木小学校の代表として参加しました。客席はほぼ満席で、多くの方に見守られる中、2曲を演奏してきました。
会場に到着すると、ちょうど金管バンドのメンバーがステージに向かう直前で、声をかけることができました。緊張していることを伝える子もいれば、緊張よりも楽しみが上回っている、そういった自身の気持ちを伝えた子もいました。
いよいよ、青木小金管バンドの登場です。演奏する位置を確認し、指揮を振るK先生がお辞儀をし、拍手をいただき演奏が始まりました。1曲目、音楽会同様、柔らかな音が重なり、温かな音色が館内に響きました。そして2曲目、軽快なテンポを保ち、力強い音を重ねていきました。そして演奏終盤、パートごとに立って演奏をし、最後はトランペットやトロボーンなどの楽器を上向きにし、演奏を終えました。たくさんの拍手をもらうことができました。
前半の部が終わり、ホールへ向かうと、演奏を終えたメンバーが戻ってきました。保護者の皆様とも一緒になりました。「もう、感動しました」「表彰があれば金賞間違いないね」などなど、賞賛の声がたくさん聞こえてきました。これまでの練習の積み重ねとK先生の継続的な指導の下、聞く人の心に響きわたる、素敵な演奏を披露することができました。
金管バンドの皆さん、本当にすばらしい演奏でした。次は年明け1月の”感謝コンサート”に向けた活動、練習がはじまりますね。”おわり”は”はじまり”の合図。次へと向かっていきましょう。休日、会場まで足を運んでくださった保護者の皆様、ありがとうございました。次は、保護者の皆様に向けたコンサートになります。お楽しみに・・・!
10月16日(木) わたしたちがプロデュース ~5年生~
音楽会が終わり、各学級の次なる活動、学びが動き出しています。
5年生では、学級の中核活動として、3つのプロジェクトが生まれ、それぞれのチームに分かれて活動をしています。「年長さんとの交流」「能登の人たちのために」「学校宿泊合宿」の3チームです。
この日の6時間目には、学校宿泊合宿チームの企画を教育長先生に聞いていただく場が設けられました。子どもたちの表情は、いつもよりも緊張した面持ちでした。それには理由がありました。自分たちが考え企画した宿泊合宿をやっても良いかどうかを、教育長に判断していただくからです。
リーダーを中心に、企画の説明が始まりました。学校は地域の避難所になっているので、その避難生活を自分たちで体験するために宿泊すること、食事は防災を視点に考えたこと、一定時間断水状態を設定し生活してみることなど、途中仲間が補足をしつつ、説明を終えました。
これを聞いた教育長先生からは、「みんなの企画、すごいよ。まわりの人のこともすでに考えているし、説明もとても分かりやすかった。お願いとしては、役場に防災担当の方がいるから、そういう人ともつながってください。これからもっと具体的にしていくと課題が見えてくるから、そういった課題もぜひ乗り越えてください。」とアドバイスをいただきました。そして、子どもたちから、「宿泊合宿をやってもいいですか?」と質問がとび、ほんの少し間をおいて、「ぜひ、やってください」と言葉をかけられ、子どもたちも担任のN先生も、そして私も、拍手が沸き上がりました。
会が終わり、リーダーがお礼のあいさつをしました。「今日は、聞いてくれて、認めてくれて、ありがとうございました」、喜びが詰まった、感謝も詰まった、素敵なあいさつでした。合宿本番に向けて、ギアが一段上がる、そんな時間となりました。がんばれ、合宿チーム! がんばれ、5年生!!
10月12日・13日 村民運動会、20年に一度のお祭り
 |
 |
三連休、12日(日)には村民運動会を、13日(月)には中挾地区の豊受神社で20年ぶりに行われた遷宮祭を見る機会がありました。
村民運動会には1年生から6年生、中学生から大人、そして年長さんたちが参加していました。ウルトラクイズ(なんと2問で終了)から始まり、減点玉入れ、紐繋ぎリレーなど、子どもから大人までがハンデなく競える競技が行われました。紐繋ぎリレーでは、1mから7mまでの紐が用意されていて、紐が長いかどうかは引いてみないと分からないようになっていて、紐を引き当てる本人も、見ている側も、わくわくでした。小学生も参加していて、大人顔負けの走りも披露していました。子どもたちが、しっかりと地域と繋がり暮らしている様子が伝わってきました。
13日(月)には、青木村の中挾区で20年ごとに行われる貴重なお祭りを見る機会をいただきました。保護者の方と本校の支援員の先生から情報をいただき、時間に合わせ出かけました。出店も出ていて大盛況なお祭りでした。式典の中で巫女役の子が舞台で舞う場面があり、4人の小学生が巫女の衣装を着飾り、上手に踊り切りました。終わった時には拍手喝采でした。20年に一度の機会なので、巫女の衣装を着れたことは奇跡といっても過言ではありません。参会者からは、20年前の思い出を語り合う声も聞こえてきました。
運動会でもお祭りでも感じたことは、子どもたちがしっかりと地域に位置づいていたことです。子どもは地域の宝であり、地域に暮らす大人の生きる原動力でもあるかと思います。地域と繋がり、地域になじみ、地域の大人のお友だちをたくさん作ってほしいと思います。学校活動でも、もっともっと地域と繋がっていきたいと思います。地域の皆様、よろしくお願いいたします。
10月10日(金) ここでしか生まれない音楽会
ご来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様、そして子どもたち。大勢の方々が体育館に集い、最高の音楽会が開かれました。子どもたちの歌声と演奏を聞きに来てくださった皆さま、本日はありがとうございました。
子どもたちにとってはこの日を待ちわびていました。私自身、その待ちわびていた子どもたち一人一人の姿を、ステージ下から見つめているただそれだけでも、こみ上げてくるものがありました。保護者の皆様にとってはそれ以上だったかと思います。それぞれの学年の発表についてひと言ふた言・・・
【1年生】 合奏も演奏も、忍者ポーズが登場したり、オリジナル振り付けが登場したり、1年生らしい
かわいらしく、格好いい演奏でした。
【2年生】 地球人と宇宙人が遭遇するという物語。その前には、”わたしならではの音”を紹介する場面
もありました。担任K先生と一体になって、歌い、奏で、演じる、素敵な発表でした。
【3年生】 ミッキーと一緒に、親しみのあるメロディーを奏でました。歌では、とても音域の高い挑戦
し、3年生の美しい歌声が体育館に響き渡りました。
【金管バンド】優しさ伝わる一曲、アップテンポな勢いのある華やかな一曲の合計2曲を披露しました。
夏祭りよりも進化した見事な演奏でした。18日のサントミューゼでの発表、頑張ってき
てください。
【4年生】 学年発表のトップバッター義民太鼓の演奏は、お見事でした。太鼓を叩くのではなく”打
つ”にこだわった演奏お見事でした。ゴジラの演奏も友を励ます一曲も、どちらも素敵でした
【5年生】 打楽器の軽快なリズムに乗り、手拍子も起こり、緊張感の中にも演奏する楽しさが伝わって
くる一曲でした。平和を伝える歌では5年生にとって平和を思う気持ちが伝わってきました
【6年生】 学年発表のとりを飾りました。演奏は難しい曲に挑戦し、その難解な曲を見事に演奏しまし
た。合奏は、”今”と”これから”が交錯する、そんな一曲でした。素敵な歌を下級生は、憧れの
まなざしで見つめていました。
【全校合唱】歌い初めと歌い締めの2曲を歌いました。音楽専科のK先生の指揮と学校支援のK先生の伴
奏に合わせ歌いました。自分自身も気持ちよく歌うことができました。全校の歌を多くの方
に聞いていただくことができ、幸せな時間でした。
あっという間に時が経つ、そんな感覚を味わった音楽会でもありました。始まりと終わりの心温まる拍手の中は、心から労い、ステージに上がった仲間を称える、そんな思いの拍手が詰まっていました。本当に本当に、素敵な音楽会となりました。
10月9日(木) 明日はここに・・・ ~音楽会目前~
出張を終え、学校へ戻り、教頭先生と一緒に体育館へと向かいました。ステージ上には楽器が並び、フロアには、4年生が使用する太鼓が並び、少し間を空け児童の椅子、その後ろには保護者席、そして両側には来賓席と職員席が用意され、すべてが整いました。
学校を不在にしていたため、残念ながら本日の前日練習を見ることは出来ませんでしたが、明日の音楽会に向け、準備万端となった体育館に居るだけで、本日行われた各学年の演奏、歌声が聞こえてくるようでした。
保護者席の椅子に目を向けると、1つ1つの椅子がずれることなく、きれいに横真っすぐに並んでいました。もちろん児童席もです。前日準備をしてくれたのは5年生と6年生でした。それぞれの学年で役割を分担し、フロア、ステージの掃き掃除、椅子を出し綺麗に並べる、楽器の配置を整えるなど、細かなところまでこだわり、一人一人が頑張っていたことを教頭先生が教えてくださいました。保護者席の椅子がほんの少しずれている場所を見つけると、「納得できない」とやり直す、そんな姿もあったそうです。聞けば聞くほどに、何も手伝えていない自分がいて、申し訳なく思いました。
5年生も6年生も、「自分たちの発表があるから」という理由だけで準備をしていたわけではありません。他の学年のため、足を運んでくださる保護者、地域の方のため、お客さんのために、よりきれいな場にしようと活躍したのです。明日は、この整った場で、全校が集い、多くの人の前でこだわりの合唱と演奏が発表されます。歌声に、楽器の音色に、表情に、立ち姿に、決めポーズに、心を揺り動かしてほしいと思います。
わくわくしながらこの日記を書いていた(打っていた)のに、何だか心が引き締まってきたような感覚も・・・。どうか天の神様、青木三山の神様、子どもたちがいつも通りの生き生きさで、歌声、演奏を披露できますように。
10月9日(木) これが最後の音楽会 ~6年生~
練習の様子紹介の”とり”は、もちろん6年生です。他の学年は、音楽会バージョンに設えられた状態で、体育館での練習が始まりましたが、体育館を音楽会仕様に設えたのはもちろん6年生でした。
自分たちが作り上げたステージで、6年生も毎日練習を積み重ねてきました。その積み重ねの1回の様子を私は見ただけですが、演奏する合奏を聞き、「難しい曲に挑戦しているな」と感じました。リズムを合わせ、そのリズムを保つことも難しいと感じる曲であり、その曲の流れの中には、明確に強弱をつけるところもありました。そういった”こだわり”は子どもたちももちろんあり、指導をするK先生にもあることがやりとりからも伝わってきました。曲を止め、指揮台からK先生が楽器を担当する子どもたちに改善点を伝えます。それを聞いた子どもたちは、楽譜を見つめながら即座に納得をしていく、このやりとりが私には”対話”に見えました。どうしたいかのイメージが共有されている、目指す先が子どもも先生も分かっている。そういう状態だからこそ、対話がなりたっている、そんな風に感じました。
合唱練習では、こんなことがありました。先週のことでした。朝の時間、3階の廊下で図工の作品を見つめているところに、音楽室で合唱の朝練習を終えた6年生が教室に戻ってきました。そこには担任のN先生もいました。N先生は、私の姿を見つけると、「この子たちすごいですよ。昨日練習したことが、今日の朝、それができていて、っていうかそれを超えているんですよ」とうれしそうに、そして・・・。
明日、いよいよ音楽会当日です。ホームページでの練習の様子紹介のとりを6年生が飾ったように、明日の音楽会の学年発表の”とり”を飾るのも6年生です。素敵な演奏、合唱をどうかご期待ください。
10月8日(水) 夏祭りよりも・・そして、この先も・・・ ~金管バンド~
特別時間割が始まり、金管バンドの朝練習は、音楽室からステージへと変わりました。なので、朝、体育館へ向かうと、ランチルーム前を通るあたりから、金管バンドの素敵な音色が聞こえてきます。
この写真は昨日(7日)の朝練習の様子です。指揮台に立ちタクトを振るK先生が、楽譜を見て、一人一人の演奏具合を見つめ、体を前後に左右にと動かしつつ、指先と目で、細かな合図を出していました。その合図を子どもたちは感じ、二曲を演奏していました。K先生の姿に、「私はここまでできない!」と思わされました。言葉の指示はありません。目と体で対話をしているのですから”すごい”の一言です。
私が金管バンドの発表を聞いたのは、8月の夏祭りでの演奏でした。地域の人たちを前に、夕刻の夏の風を感じながら素敵な演奏を披露しました。それから2か月が経過し、金管バンドの演奏はステップアップしていることを実感しました。具体的に表現すると、「迫力が増し、音色の重なりの美しさも増した」といった感じです。
音楽会当日は、全校保護者の前で2曲を披露します。1曲目は優しさが伝わってきます。2曲目は音の力強さを感じる曲と表現してよいのかどうか・・・。私はそう感じました。音楽の感じ方は人それぞれです。ぜひ当日、金管バンドの演奏をそれぞれの感じ方で聞いてほしいと思います。音楽会を終えると、金管バンドはサントミューゼでの発表があります。夏祭りよりも、音楽会。そして音楽会を経てのサントミューゼ、期待満載です。
昨日から、リニューアルした村内の有線放送で、音楽会のお誘いの放送が流れ始めました。児童会三役の音声によるアナウンスです。保護者の皆様、村内の皆様、ぜひこちらもお聞きください。
10月7日(火) リズムよく、そして美しく ~3年生~
3年生は、昨年の音楽会では、オペレッタ『スイミー』を発表しました。今年は、オペレッタではなく、合奏と合唱、それぞれ発表します。
私がこの日、体育館へ向かった時は、ちょうど、合奏を終え、退場練習をする場面でした。演奏を終え、床に座り、担任T先生から、「今日の演奏、やってみてどうだった」と聞かれると、「前はずれっぱなしだったけど、今日はずれちゃったんだけど・・・」と、最後まで聞き取れませんでしたが、リズム(テンポ)についての振り返りが語られました。すると、T先生が、「そうだね。前回は、ずれ始めたらそのまま行っちゃったけど、今日は、途中ずれたんだけど、リコーダーの人たちのリズムに他の楽器の人が合わせようとして、ずれたんだけど持ち直したんだよね」と語りました。前回よりも今回、そして今回もよりも次回と、演奏をするたびにより良くなっていることが、振り返りの場面からも伝わってきました。
演奏の次は合唱でした。スイミーでは、セリフを堂々と発表し、スイミーの物語を歌声に乗せて楽しく発表しました。そんなみんなが一年の時を経て、楽しい歌声から、力強くそして美しく歌い、その歌声を聞く人たちに届けようとする、そんな姿に見えました。一人一人が本当に真剣に歌い、そして、気持ちよく歌っている姿に感動しました。
演奏するたびに、歌うたびに”よりよくなっていく”3年生です。きっと当日も、前日よりもバージョンアップする演奏、歌声になっているはずです。楽しみです!!
10月6日(月) 音楽会もニンニン忍者 ~1年生~
5時間目は1年生のステージ練習でした。この日の1年生は午前中、ランチルームでも振り付けを中心に練習をしていたので、本日2回目の音楽会練習でした。
体育館へ入ると、鍵盤ハーモニカ隊を中心に、木琴、鉄琴、大太鼓、小太鼓で、忍者にまつわる曲を上手に演奏していました。ほんの少しだけ、リズムのずれがありましたが、演奏しているのは1年生ですから、上出来です。後半は、歌の練習が始まりました。音楽会ではお馴染みの曲ですが、”探検隊”を”忍者隊”に変え、歌いました。歌の途中には、”力のポーズ”、”進めポーズ”などの決めポーズと、”流れ星”や”暗闇”、”手裏剣シュシュシュッ”などの様々な振り付けも登場します。きっと、子どもたちが考案したポーズと振り付けだと思います。右の写真は、全員が片膝になり、下を向き、片手をピンと伸ばしています。いったい、どの場面でこのポーズが登場するのでしょうか。楽しみです。
運動会で忍者になりきり、この音楽会でも1年生全員が(担任の先生も含め)忍者になりきります。歌う途中、隣の子と目を合わせニコッとする、そんな可愛らしい場面もありました。音楽会当日はとても緊張しますが、そんなほんわかする一瞬を見ることもできるかもしれません。お楽しみに・・・。
10月6日(月) ミニオペレッタ ~2年生~
| |
音楽会、いよいよ今週となりました。
2時間目、体育館へ入ると、2年生が当日に向けて練習をしていました。が・・・、ステージに立つ2年生が少なく、「あれれ、どうしたんだろう?」と思っていると、担任のK先生が電子音を流し、その音を聞いて、ステージの袖から、頭に飾り物をつけた子たちが、一人また一人と登場してきました。ここから、セリフあり、歌あり、演技ありのオペレッタが始まるのですが、詳しくお伝えすることはできません。当日をお楽しみに・・・。
後半は、演じたもの同士が一緒になって演奏し、歌うのですが、何とも可愛らしく、そして堂々と歌い演奏する、素敵な発表でした。演奏場面では、途中で担当が変わる場面もあり、工夫もされていました。一通り発表を終えると、「何か、もっと体を動かしたいな!」そんな声が聞こえてきました。1回1回の発表に満足せず、”もっと〇〇したい”と、より良いものにしようと考える姿が、何ともステキでした。劇をするにあたり、装飾品も準備されていて、こちらは手作りとのこと。音楽会から広がる活動、こちらもステキです。
担任のK先生は、ステージに上がりどうやら楽器を担当しそうです。何を担当し、どんな音を奏でるのかも、こちらも楽しみにしてください。
10月6日(月) 秋の味覚

実りの秋となりました。5年生は地域ボランティアのHさんの田んぼで田植え体験をした稲の稲刈りを先日行いました。また、2年生は夏野菜の収穫を終え、続いて大根の種まきをし、11月に収穫する予定です。3・4組の畑でもそろそろサツマイモ収穫が行われます。
この写真は、その3・4組のサツマイモではなく、私が5日(日)に収穫した紅あずまと紅はるかです。合計、100本越えの大収穫でした。住宅向かいの農業をされているKさんから畑を借り、20本の苗を植え、そのサツマイモが収穫の時を迎え、”ここ掘れ””ここ掘れ”を繰り返したところ、こんなにたくさんのサツマイモが現われました。想像以上の出来栄えに、驚きです!!
大きいもの小ぶりなもの、細いもの太いもの、真っすぐなもの少し曲がっているもの、先が細~くなっているもの等々、百本百様のサツマイモに出合うことできました。サツマイモも子どもたちも一緒。同じ芋は1つとしてありませんでした。お芋を縁側に並べ、1つ1つの違い(お芋の個性)を見つめ、楽しみました。
収穫したサツマイモ、「焼いてみようかなあ?」「大学芋にもチャレンジしたいな!」「保存食の干し芋もやってみたいな」と、早速”欲”が沸いてきました。これだけ収穫できたので、いろいろとチャレンジしてみようと思います。
10月1日(水) 響かせたいものとは・・・ ~5年生~
暦も10月となり、秋の心地よい風を感じられるようになりました。青木に広がる水田も、はざ掛けされたり、きれいに刈られた田んぼなど、目に映る景色からも秋が感じられます。
学校での10月といえば、やはり音楽会です。毎時間、体育館から素敵な歌声と音色が聞こえてきます。今日は、5年生です。体育館へ入ると、『情熱大陸』の力強くもあり、心地よくもある、そんな音色を響かせていました。演奏に聞き入るN先生に、「指揮台に立たないの?」と聞くと、「いやあ、これからですかね」と一言。これまでに合唱での指揮の経験はあっても、合奏の指揮が初体験のようで、指揮台に立つことへの不安が見え隠れしていました。
私自身、この曲には、忘れもしない思い出あります。20年以上前、岡谷市の小学校での初めての6年生を担任し、この『情熱大陸』を合同音楽会で発表した時のことです。サンバホイッスルを急きょ担当し、子どもたちと一緒にステージ上がり、演奏することになったのですが、ここで事件が・・・。冒頭、サンバホイッスルも打楽器と一緒に演奏を始めるのですが、なんと、私が、数テンプ(数拍)早くホイッスルを鳴らしてしまったのです。子どもたちの視線が一斉に私に向かい、「違う!先生間違えてるよ!!」と目で訴えられ、やり直す状況を作ってしまったのです。忘れようとしても忘れられない思い出です。
N先生は、次回から指揮を振ることになっているとのこと。子どもたちと一体になり、私たちならではの『情熱大陸』を披露してほしいと思います。この後、合唱曲も聞きました。出だしの「ラ~ララ~ララ~・・」の響きを大切に歌ってました。もちろん、いい表情で歌っていました。歌の中に「平和の鐘は、君の胸に響くよ~」という歌詞があります。音楽会当日、子どもたちが歌う先に見える全校に向けて、保護者に向けて、きっと5年生は、一人一人が思い描く平和の鐘を、歌声に乗せて響かせてくれるはずです。その響きを楽しみにしてください。
9月29日(月) 合唱に、合奏に、そして・・・ ~4年生~
本日より、音楽会特別時間割が始まりました。1時間目は、早速4年生がステージに上がりました。
リコーダーに鍵盤ハーモニカに大太鼓に小太鼓に木琴など、それぞれ楽器を担当し、『ゴジラ』を演奏しました。ステージ練習が始まったばかりなのに、譜面を見ずに演奏する子も多くいて、だいぶ仕上がっていて驚かされました。リズムを合わせたり強弱を付けたりと、細かなところを今後仕上げていくと思いますが、力強い演奏でした。
演奏の次は合唱でした。担任のI先生の願いから選曲された歌を先生の指揮を見つめながら歌いました。この曲は私もよく知っている曲だったので、聞きながら口ずさみました。やっぱりいい曲です。歌詞の中に、「どんなあなたも みんな好きだから」という歌詞があります。喜びや悲しみ、いろいろな場面でいろいろな”あなた”に出会うけど、その”どのあなた”も私たちはまるごと大好きだよ!そんなメッセージが込められています。
4年生は1年前のステージで、モルモットの”ゆきちゃん”との物語を歌いきりました。その感動の歌声から進化した今のわたしたちを、当日は披露すると思います。そして、音楽会当日、幕開けを飾るのは、4年生の義民太鼓です。昨年の4年生はフロアに降り、円をつくって演奏しましたが、今年は全員がステージ前で2列に並び、全校・保護者と向き合い、力強い太鼓の音を響かせるそうです。
どんなあなたも、クラスのみんなで好きになる4年生の合奏、合唱、そして太鼓の演奏、本当に楽しみです。
9月27日(土) 見て、聞いて、感じて、思いを馳せて・・・
昨日今日と、中学校の文化祭「こまゆみ祭」が開催され、金曜日は総合学習の発表を、土曜日は義民太鼓と当郷地区で受け継がれる壁塗り踊りの発表を見ることができました。
昨年6年生だった卒業生の現在の姿を見ることができるので、参観をとても楽しみにしていました。こまゆみ祭初日、1年生は宿泊体験学習の様子を発表しました。観光牧場での乳搾り体験、そこで飼育されている牛のお肉をバーベキューで食べたことなど発表する中で、「いただきます」の意味を再確認し、「生き物の命をいただき自分たちはいきていることに感謝し、これから生活していきたい」と素敵な発表をしました。そして、登山の様子、宿泊の様子など、貴重な二日間を過ごした事が発表から伝わってきました。
金曜日には、学年および全校合唱の発表もあり、6年生が中学校へのイメージを膨らめることも含め、参観することができました。どの学年の合唱もすばらしく、感想には、「全校の歌はとても迫力がありました。目をつぶって聞いてみると、だんだん近づいてきていたみたいですごかった。他にもハモリがとてもきれいで感動しました」と記されていました。中学生へのあこがれも芽生えたようです。
土曜日の義民太鼓は感動でした。演奏(演技)直後は拍手喝采でした。壁塗り踊りでは、当郷地区の(参加希望した)小学生も中学生に混ざって笛を演奏しました。職人が壁を塗る動きを踊りにしていて、大変見ごたえがありました。
今回生で参観した歌声、演技など、そこで感じたことが10月10日に行われる音楽会に繋がりそうです。中学校のみなさん、参観させていただき、ありがとうございました。
9月26日(金) 音楽会に向けて ~音楽集会、楽器搬入~
朝の時間に音楽集会がありました。私は、中学校の文化祭(こまゆみ祭)に出かけたため、全校が集った様子を見ることはできませんでした。文化祭の参観を終え学校へ戻り、音楽会の様子を教頭先生に聞きました。音楽会当日がイメージできるよう、音楽専科のK先生が、当日はここに太鼓が最初並んでいることやどういう隊形で並び、一番最初の全校合唱の♪エール♪をどのように歌ったらよいかなど確認し、本番さながらに、一発勝負で全校で歌い、歌声を響かせました。また、ステージ上とステージ前方にある楽器は、前日、6年生が全校のために運んでくれたこともK 先生から全校に紹介していただきました。
前日の楽器運びの時間、6年生が汗を流しながら運ぶ姿がありました。私も手伝おうと思っていたのですが、手伝いに向かう時間が遅くなってしまい、体育館へ向かった時には、すでにすべての楽器を運び終えていました。6年生のみなさん、何もお手伝いできずごめんなさい。
楽器がならび、体育館内が一気に音楽会ムードになりました。来週からは、学年ごと体育館での練習が始まります。精一杯に歌い、精一杯に私の音を響かせる姿を、たくさん見たいと思います。まずは全校合唱♪エール♪、自分自身も一緒に歌えるよう、練習したいと思います。
9月25日(木) 安全を子どもたちも一緒に呼びかけ ~秋の交通安全~
秋の交通安全街頭指導に自転車クラブ員11名も参加しました。これまで、上田警察署、青木駐在所、上田交通安全協会青木支部、青木村役場をはじめ交通安全にかかわる村民の方々などが集まり、学校前の横断歩道付近で街頭指導をしていましたが、今回は、主催者側から自転車クラブの子どもたちにも街頭に立ってほしいという依頼があり、参加する運びとなりました。
7時10分に集合し、はじめの会を行いました。上田警察署交通安全かの課長さんからは、上田小県地域でも命を落としかねない交通事故が増えていること、自転車クラブのメンバーの力も借りて、青木から交通安全の輪を広げてほしいとお話をいただきました。
その後、早速街頭に立ち、チラシとティッシュ配りが始まりました。子どもたちは、「交通安全へのご協力、よろしくお願いします」と運転手の方々に伝え、手渡しをしていました。物おじせず手渡しする姿に、参加された多くの方が感心していました。20分ほどの時間でしたが、子どもたちは一生懸命活動することができました。
子どもたちへの安全指導を徹底したとしても、ハンドルを握る方々がルールを遵守し車を運転しない限り交通事故は無くなりません。子どももそして大人も、双方が交通安全への意識を高め、”村民誰もが安心して過ごせる村”の継続を、まずは子どもたちが実践していきたいと思います。
貴重な機会に参加させていただき、ありがとうございました。
9月18日(木) 好きなことをとことん ~第1回クラブ~
前回のクラブ発足会(顔合わせ会)に続き、本日、第1回目のクラブ活動が行われました。今年度、地域講師を保護者にも呼びかけ、二人の方が手を上げてくださり実現したクラブがあります。今回はこの2つのクラブを紹介します。
1 パンクラブ
パン作りをお仕事にされているYさんを講師にお招きし、活動しています。今回は、生地をこねる体験を軸に、クッキーづくりに挑戦しました。私は前半にお邪魔したので、焼く段階の手前、生地をこねて丸める活動をしているところを見ることができました。生地の硬さ(やわらかさ)を実感しながら、上手に丸めていました。不安な様子が見られると、講師のYさんがすぐに子どものもとへ行き、アドバイスしていました。写真は、完成したクッキーです。好みの型で型抜きをし、美味しそうな焼き加減で、食べてみたくなりました。きっと子どもたちは、「おいしい!おいしい!」つぶやきながら食べ、次回のパン作りを心待ちにしていると思います。パン作りをきっかけに、家族と一緒に、いろいろな料理にも挑戦してほしいと思います。
2 カラオケクラブ
こちらのクラブは、「私に何ができるだろう、カラオケクラブだったらできるかも」とSさんが考えてくださり、実現したクラブです。発足会の時に、一人一人歌い曲を決めたので、今回は、音楽室を会場に、一人一人が歌っていきました。学校担当が音楽専科のK先生なので、盛り上げアイテムのタンバリンなども用意してくださったので、そのアイテムも使いながらの盛り上がりでした。私が音楽室へ入ると、ちょうど5年生のOさんが歌う番でした。マイクをギュッと握り、イントロが流れ歌い始めました。ほぼ完ぺきに歌いあげました。「友だちが聞いていても、こんなに堂々と歌えるんだ!」と感心しました。次回は、学校を飛び出し、カラオケ機器のある場所へ出かけ歌います。ラポートあおきを利用されている方の前でも歌う予定です。歌を通して、多くの方と繋がってほしいと思います。
次回は10月23日(木)です。お伝えできていないクラブ活動の様子を掲載する予定です。
9月16日(火) 歩くのも、自転車も、安全に ~秋の交通安全教室~
2時間目、秋の交通安全教室が行われました。春の安全教室には上田交通安全協会青木支部の皆様を中心に、自転車の安全な乗り方、運転の仕方について教わりましたが、今回は、長野県交通安全教育支援センターから、交通安全教育指導員の方4名を講師に招き、教室を開いていただきました。
実際に自動車が動く様子を見ながら、実演をしながらの説明を聞きながら、運転者の死角について、自動車の前輪と後輪の内輪差について、そして、交差点では「止まる」「見る」「待つ」の3つを常に心がけること、こういったことを教わりました。この日の5年生の日記には、今回の交通安全教室のこと、内輪差についてはじめて知ったことなどを書いてきた子がいたそうです。
安全教室で学んだことを実践するのは、子どもたち一人一人です。登下校時、休日などでの自転車の運転時など、交通安全に心がけ、誰一人交通事故に遭わないよう心掛けていきましょう。ハンドルを握る自分自身、時々サイクリングに出かける自分自身も、常に安全を心がけたいと思います。安全について大切なことを伝えてくださった指導員のみなさま、ありがとうございました。
9月16日(火) 地域の、義民太鼓の一員として ~花と実まつり~

9月の半ばを迎え、夏の日差しもようやくやわらぎ、朝夕には、秋を感じさせる風が吹き始めました。青木の景色も秋色になり、稲穂揺れる水田は黄金色に輝き、タチアカネそばの花が満開なそば畑では、白一色にほんのりピンク色輝き、見る人たちを喜ばせてくれます。
三連休の初日の13日(土)、道の駅向かいの交流広場で、青木村主催のタチアカネそばの花・実まつりが催されました。そのオープニングとして県内県外で活躍する義民太鼓保存会の皆様による太鼓の演奏がありました。この保存会には小学生も所属していて、この日は、5年生のYさんが小学生唯一のメンバーとして大人の演奏に混ざり、太鼓を披露しました。本校では、毎年4年生が義民太鼓の演奏を全校の前で発表する機会(音楽会)を設けていて、Yさんも昨年、音楽会で太鼓の演奏を披露しました。義民太鼓保存会の練習に参加しているYさんなので、昨年度もとても上手に太鼓を打っていましたが、今回の演奏を見て、ものすごく進化している姿に驚かされました。
演奏後、Yさんのもとへ向かい、ものすごく上手になっていてびっくりしたことを伝えると、隣にいた保存会の方がが、「Yちゃんすごく頑張っていて、今年になって急成長しているんだよ」と教えてくださいました。それを聞いていたYさんは、恥ずかしながらも何だかうれしそうでした。
私が子どもたちと過ごすのは、学校に登校し下校するまでの時間です。子どもたちは、当たり前なことですが、平日も休日も、学校ではない時間と場所でも、生き生きと過ごします。その一場面との出会いを、13日の午前、交流広場にて、Yさんからいただくことができました。
地域の皆様に愛され、励まされ、地域の一員と過ごす子どもたちの素敵な姿に、もっともっと出会いたいと思ったひと時となりました。
9月11日(木) 夢の種まきを青木小でも ~視察研修~
本日、11月18日(火)に予定されている『夢の種まき お仕事ゼミ』実現に向けた視察研修に出かけてきました。職員が視察に出かけるので、本日は学校は休みでした。
視察先は、佐久市立佐久平浅間小学校でした。岩村田小学校から分離して10年目を迎える、新しい学校です。佐久平浅間小学校では、以前から地域の企業・事業者の方を学校へお招きし、将来の仕事に触れる機会を設ける独自の行事が行わてきました。今年、本校でもこの”お仕事ゼミ”を行うこととなり、先進的に行っている学校の様子を職員で視察することになりました。また、全員ではありませんが、お仕事ゼミでお世話になる企業・事業者の方数名、運営面でお世話になる役場、青木村商工会の担当の方も同行していただくことができました。
本校は17の企業・事業者の方のお力を借りますが、佐久平浅間小学校は35の企業・事業者の方が来校されました。警察署、新聞社、テレビ局、鍼灸、作家、薬局、ダンス、飲食店などなど、多岐にわたる皆様が授業を行いました。およそ2時間半、それぞれの会場を参観しましたが、あっという間でした。
写真は、警察署の指紋採集体験とお掃除専門の方から窓の拭き方を専門の器具を使いながら教わっている場面です。指紋採集では、茶色の瓶に付着している箇所に専用の微粒の粉を付着させ、その指紋をテープに張り付ける作業に没頭する子どもたちの姿に出会いました。見ていた子は、その作業を終えると、「自分の指紋も取ってみたいな」と、警察の方にお願いに向かっていきました。”もっと○○したい”という欲求が沸いてきたのだと思います。
窓ふきでは、窓をこする反対側(廊下側)で、窓をこする(水分を拭きとる)様子を、じっと見つめている子がいました。学校で行う窓ふきと明らかに違う”凄さ”に驚いている、あるいは、「どうしてこんなにきれいにできるのだろう」と考えている姿に見えました。
美容師の方が、子どもたちに、「人の人生には、こういう風に(黒板に横線を書きはじめ、途中で線の方向を下にしてV時を書く)沈むときが必ずあります。この溝は困っている、自分ではどうにもできない溝なんです。この困っている溝を埋めるのが仕事だと私は考えています。私の仕事で言えば、例えば髪の毛が伸びすぎて困ってしまったから切ってあげる。これが溝を埋めることになります。」仕事の意味、働くことの価値を分かりやすく子どもたちに伝えてくださっていました。
様々な方がプロデュースする授業を、たくさん見ることができ、先生方も同行された企業・事業者の方もイメージをさらに膨らめることができました。佐久平浅間小学校のお仕事ゼミをモデルにしつつ、青木小ならではの、夢がふくらむ素敵なお仕事ゼミにしたいと思います。
視察を受け入れてくださった佐久平浅間小学校の皆様、ありがとうございました。11月18日の当日に向け、本校もがんばります!!
9月5日(金) 格好よくうたおう! ~音楽集会~
10月10日(金)に行われる音楽会に向けた音楽集会が始まりました。今回は、音楽専科のK先生から「格好よく歌おうね」と全校に向けて声がかけられ、″姿勢”、”口を動かす”の2つのポイントを意識して全校合唱『エール』を歌いました。歌う前、K先生から、「さあ歌いましょう」の声が聞こえると、2年生のSさんが”いのいちばん”に、飛び上がるように立ち上がりました。もう歌いたくて仕方がない、歌いたくてたまらない、そんな姿に見えました。素敵な伴奏が流れ、K先生の指揮に合わせ全校で歌い始めると、Hさんは本当に気持ちよさそうに歌っていました。全校で歌い終えると、K先生が、「いい声、いい姿だったよ」と全校に投げかけると、Sさんをはじめ、子どもたちうれしそうでした。
『つばさをください』も全校で歌いました。1学期、音楽鑑賞教室に合わせて全校で歌ったことのある曲なので、歌詞が表示されていても、歌詞を見ずに歌っている子もいました。子どもだけでなく、「エール」同様に、子どもたちを見守る先生たちも、子どもたちに負けないくらいに歌っていました。もちろん私もです。
音楽会まであと1ヶ月。いろいろな子に「○年生は何を歌うの?」と聞くと、すぐに教えてくれます。もう、当日が待ち遠しいです。次回の音楽集会は、「曲の出だしを意識して歌う」ことが課題です。学級でもたくさん歌って、次回はもっと曲の出だしから、全校の歌声がより一層響き渡ることを期待します。歌うことって、本当に気持ちがいいです。
9月4日(木) どんなことをするのかな ~クラブ発足会~
今年度のクラブ活動が始まりました。そばクラブがすでに動き出したことはすでにお伝えしましたが、すべてのクラブの発足会が本日6時間目に行われました。私は当日出張があったため、発足会の様子を参観することができず残念でしたが、それぞれのクラブで1年間の活動計画がたたったと思います。今年度のクラブを紹介します。(写真は、タチアカネそばの花の観察に出かけたそばクラブの様子)
○サッカー:外部講師(青木スピリッツコーチ)に指導をいただきながら試合を楽しみます。
○そば:青木特産タチアカネのそば粉を使って蕎麦打ちをします。蕎麦職人が講師です。
○カラオケ:郊外へ飛び出し、本格カラオケを体験。ラポートあおきさんとも交流。講師は保護者。
○ダンス:ヒップホップダンスに磨きをかけます。踊らされるのではなく、踊ります。
○パソコン:名刺、音楽会招待カード、プログラミング、作曲、様々な体験をします。
○パン:本格的なパン作りに挑戦します。家庭科室にはおいしい香りが漂うはず。講師は保護者。
○工作園芸:ハンドメイドに挑戦します。普段の生活で使えるものを作ってみたいな。
○バドミントン:広い体育館を使って、何回続くかラリーを楽しみ、ゲームも楽しみます。
○マンガイラストボードゲーム:キャラクターも模写したり、ボードゲームで真剣勝負も楽しみます。
翌日の下校の時間、階段を下りてきた5年生のSさんに声をかけました。「Sさん何クラブに入ったの?」「カラオケクラブだよ」「そっか、カラオケかあ。歌う曲は決めたかな?」「決まったよ。一曲はカーテンコールで、もう1つは・・・」と明るく元気に、そして即座に答えてくれました。明るさ、元気さ、そして素早い返答に、みんなの前で歌うこと、みんなと一緒に歌うことを楽しみにしていることが伝わってきました。次回が本格スタートの1回目です。次回の様子は私も見ることができそうです。すべてのクラブをちょっとずつ、見たいと思います。
子どもたちのために講師の役をおつとめいただく、保護者の方々、地域講師の方々、よろしくお願いします。
9月3日(水) 忍者の修行はつづきます ~1年生~
1年生の予定黒板に『2じかんめ たいいく にんじゃしゅぎょう』と書かれていたので、体育館へ向かいました。授業はすでに始まっていて、1組2組みんなで、マットと平均台を、「よいしょ!よいしょ!」と運んでいるところでした。マットと平均台を並び終えると、いよいよ修行開始です。
担任の先生から、あざらし歩き、腕の力でうつ伏せ前進、横向きに寝てからのクルクル回転、ペアになっての手押し車などなど、矢継ぎ早に伝えられる指令(技)を難なくこなしていました。
そして、いよいよ初お披露目の平均台の修行タイム。10センチの幅を最後まで歩き切れるのか、そのチャレンジが始まりました。先生からは、バランスを取るためには、腕を大きく広げることがコツであることが伝えられ、トップバッターが歩き出しました。すると、後ろに並ぶTさんが、平均台をそろりそろりと歩く友だちに向けて声をかけます。「下にサメが泳いでいると思えば、ぜったい落ちないよ!!」とアドバイス。バランスを保つための技術的なアドバイスではなく、下にいるはずのないサメをイメージしたら「落ちたくない」と心がはたらくという心理的なアドバイスでした。「子どもって、本当におもしろい」と思った瞬間でした。
全員が初平均台歩きを終えると、先生から次なる課題が与えられました。「途中でジャンプできたるかな?できたらすごいよ!」とひと言。平均台に上がり歩き出す子どもたちは、一人また一人と途中で立ち止まり、ピョンとジャンプをし始めました。あの細いところからのジャンプは、子どもたちにとっては大冒険です。一度できるともう子どもは止まりません。もっとジャンプしてみたり、途中で体を一周させる子も登場しました。「やってみたい」「もっとこうしてみたい」の連続でした。
1年生の姿に、元気をもらったひとときとなりました。みんな!!すごかったぞ!!!
9月1日(月) 安全に、そして速やかに ~第2回避難訓練~
9月が始まりました。9月になってもなお、暑い日が続きそうです。
本日は、防災の日に合わせ、第2回目の避難訓練が行われました。緊急地震速報を伝えるアナウンスが校舎に響き、一気に緊張感が高まりました。「地震により、給食室より火災が発生しました。校庭に避難しなさい」のアナウンスを終えると、学年ごと、安全に且つ速やかに避難が始まりました。私語なく整列することができていました。
避難後には、青木村消防団の方々が、消火器の使い方について教えてくださいました。実演しながらの説明だったので、とても分かりやすかったです。児童代表の6年生のRさん、職員代表5年生担任のN先生が、全校の前で実際に火(今回は赤色のペットボトル)をめがけて噴射をしました。消火器を持つ前には火事が発生したことを周りに伝える「火事です!火事です!」の声も、大きな声で伝えていて素晴らしかったです。
消防団長さんから講評をいただき、私からは、防災の日は、災害について考える日でもあるけど、命について考える日でもあることを伝えました。
○ゲームの世界では、リセットすればやり直しができ、生き返ることもできるけど、人間の命は、リセッ
トできない大切な命であること。
○その大切な命も、災害時にはあっという間に命が奪われてしまうこともあること。
○災害は、いつ、どこで、だれに起こるのか分からないこと。
○だからこそ、安全に気を配り、命を大切にしてほしいこと。
○そして、大人になった時、地域の消防活動に参加してほしいこと。
こういったことを伝えました。
ご家庭でも、災害が起きたらどう行動をとったらよいか、我が家の避難場所はどこなのかなど、話していただけたらと思います。そして、我が子の命の大切さを、温かな言葉で伝えてほしいと思います。
8月29日(金) すべてが手作り児童集会 ~学校を明るくする委員会~
2学期一回目の児童集会が行われました。今回の主催委員会は、学校を明るくする委員会でした。
今回はステージの緞帳が閉まっていて、集まってきた子どもたちは、「これから何が始まるのか」と興味津々でした。
全校が集まり、緞帳が開くと、演劇が始まりました。学校を明るくするためには、『なかよくする』ことが大切なのか、それとも『あいさつをする』ことが大切なのか、なかよく派とあいさつ派との言い争いが、全校を前にして始まりました。言い合いが続くので、困り果てた委員長Fさんが、全校に、「みなさんはどう考えますか。何かアドバイスをください」と突然投げかけました。
しばらくすると3年生のHさんが手をあげ、「あいさつもなかよくも、どっちも大事だと思います」と発言しました。続けて6年生のHさんが、「明るいあいさつをするといいと思うよ」と発表し、さらに4年生のYさんが、「楽しく過ごすことだと思う」と続けました。突然の投げかけにしなやかに答える二人の姿が、頼もしく見えました。その後、しばらく手が上がる気配がないと判断したのか、委員長が「校長先生はどうですか」と言いつつ、マイクが向けられました。事前に何もなかったので、さすがにどう答えたらよいかとフリーズし、心を落ち着かせてから、「やっぱり笑顔が大切かな」と、確かこのように答えました。
最後に、委員みんなから、なかよくすることもあいさつをすることもどちらも大切であること。そして、みんなで明るい青木小学校をつくりましょうとメッセージが送られ、児童集会が終わりました。
これまではクイズを出すことが多かった児童集会ですが、今回は、劇を通してメッセージを届けるスタイルでした。今回の台詞とスクリーンに映し出された映像は、すべて子どもたちがつくったと聞きました。本当に頼もしいです。
子どもももちろん、先生たちも、素敵な挨拶をかわし、素敵な笑顔を見せ、けんかをしたら仲直りできる、そんな仲良しの世界を作っていきたいと思います。
学校を明るくする委員会のみなさん、素敵な発表ありがとう!!
8月28日(木) 太鼓を感じる 義民を感じる ~4年生~
1学期に行われた運動会同様に、2学期も全校にとって大切な、保護者の皆様にとっても待ち遠しい行事があります。音楽会です。2学期が始まり、それぞれの学年の合唱曲と合奏曲も決まってきました。音楽会の幕開けを飾る全校合唱の曲も決まり、それぞれの学年ごと、音楽会に向けて動き出しました。
そんな中、本日、4年生も動き出しました。4年生が発表する演奏は、ご覧の通り”義民太鼓”です。昨年の4年生も演奏しましたが、力強いすばらしい発表でした。現4年生は、昨年の発表を見ているので、「次は私たちの出番」と、太鼓のばちを持つ日を心待ちにしていたはずです。ようやくその日を迎えました。
義民太鼓保存会の方が今年も指導をしてくださいます。早速太鼓を前にし、練習が始まりました。子どもたち一人一人のまなざしは、真剣そのものです。ばちの持ち方、姿勢、立ち位置、しゃがみ方、立ち方などなど吸収するものばかり。保存会の宮入さんの発する一言一言を子どもたちは聞き逃さぬよう、一生懸命に聞いている姿がありました。
私が様子を見始めてしばらくすると、水分補給タイムになりました。目の前にいたМEさん。太鼓のばちを置くなり、びっくりした表情で、自分の両手の手のひらを握ったり広げたりしながら見つめる瞬間がありました。おそらく、ずっと握っていたので、ばちを置いた途端、両手が今まで味わったことのない不思議な感覚(しびれたような感じ)になったのだと思います。夢中になってばちを握り、太鼓を打っていた証拠です。
10月の音楽会当日まで、4年生は週に2回のペースで、太鼓が保管されている村の武道館まで行って練習を続けます。昨年は昨年の4年生の音があり、今年の4年生は、同じ演目を発表したとしても、今年の4年生ならではの、発表、演奏、そして音があるはずです。
4年生のみなさん、聞く人たちの心の内側に響く音を鳴らし、太鼓を打つ姿で聞く人たちの感情を揺り動かす、そんな”打ち姿”を見せてくださいね。期待しています。
8月26日(火) 唯一無二の17つの集団誕生 ~お仕事ゼミ~
今年度の本校の大きなチャレンジの1つが”夢の種まき お仕事ゼミ”です。
このお仕事ゼミは、昨年度末から動き出しました。子どもたちに働くことの素晴らしさ、青木を拠点に働く方々のすごさ、そういったことが伝わる機会がつくれないかと立ち上がったのがお仕事ゼミプロジェクトです。地元の商工会、青木村役場のお力も借り、もちろん保護者の皆様にも呼びかけ、今回のプロジェクトに賛同いただいたのが17の事業所の皆さまでした。
その事業者の皆様との顔合わせ兼打ち合わせ会が、本日夕刻行われました。もちろん保護者の方は既にお会いしている方々ばかりですが、今回の顔合わせ会で初めてお会いする方もいらっしゃいました。会の冒頭、自己紹介を兼ねて、お仕事ゼミ当日(11月18日)、子どもたちに向けてどんなことをするのか(授業を行うのか)、お一人ずつお話いただきました。お一人一分を目安にしたわけですが、思いのある皆様なので、お一人ずつ数分ずつお話しいただきました。すべての方のお話が大変魅力的で、あっという間に時間に過ぎていきました。
「お箸一善から大きな家具、リフォームまですべてを一人でやってます。木を通じて、わたしを表してほしいと思ってます」
「鋳造の場面を実際に見せることはできないので、普段使っている道具を実際に子どもたちに触れてもらおうと考えています」
「具合が悪くなったら病院というだけでなく、自分自身の健康をセルフチェックし、自分自身でメンテナンスできること、そういったところを伝えられたとか考えています」
「旅館は、人が生まれてからこの世を去るまでの、その人たちの人生の中にかかわり、人生の一部をもてなします。そういった仕事について伝えるだけでなく、青木村のすばらしさも子どもたちにつたえたい」
などなど、本当に魅力的なお話ばかりでした。
今後、その時々に打ち合わせを行いつつ、準備を進めていきます。子どもたちに挑戦することの大切さを伝える私たち職員も、子どもたち同様に、失敗を恐れずにチャレンジしたいと思います。
11月当日、こうご期待!!
8月25日(月) ひと足早く ~蕎麦打ちクラブ~
| |
|
本日放課後、蕎麦打ちクラブのメンバー5名が、学校近くのタチアカネ蕎麦を育てている畑で、蕎麦の種まきを行いました。
2学期は、クラブ活動が始まります。活動する学年は4年生から6年生です。今年度は、”より”地域の方を外部講師としてお招きし、クラブ活動を行いたいという願いがありました。そういった願いを実現するため、3つのクラブが新たに新設されました。その1つが蕎麦打ちクラブです。
青木村はタチアカネ蕎麦で有名です。そのタチアカネ蕎麦をさらに広めたいという思いが地域にあり、畑の提供してくださる方、種を準備してくださる方、タチアカネ蕎麦の育て方を指導してくださる方、そして蕎麦打ちを指導してくださる方と、役場の方に相談したところ、瞬く間に支援してくださる方を紹介してくださいました。
当初、活動としては、蕎麦打ちのみを考えていましたが、支援してくださる方から、「せっかくクラブを立ち上げたのだから、蕎麦打ちだけでなく、蕎麦を育てるところも携わった方が、子どもたちにとっては、”わたしの蕎麦”になるのではないか」と教えていただき、夏休み明けてすぐの本日、放課後の時間を使って種まきをすることになりました。
畑へ向かうと、すでに支援してくださる方が種まきの準備をしてくださっていました。畑には既に8月に入ってから種まきがされていて、子どもたちが蒔くスペースを取っておいてくださいました。あいさつをし、種の蒔き方を早速教わりました。そして、種同士の間隔が空くようにし、土をかぶせる時には鍬の平な部分を使って、しっかりと固めることがコツであることを知ることができました。
種まき開始です。それぞれ一列を担当し、畝に種を蒔き終えると、土を寄せつつしっかりと土を固める姿がありました。「先生、ぼくの顔見て!汗びっしょりでしょ!!」疲れている様子を伝えつつも、表情はとっても楽しそうな表情でした。
種まきを終え、感想発表では、「農家の方がこうやって蕎麦を育てていることが分かってよかった」「土を寄せるとか、大変な作業をしていることを知ることができた」「収穫が楽しみ」そんな声が聞こえてきました。
蕎麦の種蒔きのためにご準備してくださった地域の皆様、ありがとうございました。
クラブ活動の本格スタートは来月4日です。それぞれのクラブの様子も、お伝えする予定です。お楽しみに・・・。
8月22日(金) ヘチマ「も」成長 ~4年生~
| |
2学期二日目となりました。早速、各学級学習や活動が始まりました。
2時間目、校庭から子どもたちの声が聞こえてきました。畑や花壇で活動が始まる中、理科の授業でヘチマの観察をしている4年生の様子を見つめました。体育館横の小さな畑で、夏休み前に植えた苗が大きく成長していました。理科専科のH先生が管理してくださっていました。
この時間は、雄花と雌花の観察と、ヘチマの育つ様子を観察しているようでした。観察した様子をスケッチしている子もいました。観察を終えたAさんに、「雄花と雌花はどう違うの?」と聞くと、Aさんは教えてくれました。「雄花にはぷっくりしているものがあるけど、雌花にはそれがないんだよ」雄花と雌花を見分けるポイントを、Aさんは”ぷっくりがあるかないか”で表現しました。実際に雄花と雌花それぞれを観察すると、確かに”ぷっくり”が雄花にはありました。
スケッチを続けるSさんに話しかけると、「ヘチマが、めっちゃ大きくなっていた。夏休みの前には花が咲いて、そこに実みたいなのがあっただけだったんだよ」と、あまりの変化の大きさに、ヘチマが成長していることに、驚きの表情を見せながら話しました。
目の前のヘチマが大きく大きく育ったように、Sさんも、4年生のみんなも、全校のみんなも夏休みを経て、大きく大きく成長しました。昨日から始まった2学期の中でも、友を感じ、友を思い、共に関わり合いながら、青木三山の森の根のように、互いの根っこを邪魔することなく、”あらたなわたし”へとなっていってほしいと思います。そして、一人一人の持ち味が伸びるよう、先生たちも子どもたちの後押しが出来たらと思います。
8月21日(木) 驚きとワクワクの2学期が始まる
本日より2学期が始まりました。久しぶりの学校、ただそれだけでもワクワクするところに、今年も、”あの”黒板アートが6枚登場しました。教室を開けてびっくりです。目をまんまるくして、ランドセルを背負ったままの低学年がいるかと思いうと、3階までランドセルを鳴らせて駆け上がり、教室へ飛び込み、今年の黒板アートを楽しみにしていたことが伝わってくる、そんな高学年の姿も見られました。青木小にとっての恒例行事となりました。
海の世界、白猫、りんごと刃、出目金、鹿と光、そして樹木、武蔵野美術大学の学生さんが2日がかりで仕上げた作品に、子どもたちは感動していました。ただし・・・、黒板アートはすぐに消されることがルールです。制作した学生さんとのやりとりを終えると、1つ、また1つと、黒板に描かれた素敵な絵が消されていきました。子どもたちは本当にじっくりと作品を見つめ、学生たちの言葉に聞き入っていました。絵の残像は、きっと子どもたちに残ったのではないでしょうか。
その後清掃を済ませ、2学期の始業式が始まりました。新しい先生と出会い、3名のお友だちの発表を聞きました。2年生のHさんは「難しい問題に挑戦したい」、4年生のAさんは「習っているダンスをがんばりたい」、6年生のDさんは「児童会まつりを成功させ、小学校生活最後の2学期を大切にしたい」と、素敵な発表を全校の前でしてくれました。その後、私からは、夏休みの思い出を少しインタビューし、また、それぞれの学年学級で2学期どんな学びや活動が生まれるのか、そういったところに思いが馳せられるような話をしました(したつもりです)。最後は全校で校歌を歌いました。2学期には、音楽会があります。どんな音楽会になるのかな?そんなことも思いつつ、子どもたちが歌う姿を見つめつつ、歌いました。
その後、それぞれの学級の様子を見ようと教室へ向かうと、夏休みの作品が早速飾られていました。それぞれの作品を鑑賞したり遊んだりしているクラスもありました。子どもたちの1つ1つの作品を見つめても、やぱりその作品には”わたし”がいるのです。「どんな風に作ったのかな」「誰と一緒に作ったのかな」「作りながら、どんなことを考えていたのかな」そんなことを、自然とその子に聞きたくなる自分がいました。夏休みの思い出が色あせぬうちに、子どもたちと”わたしの夏休み”を聞いてみたいと思います。
さあ、みんな、2学期も素敵な物語をつくろうね!!
8月7日(木) かめ吉だって気持ちよく ~かめ吉すいそう掃除~
朝、事務室の先生が、夏休み期間中限定で昇降口前に引っ越してきたかめ吉の様子を見つめ、「かめ吉の水、きれいにしてあげたほうがいいと思うので、午後、水の入れ替えをやりたいです」と言ってくださったので、午後の時間を使って、水槽の水の入れ替えを行いました。お二人の先生方も一緒に手伝ってくださいました。
事務室のK先生は、事務室入り口のガラスの装飾も行ってくださっています。現在は”夏真っ盛り”なので、某アイスクリームをモチーフに、当たりくじ付きのアイスを飾ってくださっています。この飾りつけの発案は、7月に事務室掃除を担当の6年生Cさんで、同じく清掃に来ていたDさんも一緒に3人で作成しました。
そんなK先生が、3組Bのみんなが大切にしている”かめ吉”のために時間をつくってくださいました。水槽のそうじを終え、きれいになった水槽に浸るかめ吉を見ると、何だかうれしそうな、気持ちよさそうな、そんな表情に見えました。これで夏休み後半、かめ吉も子どもたち同様に、気持ちよく生活ができそうです。
かめ吉さん、私たち職員をこれからも癒してくださいね!!そしてK先生、かめ吉のため、子どもたちのために、ありがとうございました。
8月6日(水) ”上には上がいる”ということ ~自転車全国大会~
8月5日の午後、青木を出発しました。出発時には本校の職員だけでなく役場の方々もお見送りに来てくださいました。ありがとうございました。
宿舎へ到着し、会場となる東京ビックサイトの下見に出かけました。あまりの大きさと広さにびっくりでした。宿舎近くの商業施設で夕食を済ませ、少しだけお目当てのお店を見学し宿舎へと戻りました。
そして本日(6日)、全国大会当日を迎えました。会場には全国42都道府県の選手、保護者、チーム関係者が集まり、色とりどりのユニホームが会場を華やかにしていました。本校チームカラーは青色でしたが、島根、熊本、沖縄も同じ青色でした。
会議室にて筆記テストが行われ、その後、技能テストが行われました。当初、あまり緊張感を見せていなかった選手4名も、自転車に乗る他県の選手の様子を目の当たりにし、緊張が一気に高まったようでした。4名ともに精一杯の走行を披露することができました。・・・が、走行を終え戻ってくる表情は、やりきった表情ではありませんでした。県大会を終えた時の表情とは明らかに違っていました。悔しかったのだと思います。
あれだけ練習を積み上げてもなお、”上には上”のチームがいて、その事実にも驚かされているようでした。走行後の子どもたちの声も、「何で失敗したのか・・・」「全然だめだった」「普段を出すって難しい」など、消化しきれない気持ちを何とか消化しようとする体からの絞り出すような言葉でした。
帰りのバスでは、「ああ、終わっちゃうのヤダ。練習もっとしたい」の声が聞こえてきました。「来年も出場して、来年こそはもっといい成績をおさめたい」そんな意欲の声にも聞こえてきました。
これまで練習のためにコースを設定し、丁寧にご指導いただいた安全協会の皆様、本当にありがとうございました。そして保護者の皆様、練習ならびに大会出場へのご理解ご協力ありがとうございました。選手のみんな!来年も全国目指しましょう!!がんばりました。
8月5日(火) 姉妹都市 長泉へいざ! ~長泉サマーキャンプ~
本日、村の文化会館へ朝6時に集合し、長泉サマーキャンプに参加を希望した4,5年生およそ20名が静岡の地へ出発しました。
長年続くサマーキャンプには信州大学の学生もサポートメンバーとして参加してくださいます。5月に行われた通学合宿にも来ていた学生さんたちなので、子どもたちにとっては顔なじみのお兄さんお姉さんで、久しぶりの再会を喜んでいる、そんな姿にも見えました。
出発式では、代表のRさんが、「協力して頑張りましょう」と、一緒に参加する仲間、学生、見送りに来てくださった保護者に向けて発表しました。学校代表で引率する教頭先生からは、「このキャンプのみんなの目標を達成するためには、みんながちょっとずつ我慢することです」とアドバイスをくださいました。教育長からは、風の影響で日程が変更する可能性もあることを事前にお伝えいただきました。日程通りにはならない、何かハプニングがあるかもしれない、そういった時にどう臨機応変に判断するのか、そういったところにも成長の機会があることを伝えてくださっているように感じました。
天気予報では暑さが心配です。無理をせず、長泉キャンプでしか味わうことのできない素敵な体験を通して、大きく成長してきてほしいと思います。
本日お昼には、自転車クラブのメンバー4名が、全国大会へ向けて出発をします。静岡の地で豊かな体験をする子どもたちもいれば、全国大会へ向け東京へ出発する子どもたちもいます。青木で培ってきた度胸を自信に変え、双方の地で豊かな体験をしてきてほしいと思います。
静岡の地も、東京の地も、みんなを待っています!!
8月2日(土) 熱を帯び 思いが集った なつまつり
暑さまだまだ残る夕刻、北村村長の開会宣言により、今年の夏祭りが始まりました。青木村保育園年長さんの義民太鼓が披露され、日頃の訓練を繰り返す消防団のラッパ隊の演奏が響き、各地区ごとの神輿が村民グランド内を練り歩きました。その内側では、青木村ならではの民謡に合わせ踊りも披露されました。各地区ごとの人数の差はありますが、地区ごと工夫を凝らした神輿を担ぎ、わっしょい、わっしょいの掛け声に合わせ、汗を流しながら頑張りました。
日が沈むころに合わせ、ステージには青木小学校金管バンド30名が登り、会場に集った多くの人たちの前で、素敵な演奏を披露しました。およそ15分間、4曲を演奏しました。メンバーの代表が挨拶と曲紹介をしましたが、緊張しながらもしっかりと伝えることができていました。最後には、パートごとのメンバーが目立つように立ったり座ったりを繰り返し、楽器を演奏しながらの振り付けもあり、会場を驚かせました。夏休み中に入ってからも午前練習を続けてきた金管バンド、練習の成果を十分に発揮した堂々とした演奏でした。会場からは大きな拍手をいただくことができました。
金管バンドの演奏後には、先日長野県大会の出場を決めた中学校吹奏楽部の演奏、県内はもちろん県外でも演奏を披露する義民太鼓の皆さんの力強い演奏と続き、クライマックスは会場に集ったみんなが楽しみにしていた大花火大会でした。浦野川のすぐそばから上がる花火の数々は本当に圧巻でした。大きな花火が上がり、大きな音が青木三山めがけてこだますると、会場からは歓声と拍手が上がりました。
本当にきれいな花火でしたが、きっと集った皆様一人一人が、その花火を見つめ、村の益々の発展、家族の幸せ、平和な世界などなど願ったのではないでしょうか。私はというと、花火を見つめながら、欲張ってたくさんの願いを巡らしていました。その1つは、もちろん青木小学校に通う全校ひとりひとりのますますの成長です。
夏休みが始まってちょうど一週間が経ちました。夏休みならではの体験や経験を通じて、心も体と頭を刺激して、ひとまわり大きくなった子どもたちと出会うのが楽しみです。
お空の神様、花火が終わるまでいいお天気にしていただき、ありがとうございました。
7月29日(火) 夏祭りに向かって ~金管バンド~
夏休みに入っても、金管バンドの練習は続いています。「練習の熱量は、さらに増した」とも言えます。それは、8月2日のステージが近づきつつあるからです。祭りの熱量は、村からも伝わってきます。学校前の信号沿いには、夏祭りに合わせ提灯が飾られ、夜には、その提灯が道を照らし、夏祭りが近づいてきていることを感じます。
提灯の明かり同様に、金管バンドのメンバーの心にも、当日へ向かう”灯(明かり)”が光輝き続けています。夏休み練習2日目のこの日は、青木中学校にお勤めのパーカッション専門の先生が臨時講師で来てくださいました。私は、冒頭10分ほどしか練習の様子は見ることはできませんでしたが、講師の先生は、メンバーひとりひとりの奏でる様子を真剣に見つめていました。
音出しを終えて、早速夏祭りのステージで演奏する曲練習がはじまりました。「きらきらぼし」を終えると、「名探偵コナンのテーマソング」へと移りました。顧問のS先生からは、「楽しく演奏しようね。そのためにはキャラクターのコナンを常にイメージしないとね。アニメをイメージしながら演奏すれば、きっと楽しく演奏できると思うよ」と言葉を伝え、演奏が始まりました。音色からは、楽しさだけでなく、メンバーみんなの2日の本番へと向かう真剣さが伝わってきました。
練習は、まだまだ続きます。当日は夕刻とは言いつつも、まだまだ暑さが残る時間帯です。暑さ対策をしっかりとし、練習で得た自信も音に加え、みんなならではの演奏を村の皆さんの前で披露してほしいと思います。
校長日記をご覧の皆様、ぜひ村祭りのステージへお越しください。そして、お声がけできる方がいたら、ぜひお誘いください。一人でも多くの方の前で演奏できることが、金管バンドにとって今後へとつながります。よろしくお願いします。
当日の夕刻、雨に当たりませんように・・・そして、夜には素敵な花火が夜空を彩りますように・・・
7月28日(月) 早起きをして ~地区のごみ拾い~
本日より、夏休みが始まりました。出張の前に学校へ寄ったのですが、子どもたちが「おやよう」とやって来ないのかと思うと、やはり淋しさがあります。
そんな朝の始まりでしたが、実は、朝の時間に早起きをしてウォーキングをしました。毎日とはいかないまでも、可能な時は「青木を歩こう」と発信している本人がまずは歩かないとと思い、出かけました。浦野川沿いを歩き(ときどき走り)、村営グランドを見ながら、道の駅方面へ向かうと、親子でゴミ拾いをしている姉妹を見かけました。「あっ、あれはきっと○○さんだ」と思い、何気なく近づくと、お母さんが私に気づき、その後、二人と目が合いました。お母さんと三人で地区のごみ拾いを一生懸命行う姿に出会い、何だか得をした気持ちになりました。「よし、夏休みが始まったけど、仕事がんばるぞ!」と気合も入れていただきました。
早起きは、一日のリズムを作るのに最適です。暑い暑い毎日ですが、朝のそよ風は心地よく、鳥の鳴き声、カエルの鳴き声も、体を癒してくれます。時間があるときは、ウォーキングを続けるつもりです。子どもたちはもちろん、私自身も生活のリズムを意識して、夏休みならではの過ごし方をしていこうと思います。
7月25日(金) 「夏休みに行ってきます」 ~1学期最終日~
本日、学期が終わりました。
桜満開を迎える4月、1年生が新たに仲間入りし、新しい先生方をお迎えし、1学期が始まりました。全校遠足では学年ごと(5、6年生は合同登山)に大宝寺三重塔、リフレッシュパークあおき、昆虫資料館、十観山、夫神岳を目指し、全校で青木を感じました。運動会では、多くの保護者の前で、素敵な演技と競技と走りを披露することができました。
学年それぞれの活動も充実しました。
1年生・・・運動会の忍者がその後も続き、プールの学習では、忍者修行と銘打って、小プールでの活動
を自分たちで考え、楽しく活動することができました。
2年生・・・体育館裏の学校の畑を”わたしたちの畑”へと変身させ、思い思いの野菜作りが始まり、収穫
できたときには、最高の笑顔を見せていました。
3年生・・・青木の各地をめぐり、自分が暮らす地区自慢をしていました。自分を育ててくれたかつての
場所へも訪問し、心とからだを開放し、存分に青木を味わうことができました。
4年生・・・社会科の学習で、様々な地へ見学に出かけました。水のゆくえ、ゴミのゆくえ、普段当たり
前に見えているもの(水、ごみ)のその後を知ることができました。
5年生・・・海(谷浜)の宿泊学習を通して、大きく成長しました。海の学習でできたこととできていな
いことをあらわにし、普段の生活を見つめ直す、そんな姿がありました。
6年生・・・児童会のフロントランナーとして、学校を支え、全校が楽しめる時間と機会を作ることがで
きました。修学旅行に向けた学習も動き出し、今後が楽しみです。
3組4組・・・一人になっての活動、みんなとでの活動、めりはりをつけ活動することができました。畑
の草取りもがんばりました。2学期には販売に向けた準備も始まります。楽しみです。
本当に、その学級ならではの活動、営みがあり、学級の様子、一人一人の嬉々とした表情に出合うのが本当に楽しみだった1学期となりました。
本日は、8月6日に東京有明で開かれる交通安全子供自転車全国大会に出場する4名の壮行会も行われました。優勝旗やカップなどを手にし、ステージへと上がり、2人の団長の声高らかなエールをもらい、教育長からの激励もいただき、選手代表のTさんが、頑張る宣言をしました。午後には、村役場での表敬訪問もあり、そこでも選手たちは、「青木村のすごさを示してきたい」と宣言しました。全国優勝を本気で目指す子どもたち、全国大会へ参加できることへの感謝の気持ちを忘れずに、練習の成果を存分に発揮してきてほしいと思います。 がんばれ!!
今日の清掃の終わりの放送が流れた時、職員室掃除を終えた6年生数名が、教頭先生に向けて、
「”夏休み”に行ってきます」
と伝えている場面がありました。教師になって初めて出会う言葉でした。この言葉には、「楽しみな夏休みに行ってくるけど、夏休みが終わったら、ちゃんと大好きな学校に帰ってくるからね」の思いが含みこまれている言葉に聞こえました。
私自身、帰り際に出会う子どもたちに、「夏休み、たくさん遊んでね。楽しんでね」と声をかけました。が、その言葉の裏では、「学校は、みんながしばらく来ないから、寂しくなるんだよ。早く戻ってきてね」とも思っていました。
今年の夏はこれまで以上に暑いです。熱中症にはくれぐれも気を付け、もちろん安全も意識しつつ、わたしならではの素敵な夏休みをつくってほしいと思います、1学期、大変お世話になりました。
7月23日(水) どちらが美味しい?どちらも美味しい! ~セレクト給食~
本日の給食は、いつもと違った給食でした。その理由は、献立を”選べる”からです。
地域の食材を生かした給食を毎回提供いただき、本当に美味しい給食を子どもたちも職員も食べていることできているわけですが、本日のメニューには、村内で冷凍食品の製造を行っている沓掛冷食さんの春巻が献立の中にありました。その春巻きが”選べる春巻”になっていたのです。1つは『肉野菜春巻』、もう一つが『ひじき春巻』でした。事前にアンケートをとり、どちらの春巻が食べたいかを選び、その選んだ春巻きが子どもたちのもとへ提供されました。
セレクト給食ははじめてのことだったので、いくつかの教室を訪問しました。1年生の教室では、いただきますのあいさつを済ませ、すでに給食を食べていました。近くでおいしそうに食べるTさんを見ると、きれいに春巻がなくなっていたので声をかけると、「ぼくは、好きな物から食べるから、春巻きはもう食べちゃった」とひとこと。それを聞いていた前に座るKさんのお皿には、まだ手付かずの春巻がありました。同じく声をかけると、「僕はね、好きなものは最後に食べるから、まだ残してあるんだよ」とひとこと。二人の食べ方は違えど、二人とも春巻が大好きなこと、今日のセレクト春巻を楽しみにしていたことが伝わってきました。
5年生の教室もお邪魔して、セレクトした理由を聞いてみました。「めずらしいから、ひじきにしてみた」「ひじきが好きだからひじき春巻にした」「野菜が好きで春巻も好き。それで、肉野菜にしたよ」「そっちの方が美味しそうだなって思って、それで」など、私が選んだ理由を教えてくれました。
今回のセレクト春巻は今回のみではなく、2学期にも行う予定です。次回はどんな春巻を選べるのか。そこからわくわくしてしまいます。ちなみに私は今回、ひじき春巻をいただきました。次回も悩みに悩んで、決断したいと思います。
普段は、調理員さんが手間と暇をかけて作ってくださる春巻ですが、今回は地元の工場でこだわりをもって製造された春巻でした。地元で製造された春巻を美味しく揚げてくださった調理員のみなさん、ありがとうございました。
7月22日(火) もうすぐ夏休み
三連休が終わり、1学期の学校生活も残すところ4日となりました。朝から20℃を超える中、今日も子どもたち元気に登校してきました。
玄関には、1年生が1学期お世話を続けてきた朝顔のプランターが並んでいます。先週は、綺麗に咲く朝顔のお花と一緒に、一人一人記念撮影をしている場面に遭遇しました。青にピンクに紫色と、色とりどりの朝顔が全校の登校を見守っています(今週、どこかで各ご家庭へ持ち帰ると思います)。
朝顔が咲く隣では、庁務の先生(S先生)が草刈りをしてくださっています。右の写真は校庭北側の花壇ですが、こちらも先週、マリーゴールドをはじめサルビアなど、綺麗な花の苗が各学年ごと植えられました。雑草が無くなり、花の苗植えがやりやすくなっていましたが、その下準備をしてくださったのもS先生でした。
夏本番を迎え暑い日が続いているわけですが、雨も程よく降ってきているので、草の皆様にとっては背を伸ばす絶好のコンディションです。そんな草の対処を環境整備のフロントランナーとして、S先生がやってくださっています。先日のPTA作業でも保護者の皆様のお力を借りて環境整備をしましたが、S先生の支えもあり、整った環境で様々な活動ができています。
今日の1時間目には、2年生が”わたしの畑”の収穫だけでなく、とてつもなく伸びた草と格闘していました。野菜の成長とともにまわりの草も育っていくことを実感した時間にもなったと思います。今週も、各学年で様々な活動、学びが繰り広げられます。わくわくです!!
7月18日(金) お魚さん どこへ行く ~さかなの放流~
今週の雨で浦野川の水量ならびに水流が心配されましたが、本日無事にイワナとヤマメの成魚放流が行われました。
この放流をプロヂュースしたのは教頭先生です。浦野川をもっと身近に感じてほしい、もっと川へ行ってほしいと願い、「放流がきっかけになれば」と地元の漁業組合の指導のもと、放流を行いました。1、2年生は水着に着替え、プールを横目に浦野川へ一直線、バケツを渡され、そのバケツに水を汲み、成魚のさかなをいただいて、いざ放流タイムです。そうっと魚を掴み、そうっとリリースする子がいれば、どこか魚を掴むのを拒みつつも放流がしたいと頑張る子、バケツを横にして手放すというよりも魚が自然と川へ向かうようにしばらくその様子を見つめる子もいました。放流のさなか、「お魚おいしそう!食いたいな!!」こんな声も聞こえてきました。
放流タイムを終えると、川と遊ぶタイム。川の流れを楽しんだり、バケツ片手に放流したばかりのイワナとヤマメをゲットしようとしたり、綺麗な石探しを始めたりと、思い思いに川と遊んでいました。
1、2年生が浦野川を後にすると、竹で作った手作りの竿を持ち、教頭先生と釣りを始めるTさんの姿がありました。Tさんはこの日を待ちわびていました。庁務の先生にお願いしていた竹が届いた先週、教頭先生と竹を改良し竿にしていました。「この竿で早く釣りたい」その思いが今日叶いました。残念ながら、魚を釣ることはできませんでしたが、Tさんの表情は大満足の表情をしていました。自分のやりたいことが、とことんできた証です。今日は6年生も川へやってきて、低学年顔負けの即席のつかみ取り大会が始まり、3匹をゲットしました。「何か、今、足のところ魚が泳いでいった」「今あっちにいった」「いたよ!いた!ここ、ここ!!」そんな子どもたちの嬉々とした叫び声が、遠くに見える夫神岳まで届いたひとときとなりました。
週末、川へと向かう場合には、くれぐれも保護者同伴、安全に十分気を付けてください。
空の鳥さんたち、放流したてのお魚を取っていかないでね!よろしくお願いします。
7月16日(水) 歌声を全校で ~音楽集会~
朝の時間に、1学期最後の音楽集会が行われました。コの字の隊形をつくり、音楽専科の先生の振る指揮を見つめ、音楽会に向けて歌い始めた♪エール♪という曲を全校で歌いました。
今日のポイントは2つありました。1つは出だしの「か」をはっきりと歌うこと。もう1つは、曲の山(サビ)を盛り上げることの2つでした。1つ目の「か」は何回か練習をするうちに、はっきりとした「か」に聞こえるようになりました。2つ目の山を盛り上げる部分は、直前の歌詞の伸ばすところを、先生が上手にリズム感じられるようにじょじょに盛り上がっていく様子を、実際に歌いながら伝えてくださったことで、こちらも盛り上がりの頂点に達した状態で、サビの「世界中の・・・」につなげることができました。
どの学年の子どもたちも生き生きとした表情で、ステージに立つ先生を見つめながら歌っていました。1年生は大、大、大熱唱でした。私はと言いますと、まだしっかりと歌詞を覚えていないため、大熱唱したくても歌詞を間違えてはいけないと、スクリーンに映し出される歌詞を見ながら歌うことになってしまいました。早く覚えて、大熱唱したいです。
歌は本当に素敵です。隣の友だちの声、周りで歌う人の声と一緒に歌えることの心地よさを味わい、歌うことで元気にもなります。朝の時間、教室からも歌声が聞こえてきます。その歌声を聞くと、うれしい気持ちになり、また「よし!がんばるぞ!!」の気持ちにもなります。
音楽会は2学期にあるのでまだ先ですが、保護者はもちろん、地域の方々にも聞いていただけたらと思います。
7月13日(日) 子檀嶺岳の頂から
朝4:00、学校前の公民館を出発し、青木三山の1つである子檀嶺岳の山頂へと向かいました。この時期なので、5時前には明るくなり、涼しい中での山登りとなりました。
この日は、子檀嶺岳山頂にある奥社にて夏の大祭が開かれることから、青木区に暮らす一人として、この大祭に参加したい旨を関係者の方へお伝えし、一員として参加させていただきました。30名近くの方が山へ登り、大祭で使うもの(鱒、薪、飲み物、水、野菜、おにぎりなど)を分担して山頂まで運びました。到着後は準備を整え、7時ころから儀式を行い、その中で、名前を呼ばれたので、小学校の代表として、子どもたちの安全、学校活動でのお支えとお導きを祈願しました。
一通りの儀式を終え、山頂からの景色に目を向けると、それまで霧がかかっていた景色が『雲海』へと変化し、その後、雲の切れ間から下の景色も見えるようになりました。オレンジ色の小学校もくっきりと見えました。学校から見える子檀嶺岳は毎日見ていますが、子檀嶺岳からはこうやって学校が見えていることを知ることができました。
今年度、地域の行事では4月に村松西地区の子ども神楽を見させていただく機会もありました。これから始まる夏休み期間中も、それぞれの地区で子どもたちがワクワクする催しも企画されています。この日は、村営プールのプール祭りもあり、多くの子どもたちがプール祭りに参加したようです。
「地域の子どもは地域で育てる」「青木の子どもは青木で育てる」と言っていただいています。地域の催しに参加する度に、地域の思いや願いに学校がこたえなければと、強く思います。地域にひらかれた、地域と学校がつながり合う、そんな学校になるよう、職員一同思いを一つに、取り組んでいきます。
7月12日(土) 悲願の県大会V ~自転車クラブ~
長野市の東和田運動公園体育館で行われた交通安全子供自転車長野県大会に、上小地区の代表校として参加し、見事優勝を果たしました。
県大会には団体の部に7校9チームがエントリーし、技術を競いました。昨年同様、とても暑いコンディションでしたが、子どもたちはAチーム、Bチームともに集中力を切らすことなく、これまでの練習の成果を発揮し、技術も含めすばらしい安全走行を披露することができました。
昨年、一昨年と連続準優勝だったので、「今年こそは」の思いを選手はもちろん、指導をしてくださる安全協会の皆さんも抱いていました。閉会式での結果発表の瞬間は、会場がシーンと静まり返り、
「優勝は、青木小学校Aチーム」
と発表された瞬間、応援席からは歓声が上がりました。個人の部でもAチームのメンバー全員が10位以内に入賞するという快挙も達成しました。
当日の応戦席には、チームのメンバーになれなった仲間4名も、応援にかけつけました。走行が始まるアナウンスが流れると、大きな拍手をし、自分たちの近くに仲間が来ると、「○○ちゃん!!がんばれ~!」と精一杯の声援を送っていました。今回の快挙達成は、仲間の応援を聞き、安心して走行できたことも要因のひとつです。最後の最後まで声援を送り続けたみんな、本当にありがとう!!
8月6日、いよいよ全国大会です。会場は有明になります。全国大会は全くもっての未開の地。まだ見ぬ頂だからこそ、臆することなく、堂々とわたしならではの走行を自信をもってしてきてほしいと思います。もちろん、これまで指導してくださった安全協会の皆様への感謝の気持ちも忘れずに、1つでも上の順位を目指し、今年のメンバーでしか達成できない最高の結果をおみやげに持ち帰ってきてください。
優勝おめでとう! 次なる目標は、全国制覇!! 本気でめざしましょう!!!
7月11日(金) 浮くって楽しい ~1年生~
今週は(今週も)、毎日プールに入ることができました。連日の暑さが続いていることもあり、子どもたちは、プールの時間をとても楽しみにしています。
今日の2時間目には、小プールに1年生が、大プールに3年生が入り、浮く・泳ぐ時間を楽しく過ごしていました。1年生は『にんじゃしゅぎょう 水のまき』と題し、プールの底に2回手をつく術、2周回ってジャンプをする術、くるくると回る術、そして潜って2回まわる竜巻の術を行っていました。担任の先生に聞くと、この”術”は、子どもたちが考案したとのこと。運動会で発表した”忍者の世界”が、ここプールにでも繰り広げられていることに、驚かせると同時に、子どもたちの発想力にも驚かされました。1年生は、修業をする中で、ぷかぷかと浮き、体を見ずに委ねている、そんな姿に見えました。
大プールでは、3年生が浮く+泳ぐ活動をしていました。一昨日、3年生のプールの時間、私も同席させてもらいました。浮くだけでなく、プールの端から端まで蹴伸びをしたり、バタ足をしたりしながら泳ぎにつながる動きを何回も行っていました。3年生は1年生以上に長く浮くことができていたので、1年生以上に体を見ずに委ねているようでした。
どちらの学年も、最後は竜巻(流水)をつくり、仲間と関わり合いながら、水の中のひとときを楽しんできました。来週5日間と再来週3日間で、今年度のプール(浮く、泳ぐ)の学習は終わります。限られた期間ですが、思う存分、水で遊び、水と遊び、そして水に体を委ね、水と一体になってほしいと思います。
12日(日)には、村民プール祭りも行われ、村民プールが本格オープンを迎えます。学校のプールが終わっても、きっと多くの子どもたち、夏休みには村民プールで、水との時間を過ごすことと思います。安全に気を付けて、楽しいひとときをつくりましょう!!
7月8日(火) 県大会にむけて ~自転車クラブ~
自転車クラブの活動が佳境を迎えています。先日の上小大会を終えた選手たち、次なる目標は12日(土)に長野市で行われる県大会での優勝です。
全員が揃うことはありませんが、参加できる限り参加し、放課後練習を続けています。写真は、本日の練習の様子です。連日の暑さから想像できる通り、放課後であっても体育館の中は蒸し暑いです。そんな中、3名の安全協会の方がお見えになり、指導をしてくださっていました。指導してくださる方も汗びっしょりです。
ほんの少し練習の様子を見つめました。館内に設えられた、公道に見立てた道を模擬走行する練習場面でした。一人また一人と時間差でスタートし、その都度指導される方がアドバイスをしてくださいました。走行を終えると、しばらく待つのかなと思いきや、5年生のHさんは、指導員の方に、「終わったらどうしたらいい?」と聞いていました。それを聞いた指導員の方は、「だったら25秒走行やるか!」と一言。質問したHさんは、「分かった!!」と言って、25秒走行の練習ができる場所へ向かっていきました。
練習の間、体育館は練習に関係のないおしゃべりは聞こえてはきませんでした。本当に真剣そのものでした。体育館を去るとき、指導員の方にお礼を伝えると、指導員の方は、「子どもたち、自転車の練習を通して、本当に成長していますよ」と温かな言葉をかけてくださいました。県大会まで残すところ3日となりました。県大会当日の結果云々ではなく、こういった日々の練習の積み重ねの中で、選手一人一人は、それまでのわたしから”新たなわたし”へと進化しています。だからこそ、本番では、練習を積み重ね生まれ得る”自信”を力に変え、わたしならではの走行をしてきてほしいと思います。
がんばれ!みんな!! めざせ優勝!! 学校みんなが応援してます!!
7月7日(月) 七夕かざりと 願い事
今日は7月7日、七夕です。先週から、1年生の廊下、2年生前の階段をはじめ、教室の廊下や教室内に、七夕飾りがお目見えしました。1年生の教室では、友だちと関わり合いながら、折り紙を使って”お飾り”を作っている姿もありました。
七夕当日の今日、飾られている短冊に目線を向けました。そこには、
「パイロットになりたい」「鳥になりたい」「大工さんになりたい」
「おかしのお家に住みたい」「頭がよくなりますように」「ピアノが上手にひけますように」
「誕生日プレゼントに真珠のネックレスがほしい」といった、わたしの夢、願いごとが、一人一人のその子ならではの字で書かれていました。私は子ども時代、おそらくですが、「プロ野球選手になりますように」と書いたように思います。
一人一人の短冊の中に、「みんなが元気になれますように」という短冊がありました。これはみんなのことを思う短冊でした。2年生の子が書いた短冊ですが、みんながの”みんな”には、自分の家族を表すみんななのか、クラスのみんななのか、もっと違った意味のみんななのか、聞いてみたくなりました。
子ども落語に、七夕の噺があります。確か、天に暮らすひこぼしとおりひめが、子どもたちからのあまりの多さの願い事が届けられ、すべての願い事をかなえることに自信を(やる気を)失い、「どうか天の神様、この子どもたちのすべての願いをかなえてくださいますように」とお願いをするという話だったかと思います。
どうか、子どもたちの願い事が、かないますように!!
7月3日(木) 海の学習② ~5年生~
海の学習、二日目の様子です。
朝、6時20分に起床し(それよりも早く目覚めた子たちも)、全員浜辺に集合し、15分間散歩をしました。近づく波に足先を出し楽しんだり、貝殻やお気に入りの石を探したり、水切りを始めたりする子もいました。「水切り、7回弾いたよ」と教えてくれる子もいました。温かな朝日を浴びながらのお散歩はとても気持ちが良かったです。
その後、ラジオ体操を済ませ、朝食となりました。食事係が気を配りながらみんなの分を配膳していました。朝から食欲ばっちりで、おかわりする子も大勢いました。海に向けての腹ごしらえでした。
朝食を終えると、部屋の片づけをしました。宿泊係が積極的に動き、あっという間に部屋やトイレ、浴室ときれいになりました。
そしていよいよ二日目の”海の時間”、前日よりも若干長めの時間設定だったので、昨日以上に思う存分、海を満喫することができました。波に揺られ、波を感じ、照り付ける太陽の光を感じ、友とかかわり、時に水かけっこで戦い、休憩時間には砂浜で砂と戯れ、思い思いに海時間を楽しむことができました。海の時間終了の笛が鳴ると、「もう終わっちゃったか」とがっかりな様子も見られました。それだけ、没頭していたのだと思います。
シャワーを浴び、旅館での最後の食事、”カレーの時間”となりました。「うまい」「おいしい」が飛び交い、おかわりを複数回した子もたくさんでした。私自身も、旅館のカレーを楽しみにしていたので、三杯いただてしまいました。ごちそうさまでした。
いよいよ退館式。旅館の方から、「二日間どうだったかな?楽しかった?」と聞かれると、「ハイ!!」という大きな声の反応が聞こえました。充実した時間を過ごせた証に聞こえました。
帰りのバスでは多くの子が寝てしまうかなと思いきや、元気に会話を弾ませる子がたくさんでした。
係活動を責任もって行った5年生、わたしならではのあいさつができる5年生、そして、仲間を気遣いながら海の学習を過ごした5年生の姿に、二日間の成長はもちろん、今後ますます進化していく5年生が楽しみになりました。
今頃、お家での夕飯を食べながら、二日間の海の学習エピソードで会話を弾ませていると思います。てるてるさんたちのおかげで、両日ともに最高の天気に恵まれました。素敵な二日間となりました。
7月2日(水) 海の学習① ~5年生~
いよいよ本日、5年生の海の学習が始まりました。天気は問題なし。たくさんの人が作ってくれた”てるてるパワー”で、好天に恵まれました。
まずは上越水族館うみがたり。イルカショーでは、子どもたちの歓声がたくさん聞こえてきました。館内をグループ見学し、最後はペンギンさんに餌をあげました。とっても楽しいそうでした。
うみがたりを後にし、旅館に到着。入館式では、旅館に方に「よろしくお願いします」と、心を込めてあいさつすることができました。手作りのお弁当を食べ、いよいよ海の時間。
ひとりまたひとりと、砂浜へとかけてきました。準備体操を済ませ、いよいよ海を味わう時間です。どんな様子で海に入るのか見つめると、ブイまで一気に泳いでいく子、恐る恐る海に入っていく子、波打ち際に座り込み砂の感触を確かめる子、貝殻さがしを始める子、足をバタバタさせ水しぶき合戦を始める子などなど、思い思いの入り初めをしていきました。その後は、十分時間があったので、水攻撃アイテムで先生たちを狙ったり、ヤドカリを見付けて即席のヤドカリ動物園を砂浜に作ったり、浮き輪に乗ってぷかぷかと波の感触を味わったりと、本当に楽しく過ごすことができていました。
学年の目標に『安全』にも気を配り、無理はせず、海と波に呼応するように、海を満喫していました。
海の学習、まだまだ続きます。
6月30日(月) お友だちをはじめてお迎え ~1年生~
本日から一学期最終日まで、1年2組に、アメリカの学校へ通っている1年生のYさんが期間限定でやってきました。Yさんの祖父母が青木にいることで、今回の体験入学が実現しました。
1年2組のSさんは、学校へ来るとき、「今日ね、わたしのクラスにSちゃんが来るんだよ」と教えてくれました。Sさんは、普段そんなに話しかけてくる子ではないので、早く会いたい気持ちが、話かけてくる様子からも伝わってきました。
校長室で待つSさんをクラスのみんなで迎えに来て、Sさんをお招きしての朝の会(ようこその会)が始まりました。いつもは黒板に向かっている子たちが、この時間は窓側の後ろに座るSさんの方向を向き、質問タイムが始まりました。「好きの色は何ですか?」と質問され、「ピンク」と恥ずかしそうに答えました。続けて、「好きな食べ物は何ですか?」と質問され、Sさんはすぐに答えることができませんでした。しばし沈黙の時間となりました。その間、Sさんを見つめる子どもたちの頭が、上半身が、ぐっとSさんの方向に傾きました。Sさんに吸い寄せられているようにも見えました。担任の先生は、答えられなくて困っているのかもしれないと思い、「私はね、納豆が大好きだよ!」とSさんに向かって話すと、「私も好き」「ぼくも大好き」と続き、それを聞いていたSさんの表情が緩み始めました。和やかな雰囲気となりました。この時、Mさんは、左手にお椀を持ち、右手にお箸を持ち、何かを食べている物まねをしている子がいました。「Sさんが困っているのは、何を聞かれていて何を答えたらいいの分かっていないのかもしれない」と思ったのだと思います。子どもの柔軟さ、しなやかさに感動です。
この後、好きな果物、好きな花と続いていきました。
Sを迎えた1年2組。いつも仲良しですが、Sさんが来たことによって、その仲の良さが、磨かれていく予感がしました。Sさん、早く学級に馴染んで、”普段のわたし”を出してくださいね。そんなSさんに出会えるのも、何だか楽しみになりました。
6月28日(土) 保護者の力 PTA除草作業
本日、6時30からPTA除草作業が行われました。秋に2回目があり、今回は3年、4年、6年の保護者の方のお力をお借りし、敷地内の草取り(草刈り)を行っていただきました。もちろん、職員も参加し、一緒に活動しました。
朝の早い時間にも関わらず、本当に多くの保護者のみなさまにご参加いただきました。感謝です。全体会を終えて作業が始まりました。朝の涼しい時間帯ではありますが、暑さが感じられる中、概ね1時間、それぞれの分担場所をきれいにしていただきました。駐車場、側溝の周辺、学校畑、遊具広場など、たくさんの草を刈っていただきました。写真は遊具広場の様子です。本当にきれいになりました。休み時間になると、多くの子どもたちが我先にと駆けていく場所です。週明け、遊具広場へ駆けていくと、「きれいになっている!!」と気づくこと間違いなしです。
私自身は、早朝、グランドを散歩される地域の方がいらっしゃるので、学校西側から畑を通って校庭へ向かう道の草刈りをしました。両側から雑草が伸び、道を覆うようになっていたところが綺麗になると、やはり清々しい気持ちになりました。行為をしているのは自分自身であっても、その行為によって誰かが気持ちよくなる(今回であれば歩きやすくなる)ことに、その行為がつながっていれば、「何かいいことができた」そんな気持ちになります。保護者の皆様の行為は、紛れもく子どもたちの心地よさに繋がっています。本当に、ありがとうございました。
6月27日(金) 連なる『てるてる』 5年生のために
てるてるアナウンスをしてから、1つまた1つとてるてる坊主が増えていき、今週には準備しておいた紐の端から端まで、てるてるが連なり埋め尽くされました。
昨年度はほぼ白に統一されていましたが、今年は黄色に青にピンクにと、色とりどりのてるてる坊主がBOXに届けられ、吊るしました。てるてる坊主には願いが記されているものもあり、「5年生のために晴れますように」と、具体的な願いが伝わってくるものもありました。
来週がいよいよ海の学習となります。九州地方では平年よりも20日以上早く梅雨宣言が発表されました。新潟の海もおそらく”てるてる効果”で晴れ渡る海を見ることができそうですが、熱中症と紫外線も心配です。ほどよく、心地よい空の下、存分に海を味わえたらと思います。
てるてる坊主を作成いただいたみなさん、ありがとうございました。「飾り終わったら、ちゃんと返してね!」と返却の予約をした子もいます。海の学習を終えたら、必ず返却いたします。ご安心を・・・
6月26日(木) より学校 よりよい活動へ ~児童会~
6時間目は、児童会が行われました。それぞれの会場で、委員会として決定事項があれば、話し合いをしたり、定期的に行う活動のある委員会は、その活動を行っていました。
図書委員会は、図書館に集まり、児童会まつりのことと季節に合わせた図書館装飾についての話し合いが行われていました。具体的にどんな装飾にしたいのかの意見も出され、とても活発でした。健康委員会では、ポスター掲示が行われていました。校内を巡り、ここぞという場所を選択し、熱中症にならないための対策が発信されました。絵にこだわった子もいて、その子は、「校長先生見え!ここがね・・・」と説明までしてくれました。こだわりのポスターであることが伝わってきました。
写真はありませんが、この他の委員会では、どんな児童集会を企画するかの話し合いや、定時放送をリニューアルするためにどんな放送にしていくかの話し合いや、全校鬼ごっこを成功するためにどうしたらいいかなど、各委員会で活発な話し合いが行われていました。
すべての委員会活動に共通していることは、”学校がよりよくなるため”、”全校一人一人がもっと楽しくなるため”、”全校が安全に過ごせるため”です。「わたしの委員会ならでは」の企画に、ぜひチャレンジしてほしいと思います。応援しています!!
6月24日(火) フォークダンスでの触れ合い ~5年生~
7月に行く、海の学習では、1日目の夕刻から夜にかけてビーチファイヤーを行います。その中で行うフォークダンスの踊り方を、地域のフォークダンスクラブの方に教わりました。1時間の中で4つのダンスを教わりました。私は冒頭だけの参加だったため、『マイムマイム』を5年生と一緒に踊りました。マイムマイムの由来からはじまり、ステップの踏み方、声の出し方など、細部にわたり教わりました。実際にやってみると回を重ねるごとに子どもたちは分かってきて、掛け声の声も弾むようになりました。
しばしの休憩時間にフォークダンスクラブンの方と話をした時、「男女関係なく、手を握り合うことが心とからだのためにもいいんですよ」と話してくださいました。マイムマイムでは、手を握ってステップを踏む時間が長くあります。そして曲の中で、手を離して手拍子をして再び手を握る時があります。お互いのディスタンスを保たなければいけなった頃は”手を握る”ことは許されませんでした。今は日常が復活し、直接対話をすることができるようになりました。対話はもちろん、こういったフォークダンスをする中で、振りを合わせ、声をそろえ、手をつなぎ、お互いの存在を、分かり合ってほしいと思います。
今日は体育館でしたが、当日は、波の音が聞こえ、潮風を感じ、遠くにはイルカの群れも登場するかもしれません。そんな当日の海に思いを馳せ、海の学習当日に向けた活動を充実させてほしいと思います。
6月21日(土) 上小地区の代表として ~自転車クラブ大会出場~
21日(土)の午後、本校体育館を会場に、交通安全子供安全上小地区自転車大会が行われました。本校から、自転車クラブの所属する17名のうち12名が出場しました。
この大会は、自転車に乗る時の交通安全の意識向上をめざし行われている大会です。かつて私も佐久地区大会に小学校の代表として出場したことがありますが、歴史ある大会になります。
昨年は県大会準優勝という成績をおさめましたが、昨年度のメンバーがほとんど6年生だったため、今年度は、昨年度から所属するTさん1名からのスタートとなりました。何とかメンバーを増やしたいと、指導をしてくださっている安全協会青木支部の皆様も思いもあり、4月の交通安全教室でTさんに自転車のモデル走行をしてもらい、この大会で披露する自転車の技能も全校の前で披露してもらいました。そういったことが功を制し、メンバーが17名に増えました。
当日、都合で出場できないメンバーもいましたが、12名の選手全員が、これまでの練習の成果を披露することができました。審査をしていくださる警察の方に見守られ、ステージ上からは、ご来賓の皆様、保護者の皆様にも見守られ、これまで味わったことのない緊張感に、心がドキドキ状態の中での、精一杯の走行でした。
上位3名が表彰されましたが、出場した全員に拍手を送ります。来月には長野市で開かれる県大会の団体戦に出場します。日頃高め合う仲間同士、県大会に向けた練習に励み、青木小の代表はもちろん、上小地区の代表として、そして本校の安全リーダーとして、すばらしい走行をしてきてほしいと思います。
がんばれ!!自転車クラブ!!
6月20日(金)② 夜空に舞う ホタル
写真を撮影することはできていませんが、先週あたりから、青木の里の夜に、ホタルがやってきました。夫神橋から学校裏あたりにかけての観察を続けてきていますが、今週のはじめまでは、たった1匹のホタルにしか出合うことができませんでした。
ところが・・・、昨夜(19日)のことです。夜8時30分頃、自宅から夫神橋を流れる浦野川(沓掛川)沿いを眺めていると、複数の光が夜空に舞っていました。興奮し、対岸へまわり、学校の裏付近まで散歩をしつつホタルの数を数えると、21匹のホタルと出合うことができました。あっちへ行ったりこっちへ行ったり、夜空を彩るホタルの光は、心もからだも癒してくれました。
ホタルをたくさん観察できる田沢温泉付近には、もっと多くのホタルが舞っているそうです。今週末が、今シーズンのピークを迎える予感がします。安全には十分気を付け、ホタルに出会える場所を家族でナイトウォークすること、お薦めします。
ご家族皆さんが、たくさんのホタルたちに 出合えますように・・・
6月20日(金) てるてるさんに 願いを込めて ~てるてる大作戦~
5年生は、7月に行われいる海の学習にむけた準備を進めています。水族館見学と海水浴、そして、この仲間との初めての宿泊、楽しいことばかりの二日間の計画を子どもたちが主体となって行っています。私は、前年度に引き続き、今年度も海の学習の隊長を務め、子どもたちと二日間を共にします。
この二日間を有意義な二日間にするために、自分自身ができることは、その二日間を安全に過ごせるよう配慮することと、事前に行えることとすると、”てるてるさん”に願いを込めることです。昨日、”てるてるさん”募集の知らせを昇降口に貼りだし、回収ボックスも設けました。すると、本日、そのボックスにはたくさんの”てるてるさん”が入っていました。早速、庁務の先生に紐の準備を依頼し、少しずつではありますが、飾り始めました。その様子を見ていた先生が、こんなことを教えてくださいました。
「Nさん、去年5年生だったので海の学習に参加して、その時、たくさんの”てるてるぼうず”をみんなに作ってもらって、そのおかげで当日いい天気になったから、今年は、その恩返しとして、私がてるてるぼうずをたくさんつくりたい」
こんな素敵なことを話していたことを教えてくれました。心が温かくなると同時に、その優しさに対してのお礼を伝えたくなりました。下校時に、ちょうどNさんに会えたので、早速感謝を伝えました。
去年と今年とでは、参加する子どもたちはもちろん違います。今年は今年の海の学習を5年生が作り上げます。去年と今年は違っていても、去年と今年の海の学習は”連なっている”ことを、Nさんが教えてくれました。
私自身、できる限りの”てるてるさん”を作ろうと思います。この校長日記をご覧いただいている保護者の皆様で、お時間許す方いらっしゃいましたら、5年生のために、もちろんこの2日間、青木の空も晴れ渡り、プールの楽しいひとときが全校味わえるためにも、お手製の”てるてるさん”よろしくお願いします。ボックスに直接入れていただいても、校長室へ届けていただいても構いません。よろしくお願いします。
海の学習 晴れわたる空でありつつ 心地よい天気に なりますように・・・
6月17日(火) プールから響く 子どもたちの声 ~プール開幕~
今年度のプール学習の幕が開けました。朝の時間に体育館でプール開きをし、早速プールに入ることができました。今年の入り初めは4年生でした!!
プール開きの時には、青木小学校のプールの歴史について伝えました。今使用しているプールはなんと、今から64年前の1961年12月に完成し、翌年から使用が始まりました。計算をすると70歳を超えた人たちが小学生の頃から使っているプールになります。子どもたちはとても驚いていました。
プールを使うにあたって、今年も4年生、5年生、6年生が中心となり、プール清掃を行ってくれました。プールを磨いてくれたみなさん、ありがとうございました。
入り初めをした4年生の様子に戻ります。プールサイドで準備体操をし(ワクワク!)、シャワーを浴びて(ウワー、冷たい!けど気持ちいい!)、プールサイドにならびプールの中へ入りました(ちょー気持ちいい)。早速バディー同士で水中ジャンケンが始まりました(ジャンケンポン!かったー、まけたー)。知らぬ間にプール中央に向かって密かに泳ぎ始めようとする子どもたちもいたような・・・。
プール学習は、常に複数対応をし、安全を最優先に活動を進めていきます。
1回でも多く、プールに入れますように!!
6月16日(月) コーチ!見て!! ~1年生~
5時間目、青木村のサッカーチームでコーチをされている方にお越しいただき、1年生のサッカー教室が行われました。毎年1年生2年生に開催しているので、1年生は初めての教室でした。園の時にもお世話になったコーチなので、緊張することなく、スタートから和やかな雰囲気で始まりました。
ボールを触る前には、コーンをジグザグに走ったり、ジャンプしたりとコーディネーション的な活動をし、ボールに触れる時間となりました。1人に1つずつボールが配られると、早速蹴る真似をしてみたり、ボールをなでなでしてみたり、ボールを床に落としてバウンドさせてみたりと、サッカーボールを自由自在に操り始めました。次はボールを空に向かって投げ上げてキャッチする活動です(右の写真)。ちょっとあげてキャッチして、それができるともっと高く上げてみて、少しずつ投げ上げる高さが増していきました。うまくキャッチできると、子どもたちが発する言葉は共通でした。「コーチ見て~!」「私できるから、見て!!」でした。出来るようになった自分を見てほしいのです。そして、褒めてほしいのです。出来きたその瞬間を見逃さず、そういった瞬間に子どもは見ていてほしく、そして褒めてほしい。そういったことを改めて感じた瞬間でした。
私自身も、子どもの”旬”を見逃さず、見とどけて、その子のがんばり、良さを、その子本人に届けたいと思います。
6月13日(金) 子どもの姿を見つめて ~参観日~
本日は、参観日でした。参観授業前には2年生の給食試食会が開かれ、ランチルームで親子一緒に給食を食べました。会話を弾ませ、おいしそうに食べる様子が見られました。私は、Hさんと一緒に食べました。「Hさんの大好きな食べ物は何?」と聞くと、「おばあちゃんが作るカレーが大好き!」と答えました。”カレー”ではなく、”おばあちゃんが作るカレー”と答えるところに、Hさんにとってのおばあちゃんは特別な存在、大切な存在、そしてHさんはおばあちゃんのことが大好き、そういったことが伝わってきました。
参観授業では、発表する場面があったり、育てている野菜を一緒に観察する場面があったり、1年生では親子レクが行われ、音楽室では6年生が歌声を響かせ、目を潤ませながら歌声に聞き入る保護者の姿もありました。学校に普段の様子を見ていただくことができました。ありがとうございました。
授業参観後には、体育館で「校長講話」の時間をいただいたので、今年度大切にしている『3つの根』(思い合いの根、学び合いの根、関わり合いの根)にかかわる具体の姿を、運動会で出合った素敵なエピソードからお伝えしました。そして、『関わり』をキーワードに、多様な他者と関わり合うことの大切さ、直接的な体験活動がコミュニケーションを伸ばしていくこと、青木を歩き、家族や仲間、自然と触れ合うひとときは、豊かな心をを育む時間であり空間でもあること、このような話をさせていただきました。体育館まで足を運び聞いてくださった保護者の皆様、ありがとうございました。
6月13日(金) 全校ペアになって歌って踊って ~音楽集会~
音楽集会が朝の時間にありました。
『翼をください』を歌いながらの入場から始まりました。全校が集い、音楽の時間に行っているあいさつを体育館に響かせました。輪唱にもなり、いい声が響きました。
次は、本日の活動のメイン、『手のひらをたいように』でした。ご存じの通り、やなせたかしさんが作詞した有名な歌です。この歌を、1年6年、2年5年、3年4年でペア(2人~4人くらい)をつくり向き合って、振り付けも交えながら歌いました。学級とは違った友だちの前で歌ったり踊ったりすることに恥ずかしさあるように歌う子もいれば、歌手(ダンサー)になったかのようにノリノリで歌い踊る子もいました。表現の仕方、伝え方は、それぞれです。
最後に、音楽専科の先生から、次回は音楽会に向けて全校で歌う曲を、みんなで歌うことのアナウンスがあり、入場時と同様に、『翼をください』を口ずさみながら退場していきました。
たった15分間でしたが、音楽専科の先生が考えた、15分間の授業でした。ねらいがあり、ねらいを達成するための子どもにとってやりたくなる活動があり、振り返りをする。授業にとって大切なものが15分間に詰まっていました。音楽会はまだまだ先の10月ですが、今年の音楽会をほんの少し思いを馳せた、音楽集会でした。
6月11日(水) 梅シロップ作り交流 ~3,4組~
3組、4組さんで梅シロップづくりを行いました。副学籍の友だち(上田養護学校小学部に通う青木村の小学生)をお招きしての交流会でもありました。
左の写真は、前日の様子です。Hさんは翌日行う梅シロップづくりに向け、脚立に乗り、1粒1粒の梅を丁寧にとっていました。いつもよりも高い場所にいる自分自身を感じ、黙々と収穫していました。
そして、本日、学校で収穫した小梅はもちろん、家の木から収穫した梅も一緒に、梅シロップづくりが始まりました。副学籍の友だちも混ざって、工程を確認し、容器にたくさんの梅が入っていきました。今回出来上がった梅シロップは、すぐには完成しません。子どもたちが喜ぶ”あの味わい”になるには、しばらく時間がかかります。昨年もそうでしたが、このシロップは自分たちで味わうだけでなく、秋の参観日に合わせて販売活動も行う予定です。
梅シロップの味わいには、甘味はもちろんのこと、今日みんなで関わり合い、楽しんだ時間の、”おいしいエキス”も含まれています。ぜひ、ご購入いただき、子どもたちならではの梅シロップを味わってほしいと思います。
どんどん、どんどん、美味しくなあれ!!
6月6日(金) どろを味わう(田植え) ~5年生~
本日、3、4時間目に5年生が田植えを行いました。地域ボランティアの方にご準備いただき、田植えをしました。水田の代掻きなどはボランティア方にやっていただいているため、子どもたちにとっては田植えの体験になります。家の田植えを手伝っている子もいれば、田植えが初めてという子もいて、経験値は様々でした。
子どもたちは一列になり、苗を持ち、「植えていいぞ!」の合図に手に持つ苗を植えていきました。かんかん照りではありませんでしたが、子どもたちは汗を流し、がんばりました。どことなく泥に触れることに抵抗感がありそうな子もいれば、「土、気持ちい~~」と言いながら、みんな以上に足踏みをして、泥の感触を味わっている子もいました。
私が、田んぼに到着したときには、二人の女の子が、「校長先生見て~~」と言って、やんわりと握った手を私の目の前にもってきて、「ほらあ」とアカハライモリを見せてくれました。田んぼを見つめると、あっちにもこっちにもイモリが泳いでいて、「こんなにも当たり前にイモリがいるのか」と驚きました。「これ、持って帰って飼うんだ」とも言っていました。学校で飼うのか、それとも家に持ち帰って飼うのか、どちらなのかは分かりませんが、泥を味わい、生き物とも触れ合う、素敵な姿でした。
地域の方のおかげさまで、田植えができていることへの感謝を忘れず、田んぼを管理していく中で、自分たちにできることを見つけ、”わたしの稲、わたしのお米”にしていってほしいと思います。私はと言いますと、おいしくいただく収穫の時を心待ちにしたいと思います。
「ふっくらごはんが、味わえますように・・・」
6月5日(木) 全校のために ~プール清掃~
運動会が終わると、6月からはプールの学習が始まります。プール開きを控え、今週は、4年生、5年史、6年生がプール清掃をしてくれました。4年生はプールサイドを中心に、5年生は大プールを中心に、6年生は小プールと、大プールと小プールの境のフェンスをきれいにしました。
暑い中の作業でしたが、安全のためのヘルメットを着用し、時間の限り清掃を行う姿がありました。5年生の作業をする様子を見ている時、ちょうど休憩をして水分補給をしているTさんがいたので、「Tさんは、一人黙々と作業をしていて、先生だったらもしかするとさぼりたくなっちゃって、さぼることもあるかもしれないけど、Tさんは、さぼることなく続けられるのはどうして?」と聞いてみました。すると、Tさんは迷うことなくその理由を教えてくれました。「それはやっぱり、プール清掃は全校のためにやっているから、僕がさぼっちゃうと、全校のみんなに迷惑かけちゃうことになるから、だからやるんです」と迷わず口にしました。本心からの言葉であることが、そこからも伝わってきました。
4、5、6年生にとっては、自分たちできれいにできたプールで、1、2、3年生にとっては、きれいにしてもらったことへの感謝が込められたプールで、思う存分、水遊びに、水泳に浸りこんでほしいと思います。まずは、水で遊び、そして水と遊び、究極はプールの水をも自分のものとし”水と一体に”なってほしいと思います。水泳学習は楽しさと危険が共存しています。そのことを職員は肝に銘じ、子どもたちと共に、水泳学習をつくっていきたいと思います。
6月4日(水) 地域を歩くよ!年長さんと ~1年生~
奇跡の、そして素敵な運動会が終わり、1学期の後半が始まりました。
この日は、1年生が午前中の時間を使い、年長さんと一緒にお散歩に出かけました。1年生の散歩の活動に年長さんを誘ったのではなく、年長さんが計画していた散歩に1年生が合流する形のお散歩でした。この時期は桑の実が取れるので、桑の実をゲットできる場所への散歩を考えていましたが、まだ時期が若干早いことから村民グランドまでのお出かけとなりました。
児童昇降口前に集合し、ご対面をし、仲良く手をつなぎ出発していきました。散歩の途中、道端に咲く花や木々についての説明を1年生の植物に詳しい担任の先生がしてくださり、のんびりとした散歩となりました。
実は、このお散歩の時間帯に、プールでは6年生がプール清掃を全校のためにしていました。そこへ、1年生と年長さんのお散歩隊が帰ってきたのです。ちょうど、年長さんには6年生にお兄さんお姉さんのいる子もいて、「お兄ちゃんどこ~?」の声が聞こえてきました。妹や弟がやってきたことに気が付くと、プール内からフェンス越しまで出てきて、自分の妹、弟を探す様子もありました。見つけた時には、「あ~、いたいた!」とお互い顔を見合わせ、うれしそうでした。
プール横には桑の木があり、若干まだ早い桑の実を年長さんはうれしそうに採っていました。今年は、小学校でも、青木を(地域を)歩くことを大切に考えています。3年生では、各地区を巡り(散歩し)、地区自慢をお互いにし合っています。ゆっくりと歩き、時に立ち止まることによって、普段見過ごしている場所、ものに子どもたちは出会っています。ご家庭でも、朝に夕刻に、あるいは休日に、少し青木を歩くのもいいかもしれません。みんなで青木を歩きましょう!!
5月31日(土) 運動会② 感謝、感激、雨ふらず
大成功、大感動の運動会が終わりました。
校庭には、朝早くから保護者の皆様が集まり、運動会の始まりがまだかまだかと、待ちわびる姿が見られました。
金管バンドの素敵なファンファーレが響き渡り、全校が式台前まで行進し、運動会が幕を開けました。
前半は、かけっこ・短距離走が行われました。1年生2年生は直線を走り、3年生以上はコーナーが含まれるコースを走り切りました。一緒に走る仲間を感じ、目が合った時にニコッと笑顔を見せる、そんな様子もありました。応援席からは、白組がんばれ、紅組頑がんばれの声援で盛り上がっていました。
後半は、各学年の発表と競争がありました。
1年生:あおきっこ忍者
忍者になりきり、忍者ポーズも決め、かわらしい忍者の世界をつくりました。戦いの場面は、かっこいいというよりも格好良かったです。玉入れも盛り上がりました。
2年生:ライラック
切れきれダンスを披露しました。ステップを踏み、様々な隊形移動をし、ニコニコ笑顔の2年生でした。担任の先生のダンスの上手さに、村長さん驚いていました。
3年生:再びネバーギブアップ(台風の目)
竹を使って旋回をしながら、紅組と白組が競い合いました。普通サイズの後にはビッグサイズの竹も登場し、会場びっくりでした。大接戦の熱戦でした。
4年生:信濃の国ダンス
社会科の学習で出合った『信濃の国』をダンスで表現しました。途中、別の曲も流れ、自分たちで考案した踊りを4つのチームごとに発表しました。お見事でした。
5、6年生:フラッグ&組体操
前半が組体操、技をやるごとに仲間を感じ、様々な技を成功させていきました。後半は色とりどりのフラッグを揺らしながら、自分たちで考えた表現を披露することができました。保護者のみなさん、感動していました。
今年は低学年種目として、綱引きも行われました。一回戦も二回戦ともに白組が勝利をおさめましたが、どちらも大熱戦でした。
全校種目のボール運びリレーも4色のチームに分かれ競いました。違う学年の子同士で編成されているので、高学年が速く走って運ぶことはできません。高学年は低学年を感じ、低学年は高学年を感じ、巨大ボールを運びました。会場大盛り上がりでした。
最後は校歌ダンスを全校、保護者、来賓の皆様も一緒に踊りました。手にする旗の音が心地よく響き、運動会をしめくくる温かなダンスとなりました。
現在、13時30分を過ぎました。窓の外からは雨音が聞こえてきます。この雨が降り始めたのは、運動会のすべての片づけを終えた後でした。子どもたちの活躍を終え、保護者の皆様なのご協力のもと終えた後片付けの様子を、空の神様は見ていたかのようなタイミングでした。まさしく”奇跡の運動会”。その運動会を作り上げた子どもたちのパワーは、やはりすばらしいです。集ったすべての人たちに喜びと感動を与えた子どもたち、6月からの学校生活でも、大活躍すること間違いなしです。
最後にひとこと・・・、天気の神様には、感謝感激あめ降らず!!
5月31日(土) 運動会① 通常開催決定!!
おはようございます。予定していた運動会、開催決定となりました。昨日、運動会を開催するかどうかを悩み、可否判断をどのタイミングでしたらよいかも悩み、当日の朝、判断することを決めたわけですが、日の出の時間になると太陽も見え、天気予報も参考にし、通常通りの開催決定の連絡を5時50分にいたしました。
左の写真は、開催決定連絡をした直後のグランドの様子です。グランドコンディションは最高です。ほどよく水分を吸収し、砂埃が舞うこともなく、最高気温は低めではありますが、天気が味方してくれました。太陽さんありがとう。
右の写真は、クローバーです。昨日の前日準備が終わった時、5年生のTさんが、「校長先生、ひとつあげる」と言って、プレゼントしてくれました。クローバーはもちろん『よつばのクロバー』です。Tさんの手にはいくつものよつばのクローバーがありました。「明日の天気が心配で、明日の天気を願いつつ、Tさんはよつばのクローバーを探したのかな」そんなことを、私に手渡すTさんの表情を見つめ、感じました。もしかしたら、Tさんのクローバーも、今日の天気に一役買ったのかもしれません。
雨の心配が無くなったというわけではないので、休憩時間を短くするなどして、若干プログラムを早めていくかもしれません。
とにもかくにも、予定していた運動会開催日に、通常通りの運動会を行えることは、今週の天気予報からすると”奇跡”です。令和7年度の運動会、大勢の皆様のお越しをお待ちしております。
大勢の方に見守られ全校が集う様子を思い浮かべる、ただそれだけで、何だかわくわくしてきます!!
5月30日(金) 子ども主体でつくりだす ~5、6年~
運動会前日となりました。左の写真は昨日(29日)の5,6年生の表現の練習風景です。昨日は雨が降ることなく、校庭で練習することができました。が、本日は、朝からの雨模様となり、右の写真のように、すべての学年の練習は体育館で行われました。
今回はと言いますか、運動会練習特集の最後は、5、6年生の表現です。昨年の5、6年生はフラッグとダンスを披露しました。今年の5、6年生は、写真の通りのフラッグと写真にはありませんが、組体操に挑戦します。
フラッグでは、旗を揺らす時に生まれる独特な音を表現したり、一律表現だけでなく、動と静を織り交ぜながら、旗と一体となったオリジナルな表現を披露します。
組体操では、BGMの曲に合わせながら、一人技から複数技まで披露します。「騎馬戦をやりたい」と強く願った仲間の思いも受け取り、演技の途中に騎馬を組み、騎馬が動き出す表現もします。ここは私もまだ見ていないので当日が楽しみでなりません。
フラッグにしろ組体操にしろ、どちらも練習を進めていたのは5年生の先生でもなく、6年生の先生でもなく、担当になった6年生でした。マイク片手に、丁寧に分かりやすく動き1つ1つを確認し、よりよい表現になるよう説明をしていました。重ねるごとに自信も出てきたのか、堂々と全体に説明する姿に成長を感じることができました。
5年生と6年生が一体となって表現する、アレンジも含みこまれた表現を、どうか楽しみにしてください。ただし・・・、天気が心配です。今は雨が上がり、前日準備が始まるところですが、明日は雨の予報です。実施するかどうかの判断はこれからですが、全校168名と先生たちとで作り上げる青木小ならではの運動会、私自身も楽しみたいと思います。新たなトロフィーも運動会を見守ってくれます。
こうご期待!!
5月29日(木) 仲間同士が競い合い ~3年生~
運動会の競技種目は、各学年のかけっこ・短距離走、1年生の玉入れ、低学年の綱引き(今年度より)と3年生の『台風の目』になります。紅組白組それぞれに、大きく長い竹を操り競い合います。
複数人で竹の棒を横にし、3つのコーンで旋回し、折り返してきます。いかに速く旋回するかがポイントのようですが、あまりに速く旋回すると、遠心力で外側の棒を持つ子がそのスピードに追い付けなくなるので、ほどよく小さく回るのも大事な要素になります。
今日は、競うというよりも回り方を確認し合う場面でした。「うわあ、遠心力かんじる!」と外側を持った時に伝わってくる、何とも言えない遠心力と、旋回することによって発生する風を、心地よく味わっている、そんな姿に見えました。
聞くところによると、接戦が多いとのこと。当日は、赤が勝つのか、それとも白が勝つのか、当日もわくわくです。本日、全校の前に立った応援団に、応援を盛り上げてもらい、やる側も見る側も、心躍らせ楽しみたいと思います。
3年生は、ぜひ、一緒に竹の棒をもつ友だちを感じ、しなやかに動きを合わせ、競いながらも友を感じる、そんな瞬間もつくってほしいと思います。頑張れ、3年生!!
5月29日(木) 当日をイメージして・・・ ~全校練習~
運動会当日を2日後に控えた今日の朝の活動から1時間目は、運動会当日をイメージしての全校練習でした。体育主任の先生から、「今日は5つのことを実際にやりながら確認していくよ」と呼びかけがありました、5つとは、①入場行進 ②開会式 ③ラジオ体操 ④全校ダンス(校歌ダンス) ⑤閉会式
の5つでした。
入場行進では、金管バンドの音色が全校にお披露目されました。ファンファーレが校庭に響き渡り、演奏とともに入場行進がはじまりました。音に合わせ、力強く本部席に向かって歩きました。
開会式では、式台に上がった人をしっかり見て、お辞儀をすることの確認をしました。紅組も白組も教頭先生のお辞儀に合わせて、お辞儀を返すことができていました。開会式では応援合戦と歌も歌いました。
白組:「上履きの色は~~」「しろ~~」 「○○の色は~~」「しろ~~」
紅組:「りんごの色は~~」「あか~~」 「○○の色は~~」「あか~~」
どちらも盛り上がりました。応援合戦の次は、歌でした。途中、音楽専科の先生のアドバイス(気合)もあり、大盛り上がりでした。当日をお楽しみに!!
次は、ラジオ体操。私も気持ちよくやらせてもりました。途中途中、体操をしつつ空を見上げ、「天気が心配だけど、当日青空見えるといいあ」と心の中で願いました。
体操の後は、少しの休憩を挟み、全校ダンス(校歌ダンス)を踊りました。子どもたちの手には、白、赤、オレンジなどの旗が握られ、素敵な音を鳴らしながら踊りました。運動会当日は、ぜひ保護者、ご来賓、地域の皆様も、子どもたちと一緒に踊ってください。
最後は閉会式の練習でした。紅組、白組、どちらが勝ったかの結果発表の練習、トロフィー授与の練習もしました。トロフィーは、もちろん昨年の児童会役員が制作したアオキノコちゃん型トロフィーです。団長それぞれに渡す練習も行うことができました。
明日は、天気が崩れる予報のため、校庭での練習はできないかもしれません。明日は体育館で最後の練習を行い当日となりそうです。とにもかくにも、天気予報に一喜一憂するここ数日となっています。天気の神様、なにとぞ青木小はもちろん、上小管内の子どもたちのために、雨雲が来ることなく、当日を迎えることができますように・・・。
5月27日(火) 開会式を引き立てる ~金管バンド~
運動会は、昨年同様に金管バンドの演奏によって幕が開かれます。
今年度のメンバーは、新4年生を迎え28人。4月から早速練習がスタートし、土曜日の休日練習も行っています。全校の前で演奏するデビューが運動会ということもあり、音楽専科の先生のご指導のもと、日々の練習に励んでいます。朝練習はおよそ30分、休日練習はおよそ2時間。金管バンドのメンバーと関わり、担当する楽器と馴染み、楽器とも仲良しになりながら、私ならではの音色を見つけてもいます。
この日の朝練習には20名ほどのメンバーが集まり、運動会で披露する演奏の練習を続けていました。この日の最後には、担当の先生から、「今まで一番いい演奏だったよ。これを運動会本番でもやろう」と賞賛の声をいただき、子どもたち、とてもうれしそうでした。練習後、5年生のNさんに、「楽器演奏するの楽しい?」と声をかけると、「すごく楽しいよ」と声が返ってきました。運動会の開会式で披露する発表からも、その楽しさが伝わってくるかと思います。
運動会の開会式で演奏する時間は、なんと”1分”。その1分のためにメンバーみんなが一つになり、練習に励んでいます。その1分から始まる運動会が、いよいよ近づいてきました。
運動会、天気になりますように・・・ 予報を見ると、心配であります・・・。
5月26日(月) 今年は忍者にヘンシンです ~1年生~
1年生の練習の様子です。
今年の1年生は、忍者に変身します。合言葉は「ニン!」。表現の合間合間に忍者ポーズを見ることができます。
曲に合わせて入場すると、手裏剣を飛ばす振りがあったり、忍者ポーズをとってみたり、白忍者と赤忍者が戦う場面も登場します。隊形も全体になったり、丸くなったりと、目まぐるしく変化します。戦いの場面では、毎回”戦い方”が変わります。運動会当日、どんな戦い方をするのか、どんな”決め忍者ポーズ”を披露するのか、とっても楽しみです。
演技の後半は、1年生恒例の『玉入れ』です。今日の決戦はどうやら白組が勝ったようですが、僅差の勝利だったので、明日も明後日も、そして当日も、どちらに勝利の女神がほほえむのかは分かりません。見る側はもちろん、玉を入れる一年生本人たちも、ワクワクです。
1年生にとっては、小学校として参加する初めての運動会です。園よりもひろ~くなった校庭で、大活躍してほしいと思います。かけっこではどんな表情を見せるのか。こちらも楽しみです。
とうじつ てんきに な~あれ!!
5月24日(土) 千曲川上・下流住民による共同植会祭参加
24日(土)、参加希望者12名、保護者5名、引率職員とで、青木村内の森で行われた『千曲川上・下流域による共同植樹会に参加してきました。雨がぱらつく天候でしたが、主催者の皆様、長野市長沼地区の皆様のお力も借り、予定よりも短時間で植樹を行うことができました。
植樹した木はアカマツです。根の部分20センチほどが埋まるくらいに穴を掘り、そこに垂直に植えるアドバイスをもらい、150本の苗木を植えました。子ども同士、あるいは親子でペアとなり、クワを使って穴を掘り、苗木を垂直に立て、土を穴に戻す作業を、1本また1本と続けていきました。
青木村森林組合の方から、森の働きについても教わりました。森には、水を貯え、洪水や渇水を緩和する、あるいは水質を浄化するという”水源かん養機能”と、山崩れや土砂の流出を防ぐ”土砂災害防止機能”があることを知ることができました。青木には『十観山』『子檀嶺岳』『夫神岳』があると同時に、山林が村の80%を占めています。森とともに生きると言っても過言ではありません。
森が間近にある子どもたちにとって、森の働きについて学び、植樹を体験できたことは貴重な経験となりました。昨年度の校長講話では、森の根について話もしました。決して隣の木の邪魔をせずに優しく、そして力強く根を伸ばす森のように、子どもたちも仲間を感じながら、仲間を助け仲間に助けられつつ、優しくたくましい心を育んでほしいと思います。
5月23日(金) 創作ダンスを織り交ぜて ~4年生~
昨年の4年生は、『ソーラン節』を踊りましたが、今年の4年生の表現は、『信濃の国ダンス』です。県歌『信濃の国』をダンスバージョンに編曲した音楽に合わせて踊ります。踊る様子を見つめると、信濃の国の歌詞を口ずさみながら踊る子たちがいました。踊ることを通して、長らく歌い継がれる歌詞を体にしみこませているようでした。
もちろん4年生も2年生同様に、アレンジを入れています。隊形を変化させたり、踊る人の人数を増減させたりと、わたしたちならではの工夫がされています。
曲の途中、別の曲が流れる場面もあることが判明しました。どんな曲が流れるかはここでは伝えませんが、こちらの曲が流れるダンスでは、子どもたちが創作したダンスも登場し、4つのグループごとに生み出したオリジナル表現をするシーンもあります。「○○さん、振りが違っているよ。こうだよ!」と伝え合う場面もありました。ダンスを踊りつつ、友だちのことも感じていることが伝わってきました。今日の練習には、副学籍の子もかけっこに出場する練習に来ていたので、みんなが踊っている中を、うれしそうに歩く様子もありました。
担任の先生に創作のことについて聞くと、「子どもたち自身でどんどんダンス(振り)を考えることができていて驚いています」と話されました。どうやら、担任の先生が思い描く以上のことを考え出しているようです。あと一週間で、更なるアレンジがあるのかもしれません。お楽しみに・・!
来週も天気が続きますように・・・
5月22日(木) こっちを向いて あっちを向いて ~2年生~
学年種目の様子を紹介します。2年生です。今週から校庭練習を始めましたが、教室と体育館で振り付けの練習をしっかりとしてきたようで、校庭練習の1回目から、全員で合わせた振りができていておどろきました。もっと驚かされたのは、担任の先生のダンスの上手さです。子どもたちの前で、先生も一緒に踊っているのですが、リズミカルに、そして柔軟に、子どもたちの動きに合わせるかのように踊っていました。
全員が終始前向きということはなく、途中ペアで向かい合って、昔の言葉でいうなれば”手遊び”をする場面もあるようです。もちろんそれだけではなく、前後が半分に分かれお互いが背を向きながら踊ったり、隊形を移動して新たな隊形になって踊る、そんな場面もあるようです。
様々な工夫があるということは、おそらく、子どもたちと先生とで創意工夫しながら、試行錯誤しながらの表現なのだと思います。
元気いっぱいに、素敵な表情で表現する2年生の表現(ダンス)、こうご期待です。疲れ切った状態で水分補給をするためにテント下へ向かう時も、猛ダッシュで向かう姿に、「疲れているけど、水分補給したら、またすぐに踊りたい!!」そんな気持ちが伝わってきました。
5月21日(水) 全校種目決定!! ~体育集会~
本日の体育集会は、4つの色(赤、青、緑、黄)に分かれて集まりました。理由は、運動会で行う児童会種目の内容が決まり、チームの顔合わせをして、どんなことをするのかを理解するためでした。
全体の進行は6年生の担任が行いましたが、チームごとに4人ずつの組を伝え、その組ごとに並ぶところを進めたのが6年生たちでした。チームごとに支援をしてくださる先生方もいたので、その先生方のサポートを受けながら、組編成を行っていきました。低学年に向けて、「○○さんは、△組だからね。私が一緒にやるからね」と、顔を近づけ、優しく言葉をかける姿もありました。
4つのチームそれぞれの組編成の確認が終わり、最後に全校種目でどのようなことをするのかの確認を行いました。今年度の全校種目は、「協力しよう!ボール運びリレー」です。6年生の代表4名が登場し、実際にどのようにボールを運ぶのかをやって見せてくれました。大きなボールを乗せた布の4隅を4人が持ち、落とすことなくボールを運ぶ様子を全校で見つめました。何をして、どうしたらよいのかが一目瞭然でした。道具の準備をしてくれた6年生のみなさん、実際にやってくれた6年生の4名のみなさん、ありがとうございました。
次回は、チームに分かれてやってみます。ボールをスムーズに運べた喜び、途中で落ちてしまうといったハプニング、様々な場面に出合うかと思います、私もその様々な場面で、子どもたちが味わうワクワクドキドキを一緒に感じたいと思います!!
5月20日(火) 青空の下 ~体育集会②~
先週に引き続き、運動会に向けた2回目の体育集会が行われました。前回は体育館でしたが、本日は校庭に集いました。
先週の職員作業で隊形のポイントを打ったので、そのしるしを目印に整列することができました。雲一つない晴天の下、全校が一斉にラジオ体操をしました。ラジオ体操は運動会当日の最初の種目になります、当日は、保護者の皆様も、地域の皆様も、そしてご来賓の皆様も一緒に体操をしてほしいと思います。よろしくお願いします。
校長室からはグランドが一望なので、パソコンと向き合い仕事をしながらも、校庭で走ったり競ったり、表現をしたりしている子どもたちの姿を見ると、気が付くとパソコンの手が止まり、子どもたちの頑張る姿を見入っている私がいます。耐えきれないときには、カメラを手に校庭へ飛び出し、子どもたちに声をかけつつ写真撮影をしている自分がいます。それだけ魅力的なのです。
運動会は当日だけがすべてではありません。当日を迎えるまでの葛藤、思いがけなさ、できるようなった喜びなど、当日までにため込まれた感情一つ一つが、当日につながる大切な営みです。保護者の皆様には、そういった”間の物語”も聞いていただけたらと思います。
5月15日(木) プロの演奏に引き込まれ、引き出され ~移動鑑賞音楽会~
東京レインボウ合唱団の皆さんが来校され、鑑賞音楽会が行われました。
子どもたちの前に登場した楽器は、ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスとピアノでした。それぞれの楽器について紹介と説明をする場面では、「この楽器の名前、知っているかな?」と聞かれ、楽器の名称をつぶやく子もいました。
鑑賞音楽会は冒頭の素敵な演奏によって引き込まれ、子どもたちの知っている曲も多く演奏してくださったおかげで、子どもたちから自然と手拍子も生まれ、演奏するごとに会場が一体になっていく、そんな雰囲気でした。
演奏の中盤では、♪翼をください♪が始まり、あらかじめ音楽の授業と朝の時間に学級で歌ってきた歌だったので、子どもたち大熱唱でした。「こんなに歌える子どもたち、素敵だなあ」と思いつつ、私も思わず熱唱してしまいました。
後半には、『きらきら星変奏曲』が演奏され、演奏後には子どもたちが注文(お願い)に応え、ピアノ演奏してくださる場面もありました。「ポップな感じ」「クールな感じ」などと注文を受けると、その感じが伝わるように演奏してくださり、教頭先生から「悲しい感じ」とお願いされると、本当に悲しくて泣きたくなるような演奏が始まり、楽団の皆さんも悲しくなり泣きながらステージから去っていくという、子どもたちにとって「まさかここまで・・・」といった演技も披露され、子どもたち大喜びでした。
演奏との途中途中では、演奏しながらステージからフロアへ降りてくださり、子どもたちの目の前で演奏もしてくださり、子どもたちにとって大満足の鑑賞音楽会となりました。プロの演奏に引き込まれつつ、心とからだが存分に開いている子どもたちなので、翼をくださいの場面では子どもたちの素敵な歌声が引き出されました。
今月末には運動会が行われます。心とからだを開き、わたしならではの表現を全校一人一人がしてくれるはずです。来週からは、運動会に向け取り組む、各学年の練習の様子をお伝えしていく予定です。
5月14日(水) 運動会にむけて ~体育集会~
14日(水)の朝、体育集会が開かれました。全校が集い、校歌ダンスの練習(昨年の復習もしつつ)をしました。ステージに上がり、進行をつとめたのは、今年度本校へ異動してきたばかりの先生でした。事前に先輩の先生方からアドバイスをもらい当日を迎えたわけですが、振りつけ(動き)を間違えてしまう場面がありました。その動きに6年生が瞬時に気づき、そのざわつきにステージ上の先生も気づき、修正するという場面でした。「みんなごめんね。先生間違えちゃった」と全校にお詫びする場面もありました。とても和やかな空気が生まれ、全校で歌いながら『校歌ダンス』を踊ることができました。次回は校庭での練習となります。手には、旗を持つかもしれません。いい音を天高く響かせてほしいと思います。
今週月曜日から『運動会特別時間割』がはじまり、各学年での運動会へ向けた練習も始まっています。右上は1年生のかけっこの様子です。担任の先生の、「ここまで走るよ」の言葉に呼応し、1先生の子どもたち、先生のいる場所まで必死に走っていました・・・と思いきや、なぜかスタート地点へ戻る時にも全力疾走で戻っていきました。もう走りたくて、友だちと競いたくてたまらない!!そんな姿でした。
今年度は、
1年生は、玉入れ+表現、かけっこ・・去年は「スパイ」今年は??
2年生は、表現、かけっこ・・去年は、「メラ」今年は??
3年生は、台風の目(競技種目)、かけっこ・・今年の競技は??
4年生は、表現、かけっこ・・去年はソーラン、今年は??
5・6年生は、表現、かけっこ・・去年はフラッグ&ダンス、今年は??
そして6年生が主体となって行う全校種目・・去年は全校リレー、今年は??
最後に、校歌ダンス・・こちらは会場みなさんご一緒に!
このようなプログラムを構成し、当日に向け、全校が1つになり、動き出しました。運動会スローガンは、
「安全に 楽しく 協力して 最高の運動会をつくろう」
です。怪我することなく、みんな楽しく、お互いを感じ合える、最高の運動会を目指します。
5月9日(金) 何とか天気がもちました ~春の遠足~
1週間遅れとなった遠足が、本日無事に実施されました。子どもたちも職員も、そして保護者の皆様も一安心でした。
1年生は、大宝寺と郷土美術館、2年生はリフレッシュパークあおき、3年生は昆虫資料館、4年生は十観山、そして5・6年生が夫神岳が目的地でした。
暑すぎず、かといって寒すぎず、ほどよい天候の下、自分の足を原動力に、目的地へと向かっていきました。私は、緊急対応がある可能性があるため、学校へ残り、元気よく出発する子どもたちと先生方の姿を、どこかうらやましい気持ちも抱きつつ見送りました。
お昼には、登山隊の”鏡交信”を行いました。夫神岳からは太陽が背中側になり、合わせ鏡で何とか光を学校側へ届けようと試み、一瞬ではありますが子どもたちからの光が届きました。十観山からも試みましたが、頂上が少し茂みになっていたこともあり、光を届けることは叶いませんでしたが、青木村にお勤めの保護者の皆様の中には、お昼の時間に外へ出て、鏡の交信をしていただき、実際に鏡を2つの山へ向けて届けてくださいました。交信をしてくださった保護者の皆様ありがとうございました。
午後になり、1年生を皮切りに、学校へ戻ってきました。大きな怪我をすることなく戻ってくることができました。初めて遠足を体験した1年生に戻ってきたところをインタビューしてみました。すると、
「歩くのが楽しかった」「お弁当がおいしかった」「蒸したまごがおいしかった」とコメントをいただきました。そして最後、Kさんが「まずかった」と口にしたのです。私は、手作りのお弁当に対して、「どうして”まずかった”と表現したんだろう」と思いました。そして、Kさんは、少し間を空けた後、「歩くのがね!!」とニコッと答えました。お弁当がまずかったのではなく、歩くのが”まずかった”のです。きっと、「とってもつかれた。もうくたくただよ!」を「まずかった」という言葉に置き換えて表現したのでは?そんな風に感じました。
今日は、お家に帰って、わたしにとっての遠足エピソードを子どもたちはたくさん語るかと思います。どんなエピソードをお家の人たちに届けるのかな??興味津々です。
雨を降る時間を、遠足終了後にしていただいた、お空の神様、ありがとうございました。
5月7日(水) 久しぶりの学校 そしてハプニング・・・ ~2年生~
大型連休が明け、5月が始まりました。登校してきた子どもたちからは、「○○へ行ってきたよ」「親戚が来て、一緒に遊んだんだよ」などなど、様々な連休中の出来事が聞こえてきました。
そんな朝のことです。校長室でパソコンと向き合っていると、2年生のただならぬ声が聞こえてきました。担任の先生が下駄箱で靴を履き替えているところに2年生のKさんがやってきて、
「先生大変、畑のキャベツが食べられちゃってた。ほぼ全滅だよ」
と担任の先生に様子を伝たのです。おそらくKさんは、4月に植えたキャベツの苗の様子が気になり、登校するや否や畑へ駆け出し、様子を見てきたのだと思います。
この日の放課後、担任の先生に朝のやりとりについてお聞きすると、キャベツを植えた時に、虫に食べられるかもしれないからと不織布でキャベツの苗を囲う作業をしたことを教えてくださいました。Kさんは、この作業をしたから、「きっと連休中も虫に食べられることなくキャベツが育っている」と思い、キャベツの様子を確かめに行ったのだと思います。ところがどっこい、まさかの事態(風にあおられ、覆いかぶせていた不織布がめくれてしまった)になっていて、居てもたってもいられなくなり、少しでも早く担任の先生に報告したくなったのです。
Kさんの行動は、”自分ごと”になっているからこその行動でした。2年生は、学校の畑を利用して大豆をはじめ、様々な野菜を育てるようです。夢見る大収穫にたどりつくまでには、今回のような思わぬ事態が起こるかもしれません。スムーズにいかないからこそおもしろく、そういうことがあることによって、学校の畑が、大切な”わたしたちの畑”になっていくのだと思います。今後も楽しみです。
5月2日(金) 残念ながらの延期 ~春の遠足~
いよいよ5月となりました。もう4月が終わったと思うと、本当に月日が経つのは早いです。
本日は、春の遠足日でした。が・・・、残念ながら天気が味方せず、延期となりました。朝、学校前の横断歩道に立ち、子どもたちどんな表情で登校してくるかなと思い、子どもたちが来るのを待っていましたが、「おはよう」と声をかけると、元気なあいさつが返ってきました。少し、安心しました。
「お弁当忘れなかった」と声をかけると、「持ってきたよ」「決まってるじゃん」の声。そんな中、3年生のHさんとRさんに、「お腹がすいたからって、二時間目休みに食べちゃだめだからね」と声をかけると、2人は笑い、Rさんは「食べるわけないじゃんと」と言い、それに続いてHさんが、
「(Rさんを見ながら)そんなことしないよね。(私を見つめ)あ~でもね、私、大好きなお母さんが作ってくれたお弁当だから、お昼まで食べちゃいけないことは分かってるけど、食べたくなっちゃうかも!」
と話しました。心がぽかぽかになりました。そして、Hさんが、どれほどお母さんのことが大好きなのかが伝わってきました。
今日が天気であれば、おそらく私は、横断歩道には立っていなかったと思います。天気が味方してくれなかったことは本当に残念ですが、Hさんの素敵な言葉に出合えたことは幸運でした。
お昼の時間に各教室にお邪魔をすると、おいしそうにお弁当を食べていました(すでに食べ終えている子もいました)。「校長先生見て~。この○○、おいしそうでしょ」とニコニコ笑顔でお弁当の中を紹介してくれる子が何人もいました。
来週の金曜日もお弁当です。☼次回は、それぞれの目的地で、お天気空の下、おいしいお弁当を頬張ってほしいと思います。
お天道様 なにとぞ青木小学校の大好きな子どもたちのため 5月9日は朝から天気にしてください☼
4月30日(水) 19年間 ありがとうございました ~お別れの会~
水曜日の朝の活動は、ドリルの時間ですが、本日の朝は全校集会を行いました。なぜ集まったかというと、これまで19年間、本校の図書館の先生としてお勤めされた先生が本日をもって退職されるため、先生とのお別れの会を行うためでした。
私から全校へ向けて、今日でお別れになってしまうこと、これまで19年間ずっと図書館にいてくださったこと、そして、19年前の6年生は現在31歳の大人になっていることを伝えました。
子どもたちから、この場で先生への感謝の気持ちを伝えてほしいため、急遽、子どもたちにマイクを向けました。すると、さっと2年生のTさんが手をあげ、「これまでありがとう」の言葉を伝えました。そこから他の学年も手を上げ、マイクをリレーし、最後は、6年生の図書委員会の委員長と副委員長から、お別れの言葉が届けられました。とても素敵な場面でした。
お別れをする先生からも子どもたちへメッセージが届きました。「ぜひ、本を手に取って、めくってください。そして、大好きな本に出合ってください」と。思いのこもった、温かなメッセージでした。メッセ時をいただいた後、全校で、校歌を歌いました。お別れする先生たった一人のため、全校一人一人が精一杯の歌声で、校歌のメロディーに乗せ、感謝を届けることができました。
明日からは、新しい図書館の先生が一人で担当します。この1ヶ月は退職される先生と二人で引き継ぎも兼ね図書館に居ました。19年間勤め培ったノウハウを受け継いだと思います。やる気に満ち溢れると図書委員会とも連動し、素敵な図書館の世界ををつくってくださるはずです。お楽しみに!!
本は、そこに居ながら、様々な世界へ連れて行ってくれる、魔法の本です。私自身、子ども時代にたくさん本を読むことはなく、本の素敵さに気づいたのは大人になってからでしたが、ぜひ、最後のメッセージの通り、本を手に取り、本をめくり、その本が連れてってくれる素敵な世界を感じてほしいと思います。
保護者の皆様も、お気に入りの本に出合える機会をつくってほしいと思います。あるいは、素敵な絵本を読み聞かせしてほしいと思います。アナログだからこそ感じるものがきっとあるはずです。
4月25日(金) 細かなところにもこだわって ~体育集会~
朝の時間、先週に続いての体育集会が開かれ、『ラジオ体操』をしました。体育主任の先生が担当し、”細かな動き”にこだわってラジオ体操をしました。
なぜこの時期にラジオ体操なのか・・・。それは5月31日に行われる”ある行事”に向けてです。そうです、『運動会』です。昨年度から、運動会を秋開催から春開催へ移行しました。理由は熱中症対策です。前年度はじめて行いましたが、子どもたちからも、保護者からも好評で、引き続いての春開催運動会となりました。運動会プログラムの1番が、この『ラジオ体操』なのです。腕の回し方、腕の伸ばし方、どのタイミングでかかとを上げるのかなどなど、いくつかのポイントを意識しながら一回通して行いました。私も最後方から、全校のみんなと一緒に、体を動かしました。たかがラジオ体操、されどラジオ体操です。細部にこだわりラジオ体操をすると、1回やるだけでもハーハーです。全校と一緒に、活動的な時間を過ごさせてもらいました。
会の最後に、体育主任の先生から、「次、ラジオ体操をするのは、校庭になります。その時には紅組白組も決まっています」と、全校に向けた話がありました。次回の時には、運動会当日まで、1ヶ月を切っています。きっと、運動会当日は、あっという間にやってきます。学年ごとのかけっこ(短距離走)に、表現に、玉入れに、児童会種目に、5,6年生の発表に(今年は何に挑戦するのかな?ワクワク)と、昨年の運動会を思い出すと、もう心は”踊る踊る”であります。
今、この校長日記を打ちながら、外を眺めると、目の間には校庭です。5月31日には、テントが設置され、綺麗に白線が引かれ、空には万国旗がはためく。トラックの周りには多くの保護者の皆様が集い、我が子の躍動する姿を見つめます。今年ならではの、今年の全校でしかつくれない今年限りの運動会。こうご期待です!!
4月24日(木) 私の決意を疑問を伝え合う ~第1回児童総会~
6時間目に、今年度第1回目の児童総会が開かれました。今年度の児童会活動目標(スローガン)
「みんなでつくろう 楽しい青木小学校」
が発表され、このスローガンを受けて、自分はどうしたいのか(自分たちにできることの提案)を発表し合いました。
「あいさつを頑張りたい」「委員会で新しいことを考えて提案したい」「当番活動を忘れずやりたい」など、わたしが考える”自分にできること”を全体の前で発表しました。勇気をもって発言する姿が、とても頼もしく感じました。
それぞれの委員会から年間の活動計画が発表され、質問・意見・要望を出し合う時間となりました。一人の子が、すっと挙手し指名されると、「どうして、清掃の時間に赤白帽子を被らないといけないんですか」と学校をきれいにする委員会へ質問をしました。しばしの沈黙の後、議長から「みなさんはどう考えますか」と全体への投げかけがあり、質問をした子が再度挙手し、「私は、正直言って、かぶりないといけないからかぶっているだけで、かぶらなくてもいいんじゃないかなって思う」と発言しました。すると、全体の前に座る委員会の役員の子が、「頭を守るために、それから、清潔を守るために帽子をかぶります」と質問に対しての返答をしました。隣に座る委員会の仲間と、近くに座る他の委員会の仲間と相談し、生み出された回答でした。
このやりとり1つをとっても、学校生活の”当たり前”の中にある問いを全体で共有し、その問いに対してみんなで考えられたという事実に、自分たちの学校をよりよくするために考え合えることのできる子どもたちであることを強く感じました。全校みんなでつくる、子どもたちの感覚でつくりあげる楽しい学校になっていく予感がしました。
総会が行われる中、議長を担当した子は、指名をするとき、終始「○○さんお願いしまます」「○○さんの考えをお願いします」と一人一人の名前を呼んで指名していました。この姿もとっても温かな姿に見えました。学級はもちろん、全校一人一人がみんなのことを名前で呼び合えるそんな温かな、より楽しい青木小になっていくことも感じました。素敵な児童集会でした。6年生のみなさん、今年ならではの児童会活動を期待しています!!
4月23日(水) 安全に歩き、安全に運転する ~交通安全教室~
朝の時間から1時間目にかけて、交通安全教室が行われました。上田交通安全協会青木部会の皆様、駐在所の所長さん、村役場の担当の方にもご協力いただき、交通安全について考える大切な時間となりました。
1年生と2年生は、実際に学校周辺の道を1年生2年生がペアになって歩きました。実際の横断歩道を渡る時には、手前の場所でしっかりと止まり、車が来ないか、来ている車が完全に停止したかを確認し、手をしっかりと上げ渡ることができました。2年生は1年生に、「止まってくれたから渡るよ」「しっかりと手を上げてね」「渡ったら運転手さんにお辞儀をするよ」と優しく伝えている様子もありました。2年生になって間もないにもかかわらず、立派なお兄さんお姉さんになっていました。
3年生から6年生は、体育館で自転車の安全な乗り方・運転の仕方について学びました。自転車クラブに所属5年生のTさんがモデル走行をし、実際の様子を見つめながら確認することができました。後半は、自転車の運転についてのDVDを視聴しました。自転車を運転するということは、”被害者”のみならず”加害者”にもなる可能性があることを改めて確認することができました。
自転車に乗る(乗れるようになる)と、自分の力で行ける範囲(世界)が一気に広がることを、会の冒頭私から伝えました。自転車に乗るからこそ感じられる風、自転車に乗ることができるからこそ行ける場所があります。自転車は自分の世界を広げてくれるアイテムの1つです。そのアイテムを有効に使うためにも、安全のためのヘルメットを必ず着用し、交通ルールを守り、そして、安全協会の皆様が教えてくださった”こと”を忘れず、自転車に乗ってほしいと思います。もちろん、歩く時にも安全に気を配って歩きましょう。
4月21日(月) 桜は散れども・・・ ~休み時間~
週末の温かな陽気もあって、校庭の桜は一気に散り出し、葉桜と変わり始めました。桜の花の儚さを改めて感じさせられました。
そんな桜舞う校庭で、今日も子どもたちは、生き生きと遊んでいました。学年の枠関係なくサッカーを楽しみ、先生も混ざってキャッチボールをして、鉄棒で覚えたての技に挑み、ブランコではどっちが勢いよく漕げるかを競い、雲梯では6年生が優しく1年生を手助けし、ジャングルジムのてっぺんからは、「校長先生、ここだよ~」の1年生の嬉々とした声が聞こえてきました。
休み時間は、移動時間を合わせて20分間。この20分間は、子どもたちにとっては(も)、貴重な貴重な20分間です。そんな大切な20分間の営みの中で、おもいっきり体を動かすことで自分を感じ、友だちと群れ、関わることを通して友を感じ、遊びを通じて、自分自身を更新していってほしいと思います。私も時々、遊びに混ぜてもらって、子どもたちの”素”の姿に出会いたいと思います。
4月16日(水)② ちいさなちいさな 大冒険 ~1年生~
今日の朝は、この時期としては肌寒さ残る朝でしたが、写真の通り、雲一つない美しい朝でした。登校前の1枚のため、校庭に子どもたちは居ませんでしたが、校庭は子どもたちを待ちわびていました。
さて、2時間目休みのことです。1年生を迎える会を終え、一人また一人と校庭へ飛び出し、思い思いに遊び始めました。校長室から校庭を眺めると、ちょうど式台があります。その式台に3人の1年生が上がり、式台から飛び降りる遊びを始めました。その様子を見ていると、あることに気が付きました。それは、一人の子は、式台から飛び降りたことがなく、まさにそのチャレンジをしていたのです。お友だちがピョンと飛び降り上手に着地するのを見て、「次は、自分の番」と思い、足先を式台の端に持っていき、膝を折り曲げ、「よし行くぞ!!」と覚悟をするのですが、なかなか”降りる”までに行きつきません。何回か試みようとするのですが、しばらくすると両手を胸にあて、友だちに、「やっぱり怖い」と伝えているようでした。ちょうどこの時、教頭先生と他の学級の担任の先生が校長室へ来たので、状況を説明し、校長室から、「がんばれ、がんばれ」と言いながら、チャレンジし続けるRさんを見つめました。
そして、何回か友だちが飛び降りた後、2人の友だちはブランコのある遊具広場へ向かい、Rさんは、式台に一人、取り残されてしまいました。どうするんだろうと、心配と期待、両方の気持ちを抱きつつ見つめていると、Rさん、意を決して式台から飛び降りました。着地も見事に決まり、後を追うように遊具広場へと向かっていきました。
休み時間の音楽流れ、校庭で遊んでいた子どもたちが一斉に教室へと戻っていきました。私はすぐさま校長室を飛び出し、教室へと向かうRさんに声をかけました。「Rさん、冒険してたね。式台から飛び降りようとチャレンジしてたね!見事出来たじゃん。すごいよRさん。ところで、飛び降りた瞬間どうだった?」と聞くと、Rさんは、こう答えました。「えっとね。こうやって土に足が付いたでしょ。このときね、心までドスンっていうのが伝わってきた」と、両手を心臓の前に持ってきて、クルクル回しながらその瞬間の説明をしてくれました。
Rさんの冒険、大成功です。子どもたちにっての休み時間は、遊び尽くせる時間でもあり、と同時に冒険タイムでもあることを、Rさんが私に教えてくれました。次は、どんな冒険をするのかな・・・
4月16日(水) ようこそ1年生 ~1年生を迎える会~
2時間目に、1年生を迎える会が行われました。新6年生がプロデューサーとなり、企画ならびに司会進行をつとめました。
まずは入場です。BGMが流れ、花のアーチを6年生と手をつないだ1年生が入場してきました。入学式よりも穏やかな、そしてにこやかな表情でした。席にエスコートされ着席し、会のはじまりです。児童会長があいさつをし、その後、副会長が一人一人の1年生を紹介していきました。「○○が好きな、◇◇さん」です。この紹介で、一人一人が紹介されていきました。ドラえもん好き、でんぐり返し好き、スイカ好き、メロン好き、ピンク好き、などなど、バラエティーに富んだ「好き」が紹介され、とても和やかな雰囲気となりました。
紹介の次には、ゲーム「進化ジャンケン」で全校が交流をしました。まずはミミズ、次にはうさぎ、更にクマ、そして人間、最後は神です。4回連続でジャンケンに勝つと神となりステージに上がることができる。こういうルールでした。3回行われました。1回目にはジェスチャーをせずジャンケンをしていたので、ステージにいる児童会の役員から、「ミミズは這いつくばる、ウサギはぴょんぴょん歩く、クマは腰を低くしノソノソと歩く、そして人間は普通に立ってジャンケンをする」と実際にポーズをとりながら説明をしたおかげで、2回目、3回目は、全校がミミズ、ウサギ、クマの真似をしながらのジャンケンタイムとなりました。
ゲームを楽しんだ後は、1年生からお礼のメッセージが発表されました。声をそろえて、「ぼくたち、わたしたちのために、楽しい会を開いていただき、ありがとうございました。これからも、たくさん教えて、たくさん遊んでください。よろしくお願いします」と、2年生から6年生までのお兄さんお姉さんたちに向けてお礼とお願いを発表しました。きっと、休み時間や昼休みには、1年生がたくさんの学年の人たちと遊ぶ姿が見られるはずです。
6年生のみなさん、準備期間が限られる中、全校が楽しめる会を企画し、実行してくれてありがとうございました。全校が楽しむことができました。児童会活動は、6年生が主役となり、学校をよりよく、そしてより楽しくなるにはどうしたらよいかを考え、実行していく活動です。昨年の活動をより進化させ、今年の6年生だからこそ生み出せる企画、期待しています。
4月15日(火) 春を見つける 感じる ~2年生~
5時間目、雨雲に覆われていた空が瞬く間に晴れ渡り、満開の桜が風に揺られていました。そんな校庭から楽しそうな声が聞こえてきたので、お邪魔しました。桜の木の下に集まっていたのは2年でした。2年生は2クラスが1つのクラスにまとまり、スタートしたばかりですが、元○○組など関係なくかかわっていました。
私を見つけると、「校長先生、春を4つ見つけたよ」「ぼくは6つだよ」と教えてくれました。どうやらこの時間に『春』を4つ以上見つけることが課題だったようです。「さくらでしょ、すみれでしょ、つくしでしょ・・・」と、見つけた植物(花)の名前を伝える子もいれば、「さくらでしょ、それからね、紫色いろの小さなつぶつぶの花」と教えてくれた子もいました。もしかしたらタチツボスミレの花のことを言っているのかもしれません。翌日の授業で見つけた春を発表するようです。きっと、今は名前が分からず”紫色の小さなつぶつぶの花”と表現した花の名前を、友だちとのやりとりを通してその花の名前を知ると思います。図鑑を通して知ることももちろんいいですが、友との関わり、やりとりを通じて得る学びも素敵です。
10分ほど、2年生と担任の先生との時間にお邪魔をさせていただきましたが、子どもたちの目線を見ても様々なでした。足元を見て春を探す子がいるかと思えば、目線を上にして春を探す子もいました。目線を上にして春を探していたМさんが、「先生見て、桑の木に葉っぱ見つけた」と発した瞬間がありました。2年生は1年生だった去年、ブランコとプールの間にそびえる桑の木に手を伸ばし、めいいっぱい桑の実を取って食べていました。その時私も「取って(採って)取って(採って)」とたくさんせがまれました。葉っぱを見つけたМさんももちろんそこにいました。あの時わたしたちにおいしい実を届けてくれた桑の木に、緑色の立派な葉っぱがあることに気づいたのです。桜はもちろん、桑の木の葉っぱからも春を感じたこの時間、子どもたち、本当に生き生きとしていました。振り返りの時間が楽しみです。
4月14日(月) 命を守るために ~避難訓練~
今年度1回目の避難訓練が行われました。朝方少し雨も降っていましたが、校庭に避難する通常の避難訓練を行うことができました。
非常ベルが流れ、「給食室から出火、校庭に避難しなさい」の放送で、全校が一斉に校庭へ避難をしました。防災ずきんをかぶり、頭を保護しながらの避難でした。全校が避難できたことを確認し、職員の係活動を終え、川西消防署の消防士さんから講評をいただきました。「”お・は・し・も”をこれからも意識すること」「ハンカチを身に付け、避難の時には煙を吸わないようにすること」など、大切なお話をしてくださいました。子どもたちは、消防士さんの話を真剣な眼差しで聞いていました。避難訓練がとても大切なものであることを分かっているからこその姿でした。
避難訓練を終え、消防士の方に改めてお礼を伝えると、消防士さんから、「とてもいい避難訓練でした。ここまで静かに、誰も話すことなく避難する訓練を見ることはめったにと言いますか、ほとんどありません。すばらしい子どもたちですね」とお褒めの言葉をいただき、私からは、「日頃おとなしいから静かにできるのではなく、話し合いをするときには自分の考えを堂々と言えて、休み時間にはおもいっきり元気に遊ぶ子どもたちです。遊ぶときは遊ぶ。話し合う時は思いっきり話し合う。そして静かにすべき時には静かにできる。そういうメリハリのある素敵な子どもたちです」と、日頃の様子をお伝えしました。
とてもいい避難訓練となりました。日頃から、自分の命を大切にし、友を大切に思える。そういう子どもたちへとさらに成長していってほしいと思います。
4月11日(金) 初公開 ~参観日~
今年度1回目の参観授業がありました。また、年度当初の参観日なので、参観授業後にはPTA総会と学級懇談会も行われました。
我が子の授業の様子を見つめようと、大勢の保護者の皆様の参観のもと各教室で授業が行われました。粘土の作品を作ったり、音読をグループ発表したり、担任の読みきかせから授業が始まったり、友だちが思い浮かべている言葉を連想したり、友だち・仲間について考えたりと、それぞれの学級で、担任の先生の持ち味を発揮しながらの授業が展開されました。途中途中、子どもたちは教室の後ろや横側で授業を参観する自分の親を見つけようとする姿も見られました。やっぱり子どもは、自分を見てもらえていることがうれしいのです。
参観後のPTA総会では、私から保護者の皆様へ向けて今年度の取り組みなどについてお伝えをさせていただきました。3つの根っ子(思い合いの根、学び合いの根、関わり合いの根)を伸ばすことを今年度の重点においていること、お仕事ゼミに挑戦することなど話をしました。オンラインの不具合が冒頭で起こり、始まりまでに時間がかかってしまいました。反省点です。
参観後、廊下で数名の保護者の方を話をする機会がありました。ご家庭での様子を聞くこともできました。やはり、対話が一番です。一人でも多くの保護者の方と、年間を通じて対話していきたいと思います。保護者の皆様、ぜひ、お声がけください。
4月10日(木) おいしい給食はじまる
今週8日(火)から、さっそく給食が始まりました。8日(火)は2年生以上で、やきとり丼が登場しました。私はこの日、終日出張だったため、このやきとり丼を食べることができませんでした。(残念…)。昨日(9日)から、1年生の給食も始まりました。上小管内の小学校で、1年生の給食開始が一番早い学校だったこともあり、メディア取材もありました。この日は、みんな大好きエビフライが登場しました。私も食べましたが、サクサクのパリパリで揚げたてでした。自校給食だからこそ味わえる触感でした。1年生の教室では、1年生が食べながらの取材を受けていました。「給食どう?」と聞かれ、もぐもぐするのを一時停止し、「おいしい」と取材の方の瞳を見つめ答えていました。その伝え方と「おいしい」と発したトーンを聞いて、本当においしい気持ちで食べていることが伝わってきました。栄養士の先生、調理員の先生方のおかげで、毎日おいしい給食を食べることができます。食べるたびに感謝したいと思います。そして、今後ともおいしい給食、よろしくお願いします。
ちなみに本日は、チリコンカンでした。給食の定番です。明日の給食も楽しみです。そして明日は、参観日があります。大勢の方ご来校いただき、授業場面で見せる子どもたちの素敵な姿に、子どもと先生の素敵なやりとりに出会ってほしいと思います。
4月8日(火) 多くの人に守られている
本日より、令和7年度が本格始動しました。上小管内の多くの小学校は、月曜日から始まっていましたが、本校は先週の土曜日が入学式だったため、今日から始まりました。
今週は、春の交通安全週間とも重なっているため、子どもたちの登校時間に合わせ、地域の方が安全を呼びかけるため、道路に立ち、啓発活動を行ってくださいました。上田警察署の方、駐在所の所長さんをはじめ、安全協会青木支部、役場、教育委員会、森林組合、PTAの方々など、総勢50名ほどの方が、旗を持ち、立ってくださいました。子どもたちは、立ってくださっている方々に大きな声で「おはようございます」の挨拶をすることができていました。横断歩道を渡る時には、しっかりと手を上げ、渡る意思表示を示し、渡ることができていました。
今月中は集団登校が続きます。きっとその日その日で、地域の方に会うことがあるかと思います。子どもたちから元気に、「おはようございます」が言えるといいなと思います。
今回の街頭指導の担当の方と立ち話をする中で、「今年は50人に迫る方が街頭指導に来てくださいました。用意していた旗が例年だと余るのですが、今年は足りなくなるくらいでした」
と話してくださいました。地域に暮らす多くの方が、朝の貴重な時間を子どもたちのために費やして下っているということ。地域の皆様に子どもたちが守られていることへの感謝はもちろん、地域の宝である子どもたちが、生き生きと通える学校でなければならないと改めて感じる時間にもなりました。
街頭指導を終え学校へ戻ると、「早く昇降口を開けてよ」と昇降口前に並び、きらきらした目で私に訴える子どもたちがいました。地域の温かさを感じ、子どもたちの瞳を見つめ、「この子たちのために精一杯に努めねば」と背筋がピンと伸びる朝となりました。
4月5日(土) 進級おめでとう!入学おめでとう!さあ始まりのとき!
本日、始業式と入学式が行われ、青木村立青木小学校の令和7年度がスタートしました。前日の中学校の入学式に続き、この日も入学式にふさわしい、すばらしい天気に恵まれました。
まずは始業式から行われました。新任の先生が入場すると、子どもたちは一人一人の先生方を見ようと、一人、また一人と目線を移していました。「私の担任の先生はこの中にいるのかあ」そんな声が聞こえてくるようでした。
新任の先生とお会いした後は、担任、専科、様々な担当の先生の紹介がありました。子どもたちは一喜一憂でした。すべての先生の紹介の後、私から、進級おめでとうメッセージと今年度のお願い(大事にしたいこと)を全校に伝えました。伝えたことは、
☆3つの”根っこ”を伸ばすこと
①思い合いの根っこ ②学び合いの根っこ ③関わり合いの根っこ
☆青木をたくさん歩こう
以上3つのこと+α(アルファ)を伝えました。
友を思い、他者(ひと)のことでも自分のことのように感じることができれば思い合いが芽生え、
「なぜ、どうして」をみんなの「なぜ、どうして」にし、とことん追究することが学び合いとなり、
日頃の仲間だけでなく、活動から生まれる無縁の人との関わりを自ら求め、関わり合いを作り出す。
「こういうことのできる1年にしたい」といった思いを込め、伝えました。そして、歩く機会を作ってほしいことも伝えました。友だち、あるいは家族で、ちょっと外へ出て青木を歩くと、きっと様々な発見が生まれるはずです。私自身も朝、住宅のまわりを歩くだけでも、朝の空はいつも同じと思っていても、毎回違った朝を迎え、鳥のさえずりに出合うだけでも心がいやされます。日頃暮らしている青木です。分かっているつもりでいても、「へ~~」ということもたくさんあるはずです。「歩いてみてね」そんなメッセージを送りました。
始業式の次は、入学式です。新1年生を、2年生から6年生、保護者、ご来賓の皆様、そして私たち教職員でお迎えしました。1年生の歌声すばらしかったです。1年生に向けて、児童会長がお迎えのあいさつをしました。「小学校は、みんなで学んだり遊んだりして、きずなを深めるところです。ぼくたち6年生に、何でも聞いてください」と力強く発表しました。6年生のみなさん、お願いします。
入学式を終え、各教室へ戻ると、2年生から6年生までの教室で、初めての学活が行われました。先生自ら自己紹介し、子どもたちも自己紹介をする学級もありました。写真は、さよならの場面です。新しい先生と初めてのジャンケン。勝った負けたというよりも、この瞬間を楽しんむ、子どもたちと先生の姿がありました。
あっという間だった1日。207日分の1日なわけですが、貴重な1日と言いますか、半日となりました。火曜日から、いよいよ本格スタートです。1年生が、一日でも早く学校になれ、各学級学年で、様々な活動が始まります。こうご期待です!!
4月4日(金) 中学そして小学校
本日、すばらしい天気の下、青木中学校の入学式が行われました。来賓席に座らせていただきました。
今年度は、この3月に小学校を卒業した6年生が新1年生として入学するので、どんな姿で入場してくるのか、とてもわくわくした気持ちで参加することができました。
入場の音楽が流れ、体育館の扉が空き、昨年度の児童会長を先頭に、一人また一人と入場してきました。小学校での卒業式から2週間と少ししか経っていないのに、何だかその時よりも大きくなっているように感じました。新入生代表の挨拶では、元児童会長が、児童会で得た想像力を発揮すること、そして、チャレンジチェンジの精神で成長していくことを力強く発表しました。小学校を巣立った子どもたちが、いよいよ中学校の生徒の一員として、一歩を踏み出しました。”わたしならでは”を遺憾なく発揮し、大活躍してほしいと思います。
さて、明日は小学校の番です。新1年生が入学をします。本日、教職員一人一人、1年生のため、全校のため、保護者の皆様のため、精一杯に会場の体育館をはじめ、校内の整備を行いました。各教室も、進級した子どもたちの受け入れ態勢万全です。
明日の朝から、子どもたちの元気な声が校内に響くと思うと、「早く明日になれ~~」と思ってしまいますが、さすがに時間を早くすることはできません。残念無念・・・。
新鮮な気持ちで登校する子どもたちと、入学式前に行われる始業式で、今年度の私自身の意気込みを伝えられたらと思います。そして、新しい先生をお迎えした新青木小職員一同と全校みんなで、令和7年度の最高のスタートを切りたいと思います。
オン ユア マーク・・・、セット・・・
4月1日(火) いよいよ始動
令和7年度が始まりました。保護者の皆様、地域の皆様、ホームページをご覧くださる皆様、令和7年度もよろしくお願いいたします。
朝、自宅の窓を開けると、雪が降っていました。4月に入っての雪は、さすがに珍しいですが、空から舞う雪たちも、新しい先生方をお迎えしてくださったのかもしれません。
本日は、辞令交付式から始まり、新任の先生方を職員室で熱烈歓迎し、お昼には歓迎の昼食会が、本校のランチルームで行われました。新任の先生方はもちろん、前年度からお勤めされている先生方も全員で自己紹介をしました。おいしいお弁当を食べつつ、楽しい会話も生まれ、緊張感漂う新任の先生方の表情も、一気に穏やかになりました。
午後は、あいさつ回りがありました。小学校と中学校と合同で行いました。役場では、新任職員紹介の後、北村村長からお言葉をいただきました。国宝があること、1300年前の人々が青木を通る東山道で、人々が往来していたこと、くつろげる温泉があること、五島慶太翁の生誕の地であることなどお話いただき、激励のお言葉もいただきました。各所を回ったわけですが、村の皆様が本当に学校を大事に考えてくださっていること、子どもたちの未来を支援くださっていることが伝わってきました。
新たな先生をお迎えしての新たな青木小学校の幕開けです。5日には、子どもたちの声が聞こえてきます。精一杯の準備をし、始業式と入学式を迎えたいと思います。